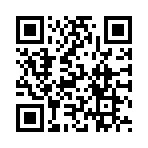2024年12月06日
「海燕社の小さな映画会2024 11月会」『武州藍』『芭蕉布を織る女たち-連帯の手わざ-』
海燕社の小さな映画会2024 11月会
【2024.11.17(日)/沖縄県立博物館・美術館3階講堂
13:15受付開場/14:00開会/15:30終了】
鑑賞料:無料(要予約)
沖縄県立博物館・美術館 特別展『芭蕉布展』×海燕社の小さな映画会2024 コラボ企画
〈上映作品〉
『武州藍』
(1986年製作/民族文化映像研究所 製作/43分)
『芭蕉布を織る女たち-連帯の手わざ-』
(1981年製作/ポーラ伝統文化振興財団製作/桜映画社 村山英治監督/30分)
〈入場まで〉
1.受付:①10周年記念栞進呈
②資料配布
2.手指アルコール消毒(各自任意:劇場入口設置)
3.入場着席:自由席
※配布資料
(チラシ2枚、アンケート用紙、案内カード、下敷き、クリアファイル、鉛筆)
<プログラム>
1.開会
2.主催挨拶(城間あさみ)
3.『武州藍』(1986年/民族文化映像研究所製作/43分)
4.『芭蕉布を織る女たち-連帯の手わざ-』
(1981年/ポーラ伝統文化振興財団製作/桜映画社 村山英治監督/30分)
5.アンケート記入
6.閉会
<スタッフ> 5人(海燕社2人、アルバイトスタッフ2人、映写スタッフ1人)
準備・片付け:全スタッフ
受付会場全体総括(海燕社2人)
受付:(アルバイトスタッフ2名)
上映:(映写スタッフ)
司会:(城間あさみ)
〈後援〉沖縄県/那覇市
【お客様の感想(アンケートより)】
だいぶ着物姿も見れなくなりましたね。
芭蕉布を続けてほしいです。
大変なお仕事ですね。
頭が下がります。
頑張って下さい。 女性
埼玉での藍は、疲れたとき、清酒を入れていたが、
沖縄では、泡盛を使用していた。正に藍づくりは、
地域に根ざしているものだと感じた。 10代男性
今まで藍染めや芭蕉布について全然しらなかったけれども、
今回の映画会を通してとても興味が湧きました。 10代女性
「武州藍」と「芭蕉布を織る女たち」
どちらも歴史ある職人の技という印象をうけて、
それをこのような映像にのこして、今の私たちでも
見ることができ伝えられているのがとても良いことだと思い、
昔の人の努力やよく考えられた技術が伝わってきました。
また、芭蕉布で藍が出てきたのも、前に観れていたのも
関係性がよく知れて良かったです。 10代男性
今回の映画会は、
大学の課題の内の一つにあり、興味を持ったので観にきました。
昔の映像と共に藍の作り方使い方を知れてよかったです。
特に、藍が団子になっているものや、
藍で染めた織物を作っているのも初めて知って驚きました。 10代男性
昔ながらの伝統を引き継いで協力している姿に感動した。
藍は生きているということを感じられた。 20代女性
芭蕉布展とのコラボ企画ありがとうございました。
布の背景にある生活の息づかいを感じさせる映像を
これだけたくさんの人にみてもらえて嬉しいです。 20代女性
面白いです。
よく芭蕉と藍染のことを知った。 20代女性
このタイミングで藍と合わせての上映、大変良かったです。 20代女性
映像で見たことで、芭蕉布づくりの大変さを感じることができた。
これから芭蕉布展に行こうと思うので、事前に詳しくなれてよかった。 20代男性
何工程もかけて作る職人の思いというものが
よく伝わる良い映画だったと思います。 20代男性
とても興味深い内容で良い学びになりました。 20代男性
身近にある染物が作成される過程には
農耕の知恵や工夫が詰められており、
農家、染物職人、織物職人、
様々な人の苦労や努力が知れて勉強になった。 20代男性
先人達の知恵や工夫を沢山知ることができて良かった。 20代男性
藍や芭蕉布について今まで知らなかったので、とても興味深かったです。
もしアンコール上映があればまた観たいと思いました。 20代女性
芭蕉布が出来るまでの工程の多さ、複雑さに驚きました。
こういうものにお金を出したいと思いました。
芭蕉布を購入できる機会があれば、是非購入させて頂きます。
戦争中での辛い記憶も乗り越え、喜如嘉の芭蕉布を守ってくださった
平良さんと喜如嘉の女性方のおかげで、無形文化財にも選ばれ、
彼女たちにとっては日常の一部かもしれませんが
沖縄に大きな貢献をされており、素晴らしいと思うと共に、
もっと知られてほしいと思いました。
このような機会がなければ知ることができなかったので、
もっと大衆的に知ってもらえるようなきっかけが必要だと思いました。
この度は素敵な上映会をありがとうございました。 20代女性
武州藍と芭蕉布の2本立てで観ましたが、
日本、沖縄の農耕文化に根差した手仕事に感動します。
植物の栽培の過程から、染め織物につくり上げていくまでの
全体をつかむのにとてもいい教材でもあると思います。
定期的に見直したい映像作品と感じます。 30代男性
藍と芭蕉布あわせて観ることができてよかったです。
とても良い企画でした。
芭蕉布展の案内もありがとうございました。 30代女性
芭蕉布を作るためにあれだけの手順と
手間があったことにおどろきました。
沖縄の伝統として残してくれたことに感謝します。 30代女性
藍はどの地域でも‶生き物‶として扱っていて興味深かったです。
また、芭蕉布(布)になるまでの工程が多く、
手間が掛かっているからこそ
触れた時にあたたかみを感じるのだと思いました。 30代女性
藍染も芭蕉布も存在は知っていたが
その製造過程は知らなかったので、今回映像で見ることで
複雑かつ繊細な工程を知ることができました。
いずれも手間暇かかった細かい手作業で、
その技術を絶やさぬよう取り組まれた方々に敬意を抱きます。
変わっていくもの、変わらないもの、人の価値感もそれぞれですが、
伝統というものは絶えず残って欲しいと思いました。 30代女性
喜如嘉の女性の美しさを感じました。
暮らしのなかに仕事があって、
自然のなかで人が生きているという感じがしました。
誰と競うでもなく、自らの手で、そして
地域社会の和のなかで生きる幸せを、
現代や将来の社会でも引き継いでいけたらと思います。 30代男性
貴重な映像が観れて、とても嬉しいです。
県外の工芸になかなか触れる機会がなかったので
埼玉の藍について学べて良かったです。
芭蕉は、昔と今の様子を照らし合わせて見ました。
また、改めて、機会があれば観たいです。
何度観ても学べる映画でした。
ありがとうございました! 30代女性
内容もとても勉強になりました。
スタッフの方も丁寧に案内して下さり、
チラシも集落内いたるところで拝見して良かったです。
次回の上映をとても楽しみにしています。
できれば、北部での上映会も企画して下さることを望みます。 40代女性
「武州藍」の職人さん方の手仕事にほれぼれしました。
工程ごとのこだわり、
藍を生き物として大切に向き合う姿に感動しました。
喜如嘉の女性たちのきずな、
村で大切にされている共同作業の様子がすばらしかった。
人の想いやくらしが織りこまれ編まれた布だと思いました。
平良敏子さんのお若い頃の姿を拝見できるだけで胸がいっぱいになりました。 40代女性
素晴らしい上映会でした。
古い撮影でも沖縄の伝統工芸や
それに関するテーマの映画を上映し続けて下さい。 40代男性
芭蕉布がたくさんの人の手によってつくられ、
またたくさんの人を支える存在だったのかなと思い、
その美しさの理由のひとつを見た気がしました。
どちらも貴重な資料映像で、見られてありがたいです。 40代女性
貴重な映像を見せていただき、大変勉強になりました。
その時代の風景や服装などとてもおもしろかったです。 40代女性
藍、芭蕉布と作り手の「想い」を学ばせていただきました。
しっかり心に刻みたいと思います。
貴重な映像をありがとうございました。 40代男性
すばらしく良い時間でした。
今後も楽しみにしています。続けてがんばって下さい。
他の沖縄のディープをクローズアップ楽しみにしています。 40代男性
とても良かったです。
ありがとうございました。 40代男性
今日、はじめて参加、とても良かったです。
特別イベントの上映会にも感動しました。
「芭蕉布」が生きもののよううに見えてきました。
とても好きになりました。
芭蕉布がもっと身近なものになることを願っています。
ありがとう、又、上映会に参加したいです。
スタッフさんおつかれさまです。 40代女性
どちらの映像も当時のありのままの様子や風景
(武州藍のほうでは子供がちゃんちゃんこを着ていたり、
芭蕉布のほうでは昔の那覇バスターミナルが写っていたり)が
記録されていて、とてもなつかしくノルタルジーな気持ちを味わいました。
前回に引き続き貴重な映像をこの場にいる方々と同時に共有することができ
嬉しく思うと同時に感謝の気持ちでいっぱいです。
芭蕉布につきましては、平良敏子先生のありし日の姿を拝見することができ
リアルタイムでお会いすることができなかった私には
ありがたい機会となりました。今回もありがとうございました。 40代女性
藍も芭蕉布も手間が掛かるものとは思っていましたが
ここまで大変な作業とは知りませんでした。
これからも日本の伝統、沖縄の伝統として
守っていって頂きたいと思います。 50代女性
今年、大宜味村の喜如嘉芭蕉布会館へお邪魔しましたが
今回の映画ほど詳しく理解することができていなかったなと痛感。
当映画にてより理解が増しました。
もっと多くの上映機会があるといいと思います。 50代女性
平良敏子さん、すばらしい人ですね。
芭蕉布展からの流れで鑑賞しましたが、
とても感銘を受けました。
お手配してくれた沖縄の友人に感謝です。 50代女性
武州藍
藍染めの工程、文化を知る事ができて、勉強になりました。
「小禄クンジーも同様な文化だったのかな⁈」と、
小禄出身なので想いをはせました。
とても興味深い内容でした。
芭蕉布を織る女たち-連帯の手わざ-
芭蕉布展(沖縄県立博物館美術館)
風にゆられて芭蕉布ワンピース展(南風原町立南風原文化センター)
喜如嘉の芭蕉布展(沖縄芸大)
を楽しんだ後なので「本当に丁寧な手仕事で素晴らしい文化だなぁ、」と
改めて感じました。 50代女性
すばらしかった。平良敏子さんはすごい。 50代女性
芭蕉布のできるまでを部分では見たことがありますが、
ここまで詳しいのは初めてみました。
わかりやすくてよかったです。平良さん、お若いですね。
前に倉敷に旅行にいったとき、大原美術館(?)で
経緯を知り、感動しました。 50代女性
この様な複雑な技が
どうして開発されたのか、
見ていてとても不思議だった。 50代男性
鑑賞できてよかったです。
ありがとうございました。 50代女性
日本、沖縄の素晴らしい手仕事、
豊かな暮らしを観ることができてとても良かった。
日本人であることをほこりに思えた。
伝統的なものをもっと生活に取り入れたい。 50代女性
映像と解説で武州藍と喜如嘉の芭蕉布について
よく知ることがでいました。
すばらしい映画の上映会を催して下さって
ありがとうございました。 50代女性
大変感動しました。
沖芸大の方でも芭蕉布展をやっていて、
たまたまこちらでは映画の上映もあるという事で
参加させて頂きました。
普段、米国に住んでいるという事もあり、
中々、沖縄の文化にふれる機会は少ないですが
(NYCではJapanSocieyで組踊などは見た事がありますが)
ぜひ、この映画、そして展示会をNYCの方、アメリカの方でも
やって頂いて、沖縄のすばらしいテキスタイル文化を知ってもらいたいですね。
今回はこういう機会を頂けて感謝しております。 50代女性
県内に産まれ育っていてもなかなか沖縄(琉球)の文化財について
学ぶ機会がなく細かな事まで学ぶ事が出来る良い時間を頂けました。
芭蕉布は知っていましたが、大宜味村喜如嘉にいらっしゃる女性の方の力で
現在まで受け継がれている事がすごくすばらしくこれから先も
沖縄の貴重な文化財として大切に守られて欲しいと思いました。 50代女性
村のどこそこでいつも芭蕉布の糸を積む女性たちが
いた時代の映像を見ることができました。
現代の風景とは違いますが、
たしかに今につながっているんだと思いました。
ありがとうございました。 50代女性
入館が遅くなってしまい、終わり15分前の鑑賞になりました。
でも、芭蕉布を織るのに、また織った後の作業の多さに
力仕事とこまやかさも必要だということを知ることができ
こんどから芭蕉布を見る時その作業を思いうかべたいと思いました。 50代女性
私の母も与那国織をしていて、
子や孫のために反物を織り、プレゼントしてくれた。
でも、映画で紹介されていたような工程をへて
織物が完成することを知らずに私は60歳を
目前に控えている。こんな自分を恥と思う。
織物をやっている人達の苦労を知らずにいたことが恥。
そして、平良さんの芭蕉布を守った心に感動した。 50代女性
なつかしい沖縄の風景とともに
大宜味、喜如嘉で、芭蕉布を再生、後世へとつないで
下さった平良敏子さんの姿に感動しました。
強い思いでつづけてこられたのだとしみじみ感じました。
芭蕉布は、ひとつひとつ丁寧な工程のたまものだと思います。
沖縄のほこるべき宝です。
今年、たまたま奥州浴衣を購入しました。
藍染の長板の工程など知ることができました。
浴衣を大切にしたいと思います。 50代女性
とても貴重な映像をありがとうございました。
芭蕉布が糸~布になるまで、大変な手間ひま、ご苦労がわかり
そんな芭蕉にとても興味がもてました。 50代女性
喜如嘉の村に生活の一部として根づいている芭蕉布織り。
村の女性達が協力し合い、伝統を守り、布を織っている姿に感動した。
これからもぜひ守り引き継がれていってほしい。
2つの映画とも自然の植物を相手に、染め、糸づくり、布を織ることを
記録していて、こういう記録を残すことが、これからの世代へとバトンが
引き継がれていくのでとても大切だと思った。
このような機会をこれからも設けてほしい。 50代女性
芭蕉布がこんなに手間ひまのかかるものだとは知らずにいました。
たくさんの沖縄の人に観てほしい作品です。
平良敏子先生のおだやかな表情ときびきび働くお姿が
とても素晴らしく感動しました。
すばらしい作品だと思います。ありがとうございました。 50代女性
藍、芭蕉布ともに良かったです。
藍は、種まきから染めまで見る事ができてよかったです。
芭蕉布は糸づくりから仕上げ、普段の生活の様子も見る事が
できてわかりやすかったです。平良先生、美恵子さん、お若い!
年をとっても、もの作りをする方々はお元気で輝いてすてきです。
先週の水害が心配ですが、どうかこの光景がずっと続くことを願います。 50代女性
武州が藍の産地ということは、大河ドラマを観て知ってはいましたが
実際どのように作られるのかは知りませんでした。
芭蕉もそうですが、まず植物を育てることからはじまって、
製品ができあがるまでにこんなに複雑な工程があり、たくさんの人々の手で
作られているのだということが、すごいと思いました。
今も、その技術は受け継がれているのでしょうか?
芭蕉布は高価でとても手に入れることはできませんが、
藍染の服は一着持っているので、
着るときには今回の映画を思いながら着ようと思いました。 50代女性
どちらの映像も、その土地に根付いた人々の営みとともに
栄えていった手仕事である事、そしてひとつひとつの作業の工程にかかる
手間ひま、難儀が、とても美しくどの作業も省略できない事が
私にはとても素晴らしく映りました。
武州藍も芭蕉布もどちらも(藍を育てていく、糸芭蕉を育てていくなど)
長い時間をかけて作られている事を改めて知る事ができて大変貴重な時間でした。
織りも染めもやはり祈りと希望がいつもそこに存在し、
作り手の方々の生きる喜びが共にあると強く感じました。
ありがとうございました。 50代女性
武州藍
藍染めの奥深さ、工程の細やかな作業を、初めて知ることができました。
泡のぶくぶくした状態になるまでには、数々の工程があるのですね。
職人さんの藍色に染まった手が格好よかったです。
芭蕉布を織る女たち
平良敏子さんの若かりし頃の映像を見るにたくましさをひしひしと感じました。
長く重い芭蕉布を、たらいでじゃぶじゃぶ洗う姿に
足腰の強さを感じずにはいられませんでした。
あの小さな体からあふれ出るパワーが
しっかり引き継がれていくことを心から願っています。
このようなすばらしいドキュメンタリー2本を
無料で鑑賞させていただきありがとうございました。 50代女性
とても勉強になりました。
ありがとうございました。 60代女性
芭蕉布は戦前、県内各地に在り、多くの担い手がいた。
戦後、喜如嘉だけがその伝統を守り存続したのは
平良敏子さんの力によるものだろう。
その想いはどこから来るものだろう。
喜如嘉の風土の力か。 60代男性
神奈川から来沖している友人を案内して参加。
芭蕉布展も観て、とても感銘したようだ。お連れできてよかった。
私も何度も観せていただいているが、次回の「むんじゅう笠」は
DVDを持っているので今回はパスします。 60代女性
衣料品の大量廃棄などが問題になっている
今だからこそ、ていねいな物づくりは
重要で必要になのだと感じました。 60代女性
もっと多くの方に観て頂きたいと思える素敵な映画だと思います。
今回、二度目でしたが、次の機会があれば又観に来ます。
ありがとうございました。 60代女性
藍について昔からの作り方、染め方、大変参考になった。
芭蕉布 制作工程はもちろん、
沖縄の昔ながらの民家や生活感がとても見れた事が良かった。 60代女性
大雨の中、まよいながら来たのだが
とても心おだやかで美しい作品でした。
ありがとうございます。
喜如嘉へ行ってその風を感じたい。
藍染は男の仕事なんだと思った。 60代女性
平良敏子が亡くなったのは残念です。
後継者が多数いることを願います。
武州藍を初めて知りましたが、とても素晴らしい芸術品ですね。
職人の知恵と技にただただ感心しました。 60代男性
「武州藍」の途中からしか鑑賞できなかったので
もう一度別の機会に上映してほしい。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
毎回見たいと思いました。 60代女性
素晴らしい映画上映をありがとうございました。
平良さんは御自分の使命をまっとうされたのだなぁと感じました。
喜如嘉の芭蕉布が一人の人の想いから
亡ばずに本当に良かったと思いました。
大原様に感謝です。
喜如嘉の芭蕉布を守り、生かしてくださったことに感謝です。
又、アンコール上映されることを願います。 60代女性
芭蕉布を織るのに手数がかかるというのは聞いていたが
これほどだと初めて知る。戦争やいろいろなことで
ほとんどすたれてしまったものが、喜如嘉でまた復興したというのは
ほんとうに奇跡で岡山の紡績工場の社長さんや柳宗悦さんには感謝である。
人間国宝にまでなった平良敏子さんの人となりと今に受け継がれるいしずえと
なった歩みがこの映画を見て知れてほんとうに有意義な時間でした。 60代女性
芭蕉布を守って育てた人々(女性)の生き様に大変感謝しました。 60代男性
昔の人のすばらしさにほんとうにカンプクの一言。
これからもいろいろなものをみてみたいです。 60代女性
平良さんには、ただただ頭が下がる思いです。 60代男性
芭蕉布作り、いろいろ手間などかけていて、すばらしい。
次世代の人々につないでほしい。又、県はもちろん
国などで代々守って欲しい。
武州藍、たくさんの人々の過程、手をかりて、すばらしい。
藍染めができて、すばらしい。これも日本の藍として守ってほしい。
ありがとうございます。 60代女性
喜如嘉にある芭蕉と木灰とシャリンバイから糸が生まれ
紡がれ織られ布になる。生産性向上や付加価値や品質管理はここにない。
あるのは、生活と連帯と感謝。
現代の日本がどこかに置いてきたものがここには全てある。 70代男性
見たい映画たくさんあります。 70代女性
良かったです。 70代男性
時間と労力をかけて紡がれる織の世界。
いつまでも継がれる事を祈るばかり。
平良敏子さんの情熱と村への思いを伝える上映でした。 70代女性
良かったです。
とくに「芭蕉布を織る女たち」は
観ているうちに涙が出てきました。 70代女性
宴会の余興等で着るぐらいしか機会のない芭蕉布でしたが
こんなにも手間ひまかけて布に織りあがるのだと初めて知りました。
ものすごく貴重な布なのですね。
芭蕉の木から布に織りあがるまでの過程がよくわかり感動しました。 70代男性
多くの方の協力で素晴らしい作品が生れてるのがわかりました。 70代女性
たいへん良い映画をありがとうございます。 70代男性
細かい作業や作品が一人一人の思いによって
できあがることを知ってよかたです。 70代女性
手仕事のすばらしさ、作品をみることができてよかったです。
ありがとうございました。 70代女性
若者へ
伝統の芭蕉布をつづける努力、
芭蕉布展をつづけてほしい。 70代男性
芭蕉布、藍染め、どちらもすばらしいですね!
生活の中に取り入れていきたいと思いました。
手間ひまのすごくかかった仕上げのもと
ステキな作品となるのですね。 70代女性
芭蕉布の工程については本も読んでおりましたので
ある程度は知っている心算でしたが、複雑で、気の遠くなるような工程は
予想を遥かに超えていました。このことは、武州藍についても同様です。
ただ、年月日も知りたかったです。
平良敏子さんの若いお姿は何歳位だったのでしょうか。 70代女性
[質問の回答]平良敏子さんの年齢について
平良敏子さんは1921年生まれのようです。『芭蕉布を織る女たち』の
製作年が1981年ですので、59才か60才だと思います。
芭蕉も藍も沢山の工程を経るのですね。
それを苦労っぽくなく、こなして楽しそうにやっていることがすごい。 70代女性
良かったです。
芭蕉布の値段が高いのがわかります。 70代女性
大変すばらしい映画でした。感動です。
喜如嘉の方々、芭蕉布作りを映像でみることが出来
また、映画を作ってくれたことに大変すばらしく、すばらしいことです。
平良敏子さん、芭蕉布をしている方々、とにかくすごいと思います。
上映会に来ることが出来、勉強になりました。ありがとうございます。 70代女性
自然と共に生きる、先人の知恵、
相手とじっくり付き合いながら、ひとつの物を作りあげていくことの喜び
今の時代に大切な事を教えてくれる作品でした。
感動しました。ありがとうございます。 70代女性
「芭蕉布を織る女たち」は以前にも見ましたが
「武州藍」は初めてで、藍の種をまくところから
藍染めができるまで詳しく工程が分かって良かった。
藍は沖縄では日かげか半日かげで栽培されていると聞いているが
日なたで育てているので驚いた。
沖縄の藍と違うのだろうか。 70代女性
[質問の回答]リュウキュウアイは日かげを好みますね。
藍の種類によって違うようです。武州藍のタデアイは
日光を好み日当たりのよい場所で育ててましたね。
武州藍、芭蕉布も、ひとつひとつの工程が
きちんとていねいに行われて布が完成していることがすばらしく、
生活の場と密着していることがよく映像化されていると感じました。
特に喜如嘉の女性達の生き生きとした姿が印象に残った。
今も喜如嘉にひきつがれていると感じる。 70代女性
とても大変なお仕事だと、ご苦労をおもいました。
現代においてずっと続けていく事は困難な作業だと思います。
記録を残すことがどんなに重要なことか、特に映像の力が大きいと思います。 70代女性
11/2に芸大で平良美恵子先生のお話を聞き
芭蕉布の事を初めて知り(県外人なので)映画も初めて見たのですが
びっくりする事ばかりでした。博物館のチラシで平良先生のお話しや
映画会がある事を知り、11/16、11/17と2日は博物館に来ました。
本当に皆さん苦労して文化をつないでこられたのだと頭が下がります。 70代女性
いづれにも共通する事だが
手間ひまが掛かり頭がさがる。
着物が好きで購入もするが、
琉球の伝統工芸は高額で手が出ない。
工程を知ってしまうと納得なのだが… 70代女性
感動致しました。 70代女性
すばらしい映画でした。 70代男性
今回の映画会は大変良かった。
芭蕉布の出来上がり、歴史の重みを感じました。
これからも小さな映画会がますます大きな映画会になりますように。
ありがとうございました。 80代男性
毎回、新たな感動を得ます。
手作業、伝統の奥深さを有難く見せてもらっています。
ありがとうございます。 80代女性
大変すばらしい。
沖縄の世界にほこる、すばらしいと思います。
「バショウ」の衣は、良い物です。
無地でバショウを作り、後であやを入れたらどうかと思いました。 80代男性
芭蕉布が布になるまですごい工程ですね。
昔の年配の人は、着物や洋服で着けていたのを思い出します。
祖母もバサーを洗たくする時は、クニブ(みかん)で洗ってました。
みかんで洗うとそれはきれいに鮮明に汚れも落ちていました。 80代女性
1.2編共大変良かった。
1本づつ上映した方が良かったのではないか。
2.取材時期が分からなかったが、最後に入れるべきと考える。
3.「芭蕉布を織る女たち」では、一着尺にどの程度の芭蕉布が使われ
どの位の時間がかかり、最終的にいくら位で取引されるのかが知りたかった。 80代男性
工芸の素晴らしさを再確認しました。
大変勉強になりました。 80代女性
・知識を広めるためとてもよかったと思います。
・手仕事のきびしさがわかった。
・奥深いきびしさがあることがわかった。 80代女性
こんなに素晴らしい映画を見ることが出来たのは
生涯忘れることが出来ない程感激した。反省するのみ。
平良先生を常に念頭に置き、残された時間を大切に生きたいと思いました。
先生を中心に織られた方達皆さんの
生き(活き)生きした姿をみることができたのも良かったです。 80代女性
芭蕉布工房で若い頃の敏子、美恵子さんのなつかしいお姿。
伝統を守ることのむずかしさ、受け継がれるのも御苦労様です。 80代男性
気の遠くなる程の過程を経て、出来上がる芭蕉布。
根気と愛で出来る布。永らく継承できる事を祈る。 90代女性
〈11月会を振り返って〉
「海燕社の小さな映画会2024」11月会、
ご鑑賞の143名のお客様、ありがとうございました。
「ポーラ伝統文化振興財団」様、「桜映画社」様、ありがとうございました。
「民族文化映像研究所」様、ありがとうございました。
11月会は沖縄県立博物館美術館『芭蕉布展』とのコラボ上映会が実現しました。
おかげさまでお客様に映画を無料でご鑑賞頂けることができました。
「沖縄県立博物館美術館」様、ありがとうございました。
後援の「沖縄県」「那覇市」様、ありがとうございました。
宣伝にご協力下さいましたマスコミのみなさま、ありがとうございました。
SNSや口コミで宣伝下さいましたみなさま、ありがとうございました。
みなさまに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
海燕社の小さな映画会は海燕社が「観たい」「観て欲しい」映画を
一緒に観ませんか、というスタンスで開催している映画会です。
劇場ではなかなか上映されない映像作品や旧作映画を上映しています。
映画の多様性、特にドキュメンタリーの幅広さを知ってもらいたいという気持ちもあります。
2024年の映画会は10年目を記念してご鑑賞者にオリジナル「栞」をプレゼントしています。
4月会は「獅子」5月会は「木」…上映作品に合わせてテーマを決めてデザインしています。
記念品を「栞」にしたのは、私が映画を観る前や観た後に原作本や関連する本を読みたくなるからです。
映画会の思い出とともに読書の時に「栞」を愛用して頂けたらうれしいです。
「海燕社の小さな映画会2024」の11月会は、
『武州藍』『芭蕉布を織る女たち-連帯の手わざ-』(以下『芭蕉布の織る女たち』)の二作品を上映しました。
沖縄初上映作品『武州藍』とアンコール3回目上映作品『芭蕉布を織る女たち』
この二本立を企画した理由を主催者挨拶で話しました。
きっかけは『芭蕉布を織る女たち』です。この作品で私が印象に残った言葉が「藍の花」です。
藍を、花のように見る、人のように思いやる、そこに惹かれました。
藍と藍をつなぐ上映会をしたいと『武州藍』と『芭蕉布を織る女たち』の二本立を決めました。
映像作品は完成後が大事だと思っています。
製作者としては観てもらうこと、観客としては観ること、
その二つを映画に贈りたいです。
「海燕社の小さな映画会」はその一役になって欲しいと願っています。
アンケートの提出して下さった139名様に感謝申し上げます。
アンケートのご協力ありがとうございました。
感想を書いて下さったのは120名様。感想ブログ掲載不可は15名様。
105名のお客様の感想を上記で紹介させて頂きました。
ブログでのお客様全員の感想を紹介する活動を続けています。
海燕社のスタッフだけで読むには惜しい内容の感想ばかりだからです。
映画会に来て下さった皆様と感想を共有したい、
映画製作者のみなさまにお客様の感想を伝えたい、
映画会に来れなかったみなさまに作品について伝えたい、
という思いで感想をブログで紹介しています。
これからも続けます。ご協力をよろしくお願いします。
城間あさみ
【2024.11.17(日)/沖縄県立博物館・美術館3階講堂
13:15受付開場/14:00開会/15:30終了】
鑑賞料:無料(要予約)
沖縄県立博物館・美術館 特別展『芭蕉布展』×海燕社の小さな映画会2024 コラボ企画
〈上映作品〉
『武州藍』
(1986年製作/民族文化映像研究所 製作/43分)
『芭蕉布を織る女たち-連帯の手わざ-』
(1981年製作/ポーラ伝統文化振興財団製作/桜映画社 村山英治監督/30分)
〈入場まで〉
1.受付:①10周年記念栞進呈
②資料配布
2.手指アルコール消毒(各自任意:劇場入口設置)
3.入場着席:自由席
※配布資料
(チラシ2枚、アンケート用紙、案内カード、下敷き、クリアファイル、鉛筆)
<プログラム>
1.開会
2.主催挨拶(城間あさみ)
3.『武州藍』(1986年/民族文化映像研究所製作/43分)
4.『芭蕉布を織る女たち-連帯の手わざ-』
(1981年/ポーラ伝統文化振興財団製作/桜映画社 村山英治監督/30分)
5.アンケート記入
6.閉会
<スタッフ> 5人(海燕社2人、アルバイトスタッフ2人、映写スタッフ1人)
準備・片付け:全スタッフ
受付会場全体総括(海燕社2人)
受付:(アルバイトスタッフ2名)
上映:(映写スタッフ)
司会:(城間あさみ)
〈後援〉沖縄県/那覇市
【お客様の感想(アンケートより)】
だいぶ着物姿も見れなくなりましたね。
芭蕉布を続けてほしいです。
大変なお仕事ですね。
頭が下がります。
頑張って下さい。 女性
埼玉での藍は、疲れたとき、清酒を入れていたが、
沖縄では、泡盛を使用していた。正に藍づくりは、
地域に根ざしているものだと感じた。 10代男性
今まで藍染めや芭蕉布について全然しらなかったけれども、
今回の映画会を通してとても興味が湧きました。 10代女性
「武州藍」と「芭蕉布を織る女たち」
どちらも歴史ある職人の技という印象をうけて、
それをこのような映像にのこして、今の私たちでも
見ることができ伝えられているのがとても良いことだと思い、
昔の人の努力やよく考えられた技術が伝わってきました。
また、芭蕉布で藍が出てきたのも、前に観れていたのも
関係性がよく知れて良かったです。 10代男性
今回の映画会は、
大学の課題の内の一つにあり、興味を持ったので観にきました。
昔の映像と共に藍の作り方使い方を知れてよかったです。
特に、藍が団子になっているものや、
藍で染めた織物を作っているのも初めて知って驚きました。 10代男性
昔ながらの伝統を引き継いで協力している姿に感動した。
藍は生きているということを感じられた。 20代女性
芭蕉布展とのコラボ企画ありがとうございました。
布の背景にある生活の息づかいを感じさせる映像を
これだけたくさんの人にみてもらえて嬉しいです。 20代女性
面白いです。
よく芭蕉と藍染のことを知った。 20代女性
このタイミングで藍と合わせての上映、大変良かったです。 20代女性
映像で見たことで、芭蕉布づくりの大変さを感じることができた。
これから芭蕉布展に行こうと思うので、事前に詳しくなれてよかった。 20代男性
何工程もかけて作る職人の思いというものが
よく伝わる良い映画だったと思います。 20代男性
とても興味深い内容で良い学びになりました。 20代男性
身近にある染物が作成される過程には
農耕の知恵や工夫が詰められており、
農家、染物職人、織物職人、
様々な人の苦労や努力が知れて勉強になった。 20代男性
先人達の知恵や工夫を沢山知ることができて良かった。 20代男性
藍や芭蕉布について今まで知らなかったので、とても興味深かったです。
もしアンコール上映があればまた観たいと思いました。 20代女性
芭蕉布が出来るまでの工程の多さ、複雑さに驚きました。
こういうものにお金を出したいと思いました。
芭蕉布を購入できる機会があれば、是非購入させて頂きます。
戦争中での辛い記憶も乗り越え、喜如嘉の芭蕉布を守ってくださった
平良さんと喜如嘉の女性方のおかげで、無形文化財にも選ばれ、
彼女たちにとっては日常の一部かもしれませんが
沖縄に大きな貢献をされており、素晴らしいと思うと共に、
もっと知られてほしいと思いました。
このような機会がなければ知ることができなかったので、
もっと大衆的に知ってもらえるようなきっかけが必要だと思いました。
この度は素敵な上映会をありがとうございました。 20代女性
武州藍と芭蕉布の2本立てで観ましたが、
日本、沖縄の農耕文化に根差した手仕事に感動します。
植物の栽培の過程から、染め織物につくり上げていくまでの
全体をつかむのにとてもいい教材でもあると思います。
定期的に見直したい映像作品と感じます。 30代男性
藍と芭蕉布あわせて観ることができてよかったです。
とても良い企画でした。
芭蕉布展の案内もありがとうございました。 30代女性
芭蕉布を作るためにあれだけの手順と
手間があったことにおどろきました。
沖縄の伝統として残してくれたことに感謝します。 30代女性
藍はどの地域でも‶生き物‶として扱っていて興味深かったです。
また、芭蕉布(布)になるまでの工程が多く、
手間が掛かっているからこそ
触れた時にあたたかみを感じるのだと思いました。 30代女性
藍染も芭蕉布も存在は知っていたが
その製造過程は知らなかったので、今回映像で見ることで
複雑かつ繊細な工程を知ることができました。
いずれも手間暇かかった細かい手作業で、
その技術を絶やさぬよう取り組まれた方々に敬意を抱きます。
変わっていくもの、変わらないもの、人の価値感もそれぞれですが、
伝統というものは絶えず残って欲しいと思いました。 30代女性
喜如嘉の女性の美しさを感じました。
暮らしのなかに仕事があって、
自然のなかで人が生きているという感じがしました。
誰と競うでもなく、自らの手で、そして
地域社会の和のなかで生きる幸せを、
現代や将来の社会でも引き継いでいけたらと思います。 30代男性
貴重な映像が観れて、とても嬉しいです。
県外の工芸になかなか触れる機会がなかったので
埼玉の藍について学べて良かったです。
芭蕉は、昔と今の様子を照らし合わせて見ました。
また、改めて、機会があれば観たいです。
何度観ても学べる映画でした。
ありがとうございました! 30代女性
内容もとても勉強になりました。
スタッフの方も丁寧に案内して下さり、
チラシも集落内いたるところで拝見して良かったです。
次回の上映をとても楽しみにしています。
できれば、北部での上映会も企画して下さることを望みます。 40代女性
「武州藍」の職人さん方の手仕事にほれぼれしました。
工程ごとのこだわり、
藍を生き物として大切に向き合う姿に感動しました。
喜如嘉の女性たちのきずな、
村で大切にされている共同作業の様子がすばらしかった。
人の想いやくらしが織りこまれ編まれた布だと思いました。
平良敏子さんのお若い頃の姿を拝見できるだけで胸がいっぱいになりました。 40代女性
素晴らしい上映会でした。
古い撮影でも沖縄の伝統工芸や
それに関するテーマの映画を上映し続けて下さい。 40代男性
芭蕉布がたくさんの人の手によってつくられ、
またたくさんの人を支える存在だったのかなと思い、
その美しさの理由のひとつを見た気がしました。
どちらも貴重な資料映像で、見られてありがたいです。 40代女性
貴重な映像を見せていただき、大変勉強になりました。
その時代の風景や服装などとてもおもしろかったです。 40代女性
藍、芭蕉布と作り手の「想い」を学ばせていただきました。
しっかり心に刻みたいと思います。
貴重な映像をありがとうございました。 40代男性
すばらしく良い時間でした。
今後も楽しみにしています。続けてがんばって下さい。
他の沖縄のディープをクローズアップ楽しみにしています。 40代男性
とても良かったです。
ありがとうございました。 40代男性
今日、はじめて参加、とても良かったです。
特別イベントの上映会にも感動しました。
「芭蕉布」が生きもののよううに見えてきました。
とても好きになりました。
芭蕉布がもっと身近なものになることを願っています。
ありがとう、又、上映会に参加したいです。
スタッフさんおつかれさまです。 40代女性
どちらの映像も当時のありのままの様子や風景
(武州藍のほうでは子供がちゃんちゃんこを着ていたり、
芭蕉布のほうでは昔の那覇バスターミナルが写っていたり)が
記録されていて、とてもなつかしくノルタルジーな気持ちを味わいました。
前回に引き続き貴重な映像をこの場にいる方々と同時に共有することができ
嬉しく思うと同時に感謝の気持ちでいっぱいです。
芭蕉布につきましては、平良敏子先生のありし日の姿を拝見することができ
リアルタイムでお会いすることができなかった私には
ありがたい機会となりました。今回もありがとうございました。 40代女性
藍も芭蕉布も手間が掛かるものとは思っていましたが
ここまで大変な作業とは知りませんでした。
これからも日本の伝統、沖縄の伝統として
守っていって頂きたいと思います。 50代女性
今年、大宜味村の喜如嘉芭蕉布会館へお邪魔しましたが
今回の映画ほど詳しく理解することができていなかったなと痛感。
当映画にてより理解が増しました。
もっと多くの上映機会があるといいと思います。 50代女性
平良敏子さん、すばらしい人ですね。
芭蕉布展からの流れで鑑賞しましたが、
とても感銘を受けました。
お手配してくれた沖縄の友人に感謝です。 50代女性
武州藍
藍染めの工程、文化を知る事ができて、勉強になりました。
「小禄クンジーも同様な文化だったのかな⁈」と、
小禄出身なので想いをはせました。
とても興味深い内容でした。
芭蕉布を織る女たち-連帯の手わざ-
芭蕉布展(沖縄県立博物館美術館)
風にゆられて芭蕉布ワンピース展(南風原町立南風原文化センター)
喜如嘉の芭蕉布展(沖縄芸大)
を楽しんだ後なので「本当に丁寧な手仕事で素晴らしい文化だなぁ、」と
改めて感じました。 50代女性
すばらしかった。平良敏子さんはすごい。 50代女性
芭蕉布のできるまでを部分では見たことがありますが、
ここまで詳しいのは初めてみました。
わかりやすくてよかったです。平良さん、お若いですね。
前に倉敷に旅行にいったとき、大原美術館(?)で
経緯を知り、感動しました。 50代女性
この様な複雑な技が
どうして開発されたのか、
見ていてとても不思議だった。 50代男性
鑑賞できてよかったです。
ありがとうございました。 50代女性
日本、沖縄の素晴らしい手仕事、
豊かな暮らしを観ることができてとても良かった。
日本人であることをほこりに思えた。
伝統的なものをもっと生活に取り入れたい。 50代女性
映像と解説で武州藍と喜如嘉の芭蕉布について
よく知ることがでいました。
すばらしい映画の上映会を催して下さって
ありがとうございました。 50代女性
大変感動しました。
沖芸大の方でも芭蕉布展をやっていて、
たまたまこちらでは映画の上映もあるという事で
参加させて頂きました。
普段、米国に住んでいるという事もあり、
中々、沖縄の文化にふれる機会は少ないですが
(NYCではJapanSocieyで組踊などは見た事がありますが)
ぜひ、この映画、そして展示会をNYCの方、アメリカの方でも
やって頂いて、沖縄のすばらしいテキスタイル文化を知ってもらいたいですね。
今回はこういう機会を頂けて感謝しております。 50代女性
県内に産まれ育っていてもなかなか沖縄(琉球)の文化財について
学ぶ機会がなく細かな事まで学ぶ事が出来る良い時間を頂けました。
芭蕉布は知っていましたが、大宜味村喜如嘉にいらっしゃる女性の方の力で
現在まで受け継がれている事がすごくすばらしくこれから先も
沖縄の貴重な文化財として大切に守られて欲しいと思いました。 50代女性
村のどこそこでいつも芭蕉布の糸を積む女性たちが
いた時代の映像を見ることができました。
現代の風景とは違いますが、
たしかに今につながっているんだと思いました。
ありがとうございました。 50代女性
入館が遅くなってしまい、終わり15分前の鑑賞になりました。
でも、芭蕉布を織るのに、また織った後の作業の多さに
力仕事とこまやかさも必要だということを知ることができ
こんどから芭蕉布を見る時その作業を思いうかべたいと思いました。 50代女性
私の母も与那国織をしていて、
子や孫のために反物を織り、プレゼントしてくれた。
でも、映画で紹介されていたような工程をへて
織物が完成することを知らずに私は60歳を
目前に控えている。こんな自分を恥と思う。
織物をやっている人達の苦労を知らずにいたことが恥。
そして、平良さんの芭蕉布を守った心に感動した。 50代女性
なつかしい沖縄の風景とともに
大宜味、喜如嘉で、芭蕉布を再生、後世へとつないで
下さった平良敏子さんの姿に感動しました。
強い思いでつづけてこられたのだとしみじみ感じました。
芭蕉布は、ひとつひとつ丁寧な工程のたまものだと思います。
沖縄のほこるべき宝です。
今年、たまたま奥州浴衣を購入しました。
藍染の長板の工程など知ることができました。
浴衣を大切にしたいと思います。 50代女性
とても貴重な映像をありがとうございました。
芭蕉布が糸~布になるまで、大変な手間ひま、ご苦労がわかり
そんな芭蕉にとても興味がもてました。 50代女性
喜如嘉の村に生活の一部として根づいている芭蕉布織り。
村の女性達が協力し合い、伝統を守り、布を織っている姿に感動した。
これからもぜひ守り引き継がれていってほしい。
2つの映画とも自然の植物を相手に、染め、糸づくり、布を織ることを
記録していて、こういう記録を残すことが、これからの世代へとバトンが
引き継がれていくのでとても大切だと思った。
このような機会をこれからも設けてほしい。 50代女性
芭蕉布がこんなに手間ひまのかかるものだとは知らずにいました。
たくさんの沖縄の人に観てほしい作品です。
平良敏子先生のおだやかな表情ときびきび働くお姿が
とても素晴らしく感動しました。
すばらしい作品だと思います。ありがとうございました。 50代女性
藍、芭蕉布ともに良かったです。
藍は、種まきから染めまで見る事ができてよかったです。
芭蕉布は糸づくりから仕上げ、普段の生活の様子も見る事が
できてわかりやすかったです。平良先生、美恵子さん、お若い!
年をとっても、もの作りをする方々はお元気で輝いてすてきです。
先週の水害が心配ですが、どうかこの光景がずっと続くことを願います。 50代女性
武州が藍の産地ということは、大河ドラマを観て知ってはいましたが
実際どのように作られるのかは知りませんでした。
芭蕉もそうですが、まず植物を育てることからはじまって、
製品ができあがるまでにこんなに複雑な工程があり、たくさんの人々の手で
作られているのだということが、すごいと思いました。
今も、その技術は受け継がれているのでしょうか?
芭蕉布は高価でとても手に入れることはできませんが、
藍染の服は一着持っているので、
着るときには今回の映画を思いながら着ようと思いました。 50代女性
どちらの映像も、その土地に根付いた人々の営みとともに
栄えていった手仕事である事、そしてひとつひとつの作業の工程にかかる
手間ひま、難儀が、とても美しくどの作業も省略できない事が
私にはとても素晴らしく映りました。
武州藍も芭蕉布もどちらも(藍を育てていく、糸芭蕉を育てていくなど)
長い時間をかけて作られている事を改めて知る事ができて大変貴重な時間でした。
織りも染めもやはり祈りと希望がいつもそこに存在し、
作り手の方々の生きる喜びが共にあると強く感じました。
ありがとうございました。 50代女性
武州藍
藍染めの奥深さ、工程の細やかな作業を、初めて知ることができました。
泡のぶくぶくした状態になるまでには、数々の工程があるのですね。
職人さんの藍色に染まった手が格好よかったです。
芭蕉布を織る女たち
平良敏子さんの若かりし頃の映像を見るにたくましさをひしひしと感じました。
長く重い芭蕉布を、たらいでじゃぶじゃぶ洗う姿に
足腰の強さを感じずにはいられませんでした。
あの小さな体からあふれ出るパワーが
しっかり引き継がれていくことを心から願っています。
このようなすばらしいドキュメンタリー2本を
無料で鑑賞させていただきありがとうございました。 50代女性
とても勉強になりました。
ありがとうございました。 60代女性
芭蕉布は戦前、県内各地に在り、多くの担い手がいた。
戦後、喜如嘉だけがその伝統を守り存続したのは
平良敏子さんの力によるものだろう。
その想いはどこから来るものだろう。
喜如嘉の風土の力か。 60代男性
神奈川から来沖している友人を案内して参加。
芭蕉布展も観て、とても感銘したようだ。お連れできてよかった。
私も何度も観せていただいているが、次回の「むんじゅう笠」は
DVDを持っているので今回はパスします。 60代女性
衣料品の大量廃棄などが問題になっている
今だからこそ、ていねいな物づくりは
重要で必要になのだと感じました。 60代女性
もっと多くの方に観て頂きたいと思える素敵な映画だと思います。
今回、二度目でしたが、次の機会があれば又観に来ます。
ありがとうございました。 60代女性
藍について昔からの作り方、染め方、大変参考になった。
芭蕉布 制作工程はもちろん、
沖縄の昔ながらの民家や生活感がとても見れた事が良かった。 60代女性
大雨の中、まよいながら来たのだが
とても心おだやかで美しい作品でした。
ありがとうございます。
喜如嘉へ行ってその風を感じたい。
藍染は男の仕事なんだと思った。 60代女性
平良敏子が亡くなったのは残念です。
後継者が多数いることを願います。
武州藍を初めて知りましたが、とても素晴らしい芸術品ですね。
職人の知恵と技にただただ感心しました。 60代男性
「武州藍」の途中からしか鑑賞できなかったので
もう一度別の機会に上映してほしい。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
毎回見たいと思いました。 60代女性
素晴らしい映画上映をありがとうございました。
平良さんは御自分の使命をまっとうされたのだなぁと感じました。
喜如嘉の芭蕉布が一人の人の想いから
亡ばずに本当に良かったと思いました。
大原様に感謝です。
喜如嘉の芭蕉布を守り、生かしてくださったことに感謝です。
又、アンコール上映されることを願います。 60代女性
芭蕉布を織るのに手数がかかるというのは聞いていたが
これほどだと初めて知る。戦争やいろいろなことで
ほとんどすたれてしまったものが、喜如嘉でまた復興したというのは
ほんとうに奇跡で岡山の紡績工場の社長さんや柳宗悦さんには感謝である。
人間国宝にまでなった平良敏子さんの人となりと今に受け継がれるいしずえと
なった歩みがこの映画を見て知れてほんとうに有意義な時間でした。 60代女性
芭蕉布を守って育てた人々(女性)の生き様に大変感謝しました。 60代男性
昔の人のすばらしさにほんとうにカンプクの一言。
これからもいろいろなものをみてみたいです。 60代女性
平良さんには、ただただ頭が下がる思いです。 60代男性
芭蕉布作り、いろいろ手間などかけていて、すばらしい。
次世代の人々につないでほしい。又、県はもちろん
国などで代々守って欲しい。
武州藍、たくさんの人々の過程、手をかりて、すばらしい。
藍染めができて、すばらしい。これも日本の藍として守ってほしい。
ありがとうございます。 60代女性
喜如嘉にある芭蕉と木灰とシャリンバイから糸が生まれ
紡がれ織られ布になる。生産性向上や付加価値や品質管理はここにない。
あるのは、生活と連帯と感謝。
現代の日本がどこかに置いてきたものがここには全てある。 70代男性
見たい映画たくさんあります。 70代女性
良かったです。 70代男性
時間と労力をかけて紡がれる織の世界。
いつまでも継がれる事を祈るばかり。
平良敏子さんの情熱と村への思いを伝える上映でした。 70代女性
良かったです。
とくに「芭蕉布を織る女たち」は
観ているうちに涙が出てきました。 70代女性
宴会の余興等で着るぐらいしか機会のない芭蕉布でしたが
こんなにも手間ひまかけて布に織りあがるのだと初めて知りました。
ものすごく貴重な布なのですね。
芭蕉の木から布に織りあがるまでの過程がよくわかり感動しました。 70代男性
多くの方の協力で素晴らしい作品が生れてるのがわかりました。 70代女性
たいへん良い映画をありがとうございます。 70代男性
細かい作業や作品が一人一人の思いによって
できあがることを知ってよかたです。 70代女性
手仕事のすばらしさ、作品をみることができてよかったです。
ありがとうございました。 70代女性
若者へ
伝統の芭蕉布をつづける努力、
芭蕉布展をつづけてほしい。 70代男性
芭蕉布、藍染め、どちらもすばらしいですね!
生活の中に取り入れていきたいと思いました。
手間ひまのすごくかかった仕上げのもと
ステキな作品となるのですね。 70代女性
芭蕉布の工程については本も読んでおりましたので
ある程度は知っている心算でしたが、複雑で、気の遠くなるような工程は
予想を遥かに超えていました。このことは、武州藍についても同様です。
ただ、年月日も知りたかったです。
平良敏子さんの若いお姿は何歳位だったのでしょうか。 70代女性
[質問の回答]平良敏子さんの年齢について
平良敏子さんは1921年生まれのようです。『芭蕉布を織る女たち』の
製作年が1981年ですので、59才か60才だと思います。
芭蕉も藍も沢山の工程を経るのですね。
それを苦労っぽくなく、こなして楽しそうにやっていることがすごい。 70代女性
良かったです。
芭蕉布の値段が高いのがわかります。 70代女性
大変すばらしい映画でした。感動です。
喜如嘉の方々、芭蕉布作りを映像でみることが出来
また、映画を作ってくれたことに大変すばらしく、すばらしいことです。
平良敏子さん、芭蕉布をしている方々、とにかくすごいと思います。
上映会に来ることが出来、勉強になりました。ありがとうございます。 70代女性
自然と共に生きる、先人の知恵、
相手とじっくり付き合いながら、ひとつの物を作りあげていくことの喜び
今の時代に大切な事を教えてくれる作品でした。
感動しました。ありがとうございます。 70代女性
「芭蕉布を織る女たち」は以前にも見ましたが
「武州藍」は初めてで、藍の種をまくところから
藍染めができるまで詳しく工程が分かって良かった。
藍は沖縄では日かげか半日かげで栽培されていると聞いているが
日なたで育てているので驚いた。
沖縄の藍と違うのだろうか。 70代女性
[質問の回答]リュウキュウアイは日かげを好みますね。
藍の種類によって違うようです。武州藍のタデアイは
日光を好み日当たりのよい場所で育ててましたね。
武州藍、芭蕉布も、ひとつひとつの工程が
きちんとていねいに行われて布が完成していることがすばらしく、
生活の場と密着していることがよく映像化されていると感じました。
特に喜如嘉の女性達の生き生きとした姿が印象に残った。
今も喜如嘉にひきつがれていると感じる。 70代女性
とても大変なお仕事だと、ご苦労をおもいました。
現代においてずっと続けていく事は困難な作業だと思います。
記録を残すことがどんなに重要なことか、特に映像の力が大きいと思います。 70代女性
11/2に芸大で平良美恵子先生のお話を聞き
芭蕉布の事を初めて知り(県外人なので)映画も初めて見たのですが
びっくりする事ばかりでした。博物館のチラシで平良先生のお話しや
映画会がある事を知り、11/16、11/17と2日は博物館に来ました。
本当に皆さん苦労して文化をつないでこられたのだと頭が下がります。 70代女性
いづれにも共通する事だが
手間ひまが掛かり頭がさがる。
着物が好きで購入もするが、
琉球の伝統工芸は高額で手が出ない。
工程を知ってしまうと納得なのだが… 70代女性
感動致しました。 70代女性
すばらしい映画でした。 70代男性
今回の映画会は大変良かった。
芭蕉布の出来上がり、歴史の重みを感じました。
これからも小さな映画会がますます大きな映画会になりますように。
ありがとうございました。 80代男性
毎回、新たな感動を得ます。
手作業、伝統の奥深さを有難く見せてもらっています。
ありがとうございます。 80代女性
大変すばらしい。
沖縄の世界にほこる、すばらしいと思います。
「バショウ」の衣は、良い物です。
無地でバショウを作り、後であやを入れたらどうかと思いました。 80代男性
芭蕉布が布になるまですごい工程ですね。
昔の年配の人は、着物や洋服で着けていたのを思い出します。
祖母もバサーを洗たくする時は、クニブ(みかん)で洗ってました。
みかんで洗うとそれはきれいに鮮明に汚れも落ちていました。 80代女性
1.2編共大変良かった。
1本づつ上映した方が良かったのではないか。
2.取材時期が分からなかったが、最後に入れるべきと考える。
3.「芭蕉布を織る女たち」では、一着尺にどの程度の芭蕉布が使われ
どの位の時間がかかり、最終的にいくら位で取引されるのかが知りたかった。 80代男性
工芸の素晴らしさを再確認しました。
大変勉強になりました。 80代女性
・知識を広めるためとてもよかったと思います。
・手仕事のきびしさがわかった。
・奥深いきびしさがあることがわかった。 80代女性
こんなに素晴らしい映画を見ることが出来たのは
生涯忘れることが出来ない程感激した。反省するのみ。
平良先生を常に念頭に置き、残された時間を大切に生きたいと思いました。
先生を中心に織られた方達皆さんの
生き(活き)生きした姿をみることができたのも良かったです。 80代女性
芭蕉布工房で若い頃の敏子、美恵子さんのなつかしいお姿。
伝統を守ることのむずかしさ、受け継がれるのも御苦労様です。 80代男性
気の遠くなる程の過程を経て、出来上がる芭蕉布。
根気と愛で出来る布。永らく継承できる事を祈る。 90代女性
〈11月会を振り返って〉
「海燕社の小さな映画会2024」11月会、
ご鑑賞の143名のお客様、ありがとうございました。
「ポーラ伝統文化振興財団」様、「桜映画社」様、ありがとうございました。
「民族文化映像研究所」様、ありがとうございました。
11月会は沖縄県立博物館美術館『芭蕉布展』とのコラボ上映会が実現しました。
おかげさまでお客様に映画を無料でご鑑賞頂けることができました。
「沖縄県立博物館美術館」様、ありがとうございました。
後援の「沖縄県」「那覇市」様、ありがとうございました。
宣伝にご協力下さいましたマスコミのみなさま、ありがとうございました。
SNSや口コミで宣伝下さいましたみなさま、ありがとうございました。
みなさまに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
海燕社の小さな映画会は海燕社が「観たい」「観て欲しい」映画を
一緒に観ませんか、というスタンスで開催している映画会です。
劇場ではなかなか上映されない映像作品や旧作映画を上映しています。
映画の多様性、特にドキュメンタリーの幅広さを知ってもらいたいという気持ちもあります。
2024年の映画会は10年目を記念してご鑑賞者にオリジナル「栞」をプレゼントしています。
4月会は「獅子」5月会は「木」…上映作品に合わせてテーマを決めてデザインしています。
記念品を「栞」にしたのは、私が映画を観る前や観た後に原作本や関連する本を読みたくなるからです。
映画会の思い出とともに読書の時に「栞」を愛用して頂けたらうれしいです。
「海燕社の小さな映画会2024」の11月会は、
『武州藍』『芭蕉布を織る女たち-連帯の手わざ-』(以下『芭蕉布の織る女たち』)の二作品を上映しました。
沖縄初上映作品『武州藍』とアンコール3回目上映作品『芭蕉布を織る女たち』
この二本立を企画した理由を主催者挨拶で話しました。
きっかけは『芭蕉布を織る女たち』です。この作品で私が印象に残った言葉が「藍の花」です。
藍を、花のように見る、人のように思いやる、そこに惹かれました。
藍と藍をつなぐ上映会をしたいと『武州藍』と『芭蕉布を織る女たち』の二本立を決めました。
映像作品は完成後が大事だと思っています。
製作者としては観てもらうこと、観客としては観ること、
その二つを映画に贈りたいです。
「海燕社の小さな映画会」はその一役になって欲しいと願っています。
アンケートの提出して下さった139名様に感謝申し上げます。
アンケートのご協力ありがとうございました。
感想を書いて下さったのは120名様。感想ブログ掲載不可は15名様。
105名のお客様の感想を上記で紹介させて頂きました。
ブログでのお客様全員の感想を紹介する活動を続けています。
海燕社のスタッフだけで読むには惜しい内容の感想ばかりだからです。
映画会に来て下さった皆様と感想を共有したい、
映画製作者のみなさまにお客様の感想を伝えたい、
映画会に来れなかったみなさまに作品について伝えたい、
という思いで感想をブログで紹介しています。
これからも続けます。ご協力をよろしくお願いします。
城間あさみ
Posted by カイエンシャ at
05:41
│海燕社の小さな映画会
2024年11月15日
「海燕社の小さな映画会2024 10月会」『こどもの時間』
海燕社の小さな映画会2024 10月会
【2024.10.6(日)/沖縄県立博物館・美術館3階講堂
13:15受付開場/14:05上映開始/15:30終了】
鑑賞料:1200円(予約一般)/1500円(当日一般)
※高校生以下無料券(予約先着10名様まで)
〈上映作品〉
『こどもの時間 』
(2001年/野中真理子監督/80分)
〈入場まで〉
1.受付:①予約の方-鑑賞券(1,200円)/当日の方-当日券(1,500円)
②資料配布
2.手指アルコール消毒(各自:劇場入口設置)
3.入場着席:自由席
※配布資料
10月会チラシ1枚、11月会チラシ1枚
アンケート用紙、案内希望カード、11月会12月会予約カード、
アンケート記入用下敷き、クリアファイル、クリップ鉛筆
※ご来場者プレゼント
10年目記念オリジナル栞1枚
(10月会デザインテーマ「こどもの時間 無限∞」)
<プログラム>
※会場~開会前
・上映前「映画会とお願い」映像上映
・お願いとお知らせ(司会アナウンス)
・11月会『芭蕉布を織る女たち』冒頭映像上映
・12月会『むんじゅる笠』予告編上映
1.開会(司会ボラティアスタッフ)
2.主催挨拶(城間あさみ)
3.『こどもの時間』
(2010年/野中真理子監督/80分)
5.閉会(アンケート記入)
<スタッフ> 4人(海燕社2人、同人1人、ボランティアスタッフ2人)
準備・片付け:全スタッフ
全体:(城間あさみ)
受付:(澤岻健/ボランティアスタッフ)
上映:(海燕社同人)
司会:(ボランティアスタッフ)
〈後援〉沖縄県/那覇市
【お客様の感想(アンケートより)】
小学3年生の息子と一緒に来ました。
終始「なにやってるー?」と突っ込んでいる息子と
笑いながらみていました。
洋服がよごれるから、ケガしたらあぶないから!と
親の都合でい色々なコトを止めたりしてきた
自分の子育てをふりかえりなが反省してばかりいます。
子どもたちと全力でぶつかる大人の姿、
「食」に対する本来の欲、
いろいろな場面で感動しました。
ありがとうございました。 女性
ようち園の子たちの時間がよく分かった。 9才以下 男性
本来の子どもの姿が、
のびのびと自分のやりたいこを見つけ出し
挑戦する姿にほっこりしました。 20代女性
こどもたちが自由にやちたいことをみつけて
遊んでいる姿が印象的でした。とても楽しそうでした。 20代女性
こどもらしい自由で主体的で自然の中で
考えながらすごしていて
ステキな幼少期をすごしているなと思いました。
私自身、「ダメ」「やめて」「いけないよ」を日常で
子どもに対して言い過ぎているなと考えさせられました。
自分自身の子どもに対する考えを
見つめなおす時間となりました。 20代女性
多分、今だったら「あふないから、やめて!」で
止められていそうなことを、自由にやらせて、
子どもたちも、ころんでも、失敗しても、
泣きながら、成長していく。
この時代に、生まれてみたかったなと、
何もないくらしがうらやましくなりました。
竹馬とかコールマーとか、コマとか、
うっすらと記憶の中にあった遊びを思い出しました。
忘れてしまってた自分は良い意味でも悪い意味でも
オトナになってしまったんだなと、思いました。 20代女性
0歳と2歳の子がいるが、
汚さないよう、変な物に触らないよう育てているが、
今日見た保育園のように
なんでもさせてみるのも良いなと思った。
この子達がどんな大人になったのかも気になる。 30代男性
子供達の感受性の豊かさに心が揺さぶられました。
釜戸の湯気、水道の水の流れ、動物のわずかなしぐさ、
ご飯の食べ方など、普段の何気ない日常の一部に
一喜一憂し、受け止める姿に面白みを感じます。
このいなほ保育園の環境はすばらしいと思います。 30代男性
現在、2才と0才の子どもを子育て中ですが、
この映画を見て、
もっと子どもたちを自由にさせた方がいいと思いました。
『こどもの時間』を見れて良かったです!
親として、とてもほっとして、気が楽になりました。
この保育園のような育て方を目指したいと思います! 30代女性
会場もこじんまりとして、映画をゆっくり楽しめました。
とても興味深い上映をしているようなので今後もチェックしたいです。 40代女性
十何年ぶりにかで鑑賞しました。
子どもはすっかり大きくなってしまいましたが、
私が大事にしたかったことは
少しは伝わったのかな?と思いました。
全然関係ないのですが、
下敷きを拝見していて、林竹二先生は私の大学の学長だった方で、
世代は違うのでお会いしたことはありませんが、
著作は読んでとても感銘を受けたので
先生の映画があるということでとても驚きました。
また機会があれば足を運んでみたいです。
ありがとうございました。 40代女性
自分が子どもの頃の時代かなと思いなつかしく見てました。
何年頃の映像だったのか、どこのどういう保育園なのか
テロップだけでもいいので、説明があるともっといいと思いました。
今は、あぶないからさせないなど、
大人たちが子どもの世界に介入しすぎている気がします。
映像のように失敗や気づきを自らくり返し成長できる世の中であって欲しい。 40代女性
保育園で勤務しています。
こんなこどもの時間があふれた毎日、
うらやましいなぁーとずっと思いながらの80分でした。
全てを否定せず、あたたかいまなざしの中で育っていく
こどもたちの今後が楽しみですね。
現在のいなほ保育園を訪れてみたいです。
ありがとうございました! 40代女性
「だめよ」「あぶない」禁止のことばが聞こえない。
豊かな自然の中で、実際に子どもたちが経験して
生きる術を体得していく。
なんてうらやましい保育環境だろうか。
現代の子どもたちに、私たち大人はたくましい生き方を
伝えていけるだろうか、と考えてしまった。 50代女性
いなほ保育園の子どもたち・・・
子どもたちが「今」やりたい事をのびのびとさせていることが
その後の生きる力につながるのだろうな・・・と思いました。
今だと危ない!と先手で行動を止めてしまうかもしれませんが、
見守る勇気も必要だと気付かされました。小4の母より 50代女性
いちばん印象的だったのは、
何でも手づかみで食べていて
先生もそれを叱らないということです。
特に野菜をいやがらずにおいしそうに食べていたのが
とてもよかったです。好き嫌いのない子に育ったのではないでしょうか。
一方で、今なら「きたない」「手を洗ってきて」「危ない!」など、
ママたちの悲鳴も聞こえてきそうです。
親の理解も必要な難しい時代になってしまったなぁと
少しさびしい気持ちになりました。 50代女性
いなほ保育園のスタッフの方々がステキでした。
子ども達の社会性を育てていく、自主性を育てる、
とてもすばらしく心が温かくなる映画でした。
今の親ももっと過保護になりすぎないよう
このような映画を見てほしいです。 50代男性
遠い昔のとても頼もしい自分を思い出し、
映画のシーンの仲間と時間を共有し、
とても楽しい。力強い。
自分の子供時代を過ごせました。すばらしい映画でした。
共有した自分は、今の自分とかなり違う自分でした。
(映画のシーンに慣れるまで少し時間がかかったのが
興味深かったです) 50代女性
途中からの鑑賞でしたがとてもすてきな作品でした。
子どもたちが土、水、火、動物に素手素肌で触れてて
この子たちがどんな風に育っているのか気になりました。
こんな時間を提供できる保育園、
一緒に子どもたちと遊んでみたいと思いました。
沖縄にもあるかしら?
あ、でも、大人としては、ケガが心配で、
ハラハラドキドキでもありました。
すてきな映画をありがとうございます。 50代女性
西原街こばとゆがふ保育園のことを思い出しました。
本土のとある保育園の影響を受けて開設したと聞いてますが、
いはほ保育園のことかと思いました。
子どもがこども時間をすごせることも
主催者、保護者が、守っての活動だと思います。
こどもの自発性、自主性、独創性を育てている
すてきな保育だと思いました。 50代女性
人のたくましさに感動しました。
信じることって大事だと改めて思いました。 50代男性
冷房強すぎ。寒かった。 50代男性
保育士をしてます。
私の園ではありえないシーンばかりで
”大丈夫?”と思ったりしましたが
子ども達の映画が”心配ないよ”と言っていました。
冬の寒い中、はだしで園庭や畑で活動する子ども達、
外でお昼を鼻水しながら、けんかもしながら食べる子ども達、
ブロッコリー、トマト、スイカにかぶりつく子ども達、
ほんとに素晴らしい環境で、もっともっと観たく、映画がとても短く感じました。
こういう園で育った子は、きっと心身共にたくましい大人になっていくと思います。
自分の保育、明日から少し変わるかも… 50代女性
観る前からとても楽しみにしていた映画です。
感動しました。
好奇心旺盛な一人一人の豊かな表情、
制限のない関わりの中で、子供達の無限の可能性、
人としての優しさ、生命力、たくましさ、
本来の子供の姿がありました。
とても胸がいっぱいです。
ありがとうございました。
考えさせられる映画でした。 60代女性
人が人生を始めるとき、そこに土があり、
火があり、尊き水があり、人としての群れがある。
そうした原始の頃からの、人のあり方を、
子ども達が供にすごす中で
身をもって味わっていく時間が尊かった。
私達の社会が見失い、いきづまりを感じている今、
生きるはじまりを思った。 60代男性
先生のよけいな声かけが一斉聞こえず、
子ども達の本来の姿が生き生きと描かれていら。
自然に恵まれた環境のすばらしさ。
周りの大人が、子ども達の力を信頼して、子どもに任せていることで、
子ども達が自分で自分を育てている姿に感動しました。
ありがとうございました。 60代女性
すばらしい保育を見せていただいた。
・児童は人として尊ばれる。
・児童は良い環境の中で育てられる。
・児童は社会の一員として重んぜられる。
それらが、すべて整った保育環境で感動しました。 60代女性
理想的な保育園ですね。
都市部では無理な環境です。
子供達のノビノビした行動にうれしくなりました。 60代男性
広い敷地があるとのびのびとした保育ができますね。
沖縄の南部でもやや似かよった(さくらんぼ保育)を行っている
保育園があり、私の孫もそこで育ててもらいました。
今は小5と中1になっていますが、ちゃんと自分の思いを主張できます。
保育園の頃より保育士とのいさかいもあったようですが心を育ててもらい感謝せいています。
幼児期にのびのびとやりたい事をさせる保育は、
その後、子どもの心の成長に良いえいきょうを与えるものだと思います。
本日、すばらしい映写に感謝致します。 60代女性
子供達の目の輝きが、とても印象的でした。
子供の時間とは大切な何かを沢山思い出しました。
ありがとうございました。 60代女性
久々に「ハンラヤー」を観た。
棒を持っている子供も今は消えている。
すずめもギンヤンマも今は見ない。 60代男性
久しぶりに天しんらんまんの子供達がまれてよかった。
こういう教育もいいなと思いました。 70代女性
こどもの時間、私にも遠い昔に確かにありました。
生きる力を持って生まれてきたことを忘れていました。
この先いつまでか解りませんが
毎日を楽しい時間のなかでやりたいことも
がんばろうと強く思いました。
今日はありがとうございました。 70代女性
65年前を思い出しとてもよかったです。 70代男性
子供達の純真でたくましく成長してゆく姿に感動しました。
有難うございました。 70代男性
今回二度目の上映を見ました。
ほのぼのです。子供は野生児のように
育てるものなのかと感じました。
大人は、子供の頃を忘れてしまってますね。
笑顔が見られるのはいいですね。 70代女性
「こどもの時間」最高でした。
こどもの表情のゆたかさ、愛らしさ、
鼻たれはこどもの個性ですね。
本当に忘れていたお目にかかれない鼻たれ、
そして、手、指、足もポチャっとムチムチ健康そのものですね。
幸せな子どもたち、そして最高のいなほ保育園の子ども達、職員の方々、
幸せな時間を味わいました。ありがとうございました。 70代女性
昔に(子供が小さい頃には)戻れない。
子育ては後悔することばかり。
子ども達の顔を見ると気持ちがなごむと共に
自分の子育てを後悔することばかり。 80代女性
よかったです。 80代女性
皆んな子供から成長していく。
良かったです。
皆んなのびのびと育って欲しい。 80代男性
今の時代では考えられない幼児教育です。
感動しました。 90代女性
〈10月会を振り返って〉
「海燕社の小さな映画会2024」10月会。
ご鑑賞の58名のお客様、ありがとうございました。
『こどもの時間』の上映を快く了承して下さいました「野中真理子事務所」様、
野中真理子監督、ありがとうございました。
会場「沖縄県立博物館美術館」様、ありがとうございました。
後援の「沖縄県」「那覇市」様、ありがとうございました。
宣伝にご協力下さいましたマスコミのみなさま、ありがとうございました。
SNSや口コミで宣伝下さいましたみなさま、ありがとうございました。
みなさまに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
海燕社の小さな映画会は海燕社が「観たい」「観て欲しい」映画を
一緒に観ませんか、というゆるっとした気持ちで開催している映画会です。
劇場ではなかなか上映されない映像作品や旧作映画を上映しています。
映画の多様性、特にドキュメンタリーの幅広さを知ってもらいたいという気持ちもあります。
2024年の映画会は10年目を記念してご鑑賞者にオリジナル「栞」をプレゼントしています。
4月会は「獅子」5月会は「木」…上映作品に合わせてテーマを決めてデザインしています。
記念品を「栞」にしたのは、私が映画を観る前や観た後に原作本や関連する本を読みたくなるからです。
映画会の思い出とともに読書の時に「栞」を愛用して頂けたらうれしいです。
「海燕社の小さな映画会2024」の10月会は、
『こどもの時間』(野中真理子監督)を上映しました。
子どものわたし、大人のわたし、ひとり二人として観ました。
子どものわたしにはあこがれのこどもの時間でした。
いいなぁ、いいなぁ、と心で何度呟いた事でしょうか。
やってなかったことばかり、やってみたいことばかり。
冬のあの大きな焚火に心で手をあてて温まっていました。
大人のわたしは、今の子ども達を想うと考えこみました。
沖縄の子ども達、日本中の子ども達に、
このようなこどもの時間を持たせてあげたいけれど、
私達大人は子どもに贈ることができるのか、と。
自然らしい自然があること、
親と子と先生が信じあうこと、
この二つが揃えば、この映画のような「こどもの時間」は叶えられるはずです。
大人が問われていると思います。
映画『こどもの時間』は、
忘れていた「こどもの時間」をその大切さを気づかせてくれました。
過ぎてゆく日常の「おとなの時間」を立ち止まって想うことができました。
「わたしの時間」を大切にしたいと思いました。ありがとうございました。
映像作品は完成後が大事だと思っています。
製作者としては観てもらうこと、観客としては観ること、
その二つを映画に贈りたいです。
「海燕社の小さな映画会」はその一役になって欲しいと願っています。
アンケートの提出して下さった51名様に感謝申し上げます。
アンケートのご協力ありがとうございました。
感想を書いて下さったのは46名様。感想ブログ掲載不可は3名様。
43名のお客様の感想を上記で紹介させて頂きました。
ブログでのお客様全員の感想を紹介する活動を続けています。
海燕社のスタッフだけで読むには惜しい内容の感想ばかりだからです。
映画会に来て下さった皆様と感想を共有したい、
映画製作者のみなさまにお客様の感想を伝えたい、
映画会に来れなかったみなさまに作品について伝えたい、
という思いで感想をブログで紹介しています。
これからも続けます。ご協力をよろしくお願いします。
城間あさみ
【2024.10.6(日)/沖縄県立博物館・美術館3階講堂
13:15受付開場/14:05上映開始/15:30終了】
鑑賞料:1200円(予約一般)/1500円(当日一般)
※高校生以下無料券(予約先着10名様まで)
〈上映作品〉
『こどもの時間 』
(2001年/野中真理子監督/80分)
〈入場まで〉
1.受付:①予約の方-鑑賞券(1,200円)/当日の方-当日券(1,500円)
②資料配布
2.手指アルコール消毒(各自:劇場入口設置)
3.入場着席:自由席
※配布資料
10月会チラシ1枚、11月会チラシ1枚
アンケート用紙、案内希望カード、11月会12月会予約カード、
アンケート記入用下敷き、クリアファイル、クリップ鉛筆
※ご来場者プレゼント
10年目記念オリジナル栞1枚
(10月会デザインテーマ「こどもの時間 無限∞」)
<プログラム>
※会場~開会前
・上映前「映画会とお願い」映像上映
・お願いとお知らせ(司会アナウンス)
・11月会『芭蕉布を織る女たち』冒頭映像上映
・12月会『むんじゅる笠』予告編上映
1.開会(司会ボラティアスタッフ)
2.主催挨拶(城間あさみ)
3.『こどもの時間』
(2010年/野中真理子監督/80分)
5.閉会(アンケート記入)
<スタッフ> 4人(海燕社2人、同人1人、ボランティアスタッフ2人)
準備・片付け:全スタッフ
全体:(城間あさみ)
受付:(澤岻健/ボランティアスタッフ)
上映:(海燕社同人)
司会:(ボランティアスタッフ)
〈後援〉沖縄県/那覇市
【お客様の感想(アンケートより)】
小学3年生の息子と一緒に来ました。
終始「なにやってるー?」と突っ込んでいる息子と
笑いながらみていました。
洋服がよごれるから、ケガしたらあぶないから!と
親の都合でい色々なコトを止めたりしてきた
自分の子育てをふりかえりなが反省してばかりいます。
子どもたちと全力でぶつかる大人の姿、
「食」に対する本来の欲、
いろいろな場面で感動しました。
ありがとうございました。 女性
ようち園の子たちの時間がよく分かった。 9才以下 男性
本来の子どもの姿が、
のびのびと自分のやりたいこを見つけ出し
挑戦する姿にほっこりしました。 20代女性
こどもたちが自由にやちたいことをみつけて
遊んでいる姿が印象的でした。とても楽しそうでした。 20代女性
こどもらしい自由で主体的で自然の中で
考えながらすごしていて
ステキな幼少期をすごしているなと思いました。
私自身、「ダメ」「やめて」「いけないよ」を日常で
子どもに対して言い過ぎているなと考えさせられました。
自分自身の子どもに対する考えを
見つめなおす時間となりました。 20代女性
多分、今だったら「あふないから、やめて!」で
止められていそうなことを、自由にやらせて、
子どもたちも、ころんでも、失敗しても、
泣きながら、成長していく。
この時代に、生まれてみたかったなと、
何もないくらしがうらやましくなりました。
竹馬とかコールマーとか、コマとか、
うっすらと記憶の中にあった遊びを思い出しました。
忘れてしまってた自分は良い意味でも悪い意味でも
オトナになってしまったんだなと、思いました。 20代女性
0歳と2歳の子がいるが、
汚さないよう、変な物に触らないよう育てているが、
今日見た保育園のように
なんでもさせてみるのも良いなと思った。
この子達がどんな大人になったのかも気になる。 30代男性
子供達の感受性の豊かさに心が揺さぶられました。
釜戸の湯気、水道の水の流れ、動物のわずかなしぐさ、
ご飯の食べ方など、普段の何気ない日常の一部に
一喜一憂し、受け止める姿に面白みを感じます。
このいなほ保育園の環境はすばらしいと思います。 30代男性
現在、2才と0才の子どもを子育て中ですが、
この映画を見て、
もっと子どもたちを自由にさせた方がいいと思いました。
『こどもの時間』を見れて良かったです!
親として、とてもほっとして、気が楽になりました。
この保育園のような育て方を目指したいと思います! 30代女性
会場もこじんまりとして、映画をゆっくり楽しめました。
とても興味深い上映をしているようなので今後もチェックしたいです。 40代女性
十何年ぶりにかで鑑賞しました。
子どもはすっかり大きくなってしまいましたが、
私が大事にしたかったことは
少しは伝わったのかな?と思いました。
全然関係ないのですが、
下敷きを拝見していて、林竹二先生は私の大学の学長だった方で、
世代は違うのでお会いしたことはありませんが、
著作は読んでとても感銘を受けたので
先生の映画があるということでとても驚きました。
また機会があれば足を運んでみたいです。
ありがとうございました。 40代女性
自分が子どもの頃の時代かなと思いなつかしく見てました。
何年頃の映像だったのか、どこのどういう保育園なのか
テロップだけでもいいので、説明があるともっといいと思いました。
今は、あぶないからさせないなど、
大人たちが子どもの世界に介入しすぎている気がします。
映像のように失敗や気づきを自らくり返し成長できる世の中であって欲しい。 40代女性
保育園で勤務しています。
こんなこどもの時間があふれた毎日、
うらやましいなぁーとずっと思いながらの80分でした。
全てを否定せず、あたたかいまなざしの中で育っていく
こどもたちの今後が楽しみですね。
現在のいなほ保育園を訪れてみたいです。
ありがとうございました! 40代女性
「だめよ」「あぶない」禁止のことばが聞こえない。
豊かな自然の中で、実際に子どもたちが経験して
生きる術を体得していく。
なんてうらやましい保育環境だろうか。
現代の子どもたちに、私たち大人はたくましい生き方を
伝えていけるだろうか、と考えてしまった。 50代女性
いなほ保育園の子どもたち・・・
子どもたちが「今」やりたい事をのびのびとさせていることが
その後の生きる力につながるのだろうな・・・と思いました。
今だと危ない!と先手で行動を止めてしまうかもしれませんが、
見守る勇気も必要だと気付かされました。小4の母より 50代女性
いちばん印象的だったのは、
何でも手づかみで食べていて
先生もそれを叱らないということです。
特に野菜をいやがらずにおいしそうに食べていたのが
とてもよかったです。好き嫌いのない子に育ったのではないでしょうか。
一方で、今なら「きたない」「手を洗ってきて」「危ない!」など、
ママたちの悲鳴も聞こえてきそうです。
親の理解も必要な難しい時代になってしまったなぁと
少しさびしい気持ちになりました。 50代女性
いなほ保育園のスタッフの方々がステキでした。
子ども達の社会性を育てていく、自主性を育てる、
とてもすばらしく心が温かくなる映画でした。
今の親ももっと過保護になりすぎないよう
このような映画を見てほしいです。 50代男性
遠い昔のとても頼もしい自分を思い出し、
映画のシーンの仲間と時間を共有し、
とても楽しい。力強い。
自分の子供時代を過ごせました。すばらしい映画でした。
共有した自分は、今の自分とかなり違う自分でした。
(映画のシーンに慣れるまで少し時間がかかったのが
興味深かったです) 50代女性
途中からの鑑賞でしたがとてもすてきな作品でした。
子どもたちが土、水、火、動物に素手素肌で触れてて
この子たちがどんな風に育っているのか気になりました。
こんな時間を提供できる保育園、
一緒に子どもたちと遊んでみたいと思いました。
沖縄にもあるかしら?
あ、でも、大人としては、ケガが心配で、
ハラハラドキドキでもありました。
すてきな映画をありがとうございます。 50代女性
西原街こばとゆがふ保育園のことを思い出しました。
本土のとある保育園の影響を受けて開設したと聞いてますが、
いはほ保育園のことかと思いました。
子どもがこども時間をすごせることも
主催者、保護者が、守っての活動だと思います。
こどもの自発性、自主性、独創性を育てている
すてきな保育だと思いました。 50代女性
人のたくましさに感動しました。
信じることって大事だと改めて思いました。 50代男性
冷房強すぎ。寒かった。 50代男性
保育士をしてます。
私の園ではありえないシーンばかりで
”大丈夫?”と思ったりしましたが
子ども達の映画が”心配ないよ”と言っていました。
冬の寒い中、はだしで園庭や畑で活動する子ども達、
外でお昼を鼻水しながら、けんかもしながら食べる子ども達、
ブロッコリー、トマト、スイカにかぶりつく子ども達、
ほんとに素晴らしい環境で、もっともっと観たく、映画がとても短く感じました。
こういう園で育った子は、きっと心身共にたくましい大人になっていくと思います。
自分の保育、明日から少し変わるかも… 50代女性
観る前からとても楽しみにしていた映画です。
感動しました。
好奇心旺盛な一人一人の豊かな表情、
制限のない関わりの中で、子供達の無限の可能性、
人としての優しさ、生命力、たくましさ、
本来の子供の姿がありました。
とても胸がいっぱいです。
ありがとうございました。
考えさせられる映画でした。 60代女性
人が人生を始めるとき、そこに土があり、
火があり、尊き水があり、人としての群れがある。
そうした原始の頃からの、人のあり方を、
子ども達が供にすごす中で
身をもって味わっていく時間が尊かった。
私達の社会が見失い、いきづまりを感じている今、
生きるはじまりを思った。 60代男性
先生のよけいな声かけが一斉聞こえず、
子ども達の本来の姿が生き生きと描かれていら。
自然に恵まれた環境のすばらしさ。
周りの大人が、子ども達の力を信頼して、子どもに任せていることで、
子ども達が自分で自分を育てている姿に感動しました。
ありがとうございました。 60代女性
すばらしい保育を見せていただいた。
・児童は人として尊ばれる。
・児童は良い環境の中で育てられる。
・児童は社会の一員として重んぜられる。
それらが、すべて整った保育環境で感動しました。 60代女性
理想的な保育園ですね。
都市部では無理な環境です。
子供達のノビノビした行動にうれしくなりました。 60代男性
広い敷地があるとのびのびとした保育ができますね。
沖縄の南部でもやや似かよった(さくらんぼ保育)を行っている
保育園があり、私の孫もそこで育ててもらいました。
今は小5と中1になっていますが、ちゃんと自分の思いを主張できます。
保育園の頃より保育士とのいさかいもあったようですが心を育ててもらい感謝せいています。
幼児期にのびのびとやりたい事をさせる保育は、
その後、子どもの心の成長に良いえいきょうを与えるものだと思います。
本日、すばらしい映写に感謝致します。 60代女性
子供達の目の輝きが、とても印象的でした。
子供の時間とは大切な何かを沢山思い出しました。
ありがとうございました。 60代女性
久々に「ハンラヤー」を観た。
棒を持っている子供も今は消えている。
すずめもギンヤンマも今は見ない。 60代男性
久しぶりに天しんらんまんの子供達がまれてよかった。
こういう教育もいいなと思いました。 70代女性
こどもの時間、私にも遠い昔に確かにありました。
生きる力を持って生まれてきたことを忘れていました。
この先いつまでか解りませんが
毎日を楽しい時間のなかでやりたいことも
がんばろうと強く思いました。
今日はありがとうございました。 70代女性
65年前を思い出しとてもよかったです。 70代男性
子供達の純真でたくましく成長してゆく姿に感動しました。
有難うございました。 70代男性
今回二度目の上映を見ました。
ほのぼのです。子供は野生児のように
育てるものなのかと感じました。
大人は、子供の頃を忘れてしまってますね。
笑顔が見られるのはいいですね。 70代女性
「こどもの時間」最高でした。
こどもの表情のゆたかさ、愛らしさ、
鼻たれはこどもの個性ですね。
本当に忘れていたお目にかかれない鼻たれ、
そして、手、指、足もポチャっとムチムチ健康そのものですね。
幸せな子どもたち、そして最高のいなほ保育園の子ども達、職員の方々、
幸せな時間を味わいました。ありがとうございました。 70代女性
昔に(子供が小さい頃には)戻れない。
子育ては後悔することばかり。
子ども達の顔を見ると気持ちがなごむと共に
自分の子育てを後悔することばかり。 80代女性
よかったです。 80代女性
皆んな子供から成長していく。
良かったです。
皆んなのびのびと育って欲しい。 80代男性
今の時代では考えられない幼児教育です。
感動しました。 90代女性
〈10月会を振り返って〉
「海燕社の小さな映画会2024」10月会。
ご鑑賞の58名のお客様、ありがとうございました。
『こどもの時間』の上映を快く了承して下さいました「野中真理子事務所」様、
野中真理子監督、ありがとうございました。
会場「沖縄県立博物館美術館」様、ありがとうございました。
後援の「沖縄県」「那覇市」様、ありがとうございました。
宣伝にご協力下さいましたマスコミのみなさま、ありがとうございました。
SNSや口コミで宣伝下さいましたみなさま、ありがとうございました。
みなさまに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
海燕社の小さな映画会は海燕社が「観たい」「観て欲しい」映画を
一緒に観ませんか、というゆるっとした気持ちで開催している映画会です。
劇場ではなかなか上映されない映像作品や旧作映画を上映しています。
映画の多様性、特にドキュメンタリーの幅広さを知ってもらいたいという気持ちもあります。
2024年の映画会は10年目を記念してご鑑賞者にオリジナル「栞」をプレゼントしています。
4月会は「獅子」5月会は「木」…上映作品に合わせてテーマを決めてデザインしています。
記念品を「栞」にしたのは、私が映画を観る前や観た後に原作本や関連する本を読みたくなるからです。
映画会の思い出とともに読書の時に「栞」を愛用して頂けたらうれしいです。
「海燕社の小さな映画会2024」の10月会は、
『こどもの時間』(野中真理子監督)を上映しました。
子どものわたし、大人のわたし、ひとり二人として観ました。
子どものわたしにはあこがれのこどもの時間でした。
いいなぁ、いいなぁ、と心で何度呟いた事でしょうか。
やってなかったことばかり、やってみたいことばかり。
冬のあの大きな焚火に心で手をあてて温まっていました。
大人のわたしは、今の子ども達を想うと考えこみました。
沖縄の子ども達、日本中の子ども達に、
このようなこどもの時間を持たせてあげたいけれど、
私達大人は子どもに贈ることができるのか、と。
自然らしい自然があること、
親と子と先生が信じあうこと、
この二つが揃えば、この映画のような「こどもの時間」は叶えられるはずです。
大人が問われていると思います。
映画『こどもの時間』は、
忘れていた「こどもの時間」をその大切さを気づかせてくれました。
過ぎてゆく日常の「おとなの時間」を立ち止まって想うことができました。
「わたしの時間」を大切にしたいと思いました。ありがとうございました。
映像作品は完成後が大事だと思っています。
製作者としては観てもらうこと、観客としては観ること、
その二つを映画に贈りたいです。
「海燕社の小さな映画会」はその一役になって欲しいと願っています。
アンケートの提出して下さった51名様に感謝申し上げます。
アンケートのご協力ありがとうございました。
感想を書いて下さったのは46名様。感想ブログ掲載不可は3名様。
43名のお客様の感想を上記で紹介させて頂きました。
ブログでのお客様全員の感想を紹介する活動を続けています。
海燕社のスタッフだけで読むには惜しい内容の感想ばかりだからです。
映画会に来て下さった皆様と感想を共有したい、
映画製作者のみなさまにお客様の感想を伝えたい、
映画会に来れなかったみなさまに作品について伝えたい、
という思いで感想をブログで紹介しています。
これからも続けます。ご協力をよろしくお願いします。
城間あさみ
Posted by カイエンシャ at
16:17
│海燕社の小さな映画会
2024年10月04日
「海燕社の小さな映画会2024 8月会」『イザイホウ』『南島残照 女たちの針突』
海燕社の小さな映画会2024 8月会
【2024.8.10(日)/沖縄県立博物館・美術館3階講堂
13:15受付開場/14:05上映開始/15:30終了】
鑑賞料:1200円(予約一般)/1500円(当日一般)
※高校生以下無料券(予約先着10名様まで)
〈上映作品〉
『イザイホウ 』
(1966年撮影/1967年製作/野村岳也監督/49分/海燕社)
『南島残照 女たちの針突』
(1984年撮影/2014年製作/北村皆雄監督/64分/ヴィジュアルフォークロア)
〈入場まで〉
1.受付:①予約の方-鑑賞券(1,200円)/当日の方-当日券(1,500円)
②資料配布
2.手指アルコール消毒(各自:劇場入口設置)
3.入場着席:自由席
※配布資料
ラインナップ1枚、8月会チラシ1枚、
アンケート用紙、案内希望カード、下敷き、クリアファイル、クリップ鉛筆
※ご来場者プレゼント
10年目記念オリジナル栞1枚(8月会デザインテーマ「女性と祈り」)
<プログラム>
※予告編上映『こどもの時間』(10月会)
1.開会
2.主催挨拶(城間あさみ)
3.『イザイホウ 』
(1966年撮影/1967年製作/野村岳也監督/49分/海燕社)
4.『南島残照 女たちの針突』
(1984年撮影/2014年製作/北村皆雄監督/64分/ヴィジュアルフォークロア)
5.閉会(アンケート記入)
<スタッフ> 4人(海燕社2人、同人1人、ボランティアスタッフ2人)
準備・片付け:全スタッフ
受付:(澤岻健/ボランティアスタッフ)
会場:(ボランティアスタッフ)
上映:(海燕社同人)
司会:(城間あさみ)
〈後援〉沖縄県/那覇市
【お客様の感想(アンケートより)】
イザイホウ、ハジチ、共にどのようなものか、
歴史等を知りたかったので観にきました。
貴重な映像を目にすることができました。
ありがとうございました。
X(Twitter)等でも海燕社さんの投稿も注目しています。 女性
ハジチもイザイホーもよかったです。
あらためて沖縄の歴史を振り返るいい映像ですね。
90代の女性たち、生き生きとしていて美しいですね。 女性
イザイホーとハジチ、
どちらも今はもう実際に見ることのかなわない
沖縄の風習を、映像の記録でみられてとても良かった。 10代男性
すばらしい2本立てでした。
作品を上映して下さり、ありがとうございました。
とても感動し、今はこれ以上のことばがみつかりません。
今日、感じたこと、考えたことを忘れずに生きてゆきたいと思います。 20代女性
大学の卒業論文でハジチについて調べている者です。
主眼は「ハジチの現在」についてです。
そもそもの基礎として本来の、かつてのハジチを理解することは重要であります。
今回の「南島残照」lは、ただ文献資料を眺めているだけでは決して分からない
ハジチの息遣いを伝えてくれる作品でした。
自分は男で、また内地の人間なので当事者になることは到底あり得ないですが、
少しでも理解の助けになったと感じています。ありがとうございました。 20代男性
テーマは違えど、同じ”失われた伝統”についての映画を見て、
価値観は時代によって変わっていくものであるので
このような伝統が消えていくのも
また時代のながれなんだろうな、と思いました。
今回のこの映画のようrに”記録”として残しておくことが大切だと思いました。
良い映画をみさせて頂きました。有難うございました。 30代女性
沖縄の女性たちの力強さと繊細さを感じる2本でした。
イザイホーの唄と掛け声が独特で、その場で見ると
すごく神秘的なのだろうなと思いました。
南島残照を観るのは二度目でしたが、
一度目とは違う視点で見ることができました。
一度目は針突を調査する側の視点で観ていましたが
今日は話者のおばあさんたちの表情や針突の文様を
じっくり観れました。アンコール上映、ありがとうございました。
※「老人と海」「糸満の女」をもう一度観たいです。 30代女性
素晴らしい作品を上映して頂いてありがとうございました。
念願叶って「イザイホウ」を観ることが出来、とても嬉しく思います。
作品の感想に関しては、想いがありすぎて、うまく今はまとめられませんが
上映中、向かって右側の時計(デジタル)が消灯すると見やすいです。 30代男性
貴重は映像をしっかり見れてよかったです。
関心の高さもあるので、
有識者の方々のトークなどもあるといいなと思いました。 30代女性
自分の住む南城市にある久高島。
とても素晴らしい島のある市なのだと改めて思った。
もう1度、久高に行きたいと思います。 30代女性
たまたま博物館に来た時に、上映会を知り、参加しました。
非常に価値のある、保存する意義のある記録だと思います。
ありがとうございました。 30代男性
イザイホウは見るのが3度目ですが、
観るたびに発見があり今日も新鮮に拝見しました。
南島残照は、2度目の感想でしたが、
糸満のタバコの女性が印象深く、
思い出して再び笑っていまいました。
個性的な皆さんのゆんたくが楽しく、ハジチの記録だけでなく、
沖縄の言葉を聞ける貴重な記録作品だと思いました。
ありがとうございました! 40代女性
久高島には、行ったことがないですが、
神の島として知られる島、その祈りの神事、
その全体の雰囲気を見ることができて、とても良かったです。
4日もかけて、神とつながる儀式を行っていたこと、男と女の役割があったこと、
今はどのような感じなのか、興味が湧きました。
でも、軽い気持ちで訪れるこてゃできないのかな・・・と思ったりしました。
ハジチ。
おばーがかわいかった。
ほこらしいという気持ち、その痛みをがまんしてまで、
行ったハジチ、すごいです! 40代女性
アンコールが無くとも、
毎年定期的に上映して頂きたい作品です。
ありがとうございました。
(イザイホウ)
1978年を以降消滅ということですが、
現在島に住んでおられる方たちにインタビューしていただきたいな、と思いました。
(南島残照)
”大和に連れていかれないためにハジチを打った”と。
当時、沖縄(琉球)の女性たちにとって本土はどのように映っていたのか?
多くの女性が”野ばん”という言葉が使われていたのが気に止まりました。 40代女性
沖縄の貴重な記録を残し公開して下さりありがとうございました。
イザイホウでの女性達は厳しい自然の中でくらしていく中で、
あらゆる苦難を受け入れ、消化して、すべてを包み込むような
優しさがつたわってきました。私もこうありたいと思いました。
ハジチの方は、当時のおばあ達の声(うちなーぐち)が聞けたことが
生の方言を聞く機会を失った私にとってなつかしくとても充実した時間でした。 40代女性
ハジチについて語る映像は初めて見ました。
女性が大人の仲間入りをする
誇り高き儀式のようなものだったんだと知れてよかったです。
イザイホーは、ウスデークのようだなと思いました。 40代女性
沖縄生まれ育ちですが、知らないことばかりでした。
貴重な映像を観せていただきありがとうございました。
文化や風習を映像で残すことはとても大事なことですね。
今の私たちのことも、
未来の人たちはどう感じるのだろう?と考えさせられました。 40代女性
インタビュー・映像を見せて頂いたことで、
文献などではわからない空気感と感じることができたので
とても良かったです。
初めて参加させてもらいましたが
2本だては、その関連性が見事でした。
貴重な機会をありがとうございました。 40代女性
南の小さな島で、役目を果たしながら
運命のままに生きた女性たちのたしかな軌跡を
イザイホーとハジチ、2つのアスペクトを通して知り、
感じることができた豊かな時間でした。 40代女性
2作品とも前から観たかった作品だったので
このような形で2本立て上映をしていただきありがとうございました。
2作品とも沖縄の女性の生きざまのようなものを
感じとても印象に残りました。
イザイホウもハジチも今は無くなってしまったものですが
2つのものに込められた思いのようなものは
ずっとこれからも忘れないでいたいなと感じました。 40代女性
母方の祖母がハジチをしていた様な記憶があります。
帰宅後、母(80代)に何か知っているか聞いてみようと思います。
4月上映の「茶の湯」に興味があります。
再映等の情報があれば知りたいです。
方言禁止法しかり、ハジチ禁止法に関しても政府の悪本だと思う。
失ってはじめて大切な物だと気付くものなんでしょうか? 50代女性
特にハジチのドキュメンタリーは印象深かったです。
最近、北谷にハジチを再現している
タトゥーアーティストがいると聞いている。
さすがに本物のタトゥーはできないにしても、
ヘナによるタトゥーは試してみたいと思った。
ウチナーンチュとして、
こういう文化習俗はずっとおぼえておきたい。 50代女性
先日、久高島へ行き、又、
「日本人の魂の原郷 沖縄久高島」という本を読んだばかりでしたので
イザイホーの貴重な映像を見ることができ感動しました。
ハジチには、当時の女性たちの祈りやまじないなどの気持ちが
こめられていたことを知りました。
当時の女性たちのほこりであり、
美しい残照であることを感じた。 50代女性
楽しみにして参りました。
はずかしそうにハジチを見せながら話しをする
お婆さんたちがまるで乙女のように見えました。
昔、そんな乙女たちがいたんだと今では夢のように
思えるのがなんだか切ないですね。 50代女性
イザイホー、ハジチ、
共に女性の生き方(当時の社会の中での)を理解できる内容でした。
上映会の開催、ありがとうございました。
ハジチについては、
1984年当時、私の祖母(明治44年生ー宮古島)にも
ハジチがあったと記憶しています。
くわしく知りたいと思いました。 50代女性
どちらも女性を中心にした映像でしたね。
南島残照は勉強になりました。
祖母にもハジチがありました(ナハ市首里の人)
生きていれば120くらいでしょうか。
どうしていハジチをしているのかと聞くと
祖母は「結婚した女がやるもの」と言ってましたが
本当のところはどうだったのか。
私が3つだった覚えです。
イザイホウは久しぶりに拝見しました。
島の現状にやるせなさも・・・
そして、10年目、おめでとうございます。
今後も楽しみにしています。 50代女性
おもしろかったです。
沖縄の歴史文化を記録に残してくれてありがとうございます。
南島残照はすばらしい記録映像です。 50代男性
映像として残すことの大切さを感じました。
頑張って下さい。 50代男性
貴重な映像資料だった。
2024年の今からは想像できないものだった。 50代男性
また再々上映して欲しい。 50代男性
私は今65才。
何才の頃が覚えていませんが、
ハジチのおばー達を実際に見ましたが
とても”こわかった”と覚えています。
今では1人も残っていない貴重な映像ありがとうございました。
60年前の記憶でしょうか?(私の)
次回も楽しみにしています。
イザイホーの記録も良かったです。 60代女性
大変よかった。 60代女性
知りたかった。
イザイホーの映写をみせてもらってよかったです。 60代女性
イザイホウ
当時の久高島の人々の生活の様子がわかりました。
針突
無知と迷信が生みだした悪習だったと思います。 60代男性
1978年の最後のイザイホウを学生時代にみました。
その12年後のイザイホウの開催年に
NHKで特集をしていましたが、外間ノロか誰か神人の方が、
開催されないことの無念と何の気持ちを込めてなのか、
当然、エーファイ!エーファイ!と神歌を歌い踊った(?)シーンが印象的でした。
この’66年の記録映像中に「次は開催されるか、わからんさぁね、
開催されなかったら、神様に開催されないことを報告するさぁ」と
言っていたシーンがズバリ、実現したことを感慨深く、今日の上映で想いました。
上映記録の中で「根人(ねびと)」とナレーションしていたのが気になりましが
久高島では根人(ニーッチュ)のことを
根人(ねびと)と呼ぶようになっていたのでしょうか。 60代男性
幼い頃の記憶がよみがえりなつかしく思いました。
神聖な空気感に触れる事や目に見えない神への畏怖の念が
日常の中、いたる所に息づいていた時代でした。
ありがとうございました。 60代女性
こんなに素敵な映像を残して下さり
ありがとうございました。
”老人と海”に続き最高でした。
ハジチの意味を知る事ができた事に感謝します。
亡き祖母の手にもありました。 60代女性
イザイホーは、だいぶ目にみて、
ものすごく衝撃を受けたことを憶えています。
それから上映を待ちわびて幾度かチャンスを逃して
やっと今日観る事がかないました。
ハジチは、祖母(明治生まれ)がしていて、
ハジチをしていないとヤマトに連れて行かれるという事で
突いたと言っていました。
理由が意味が判って良かったです。 60代女性
芸大でハジチをテーマに研究論文を書きたいという
学生がいましたので関心を持つようになりました。
「南島残照」が見られてよかったです。 60代女性
とても貴重な記録を見させて頂きありがとうございました。
これからも頑張って創って下さい。 60代女性
イザイホーはもう消滅した祭事ではあるが、
今もあの島にある祭事の元となっているのでしょう。
企画、ありがとう。 70代女性
ハジチは針突と書くことで意味が分かりました。
琉球の言葉は音を聞いて、全然理解できませんが
漢字に置き換えてもらうと分かるということは、
同じ原語になるのでしょうか。
中国語の漢字は、中国読みで、別な文化園と考えていまいますが、
大和につれて行かれなくなかったから、という声は、
生まれた所に住みたいと理解しました。
これは世界共通でしょう。仲間、家族の身を守るオキテは、
外部に出て行かせないためのものとも思えた。
少し琉球のことが分かって嬉しかった。ありがとう。 70代女性
貴重な映像を残していただきありがとうございました。
人々の生活の激しさの中で、たくましく、豊かな祈りをこめて
生活していることに感動しました。 70代女性
「イザイホウ」を見るのは、3回目だと思うが
なかなか私の体の中まで入ってこなくて、
今回で少しずつ分かったような気がした。
「ハジチ」も2回目だと思うが、ハジチをした理由や
模様はいろりおあるようで、最後の祈りや沖縄の歴史と
関わっているというコメントが特に心に残った。 70代女性
イザイホーの久高島に行ったことがあります。
祭そのもを見ることはできませんでしたが
神々の島だと感じることはできました。
映像を見て女性たちの宗教性はどこに在るのだろうと想像を巡らしました。
ハジチは子供の頃の、おばあさんたちを想い出しました。 70代女性
女達の生き方を見る時、つつしみ深く、強く生きる姿は、
どんな時代でも、感動をもらうものです。
女から生をもらった男達よ、女を大切にして下さい、と言いたい。
イザイホーは、ニュースで最後になると言う事を知っていました(当時)。
このように記録して下さりありがとうございます。
ハジチは、祖母の姉になる人がしていました(本島)。
子どもながらに、不気味なもののように思えました。
祖母からは、ヤマトにつれていかれないようにしていたとか、
祖母も、二・三年でしたか早ければさせられていたとか言っていました。 70代女性
イザイホー良かったです。
ハジチは、私の祖母(亡くなった)もやっていました。
小学生の頃、その指を見てよく聞いていたことを
(どうしてそうしたのかを)思い出しました。
今日の映画を見て意味がわかったように思います。
90代の人達、それぞれ頭のしっかりした方いて感心しました。 70代女性
二年前に平和通りの雑貨屋さんで若い女性が
シーサーの色付けをされていました。
彼女の指にはハジチが彫られていました。
私が動くハジチを見たのはこれが初めてで
色々とお話しました。大祖母がハジチを入れていて
写真を見て興味を持ち、自分に入れたと言っておられたような。
ふと、それを思い出しました。
ありがとうございました。 70代女性
ハジチは小学生の頃、近所のおばあちゃんの両手の甲に
黒い模様として見たことがあります。
前回上映でもハジチに関する情報が得られ感謝致しております。
今回も、ハジチの時代があったこと忘れないために足を運びました。
上映、ありがとうございました。
イザイホーの願。
30~42才の女性たちによる行事。 70代女性
ハジチはいろいろな意味があったのだと思いました。
幼い頃、2、3軒となりのおばあちゃんの手にあったのを思い出しました。
アイヌや南島の人達が手などに入れているのをみると
ファッション感覚であったのかなとも思いました。 70代女性
祖母がハジチをしていました。
その頃は私は高校生でした。
そうしていれずみがあるの?と聞いた時は
既婚者であるしるしと話していました。
その頃は、あちら、こちらで見かけたので、そうなんだと思い
深く考えませんでした。今となってはどうして深く聞かなかった事に
対してとても後悔しています。今日は貴重な映写でした。
とても感動しました。
誇りとして針突をしたいたのですね。
そらにはびっくりしました。一つのおしゃれでもあったんだと思いました。
ありがとうございました。 70代
南島残照女たちの針突
石垣島の実家の本家の屋号が「ティーツキヤー」と言われていて
石垣島に住んでいる時は「入墨」の施術をしている先祖がいるんだ、
くらいに考えていたのだが、最近「針突」に背景を知ることにより
「ティーツキ」についても理解が進むのではと申込みました。
地域によって、背景が違う、思いが違うこともありますが、
納得できる内容を知ることができました。
イザイホウ
現在は実施されていないのが残念。 70代女性
途中休憩が欲しかった。
イザイホウ。
昔の様子がよくわかる。
ハジチ。
だだのイレズミかと思ったら
いろんな文化が育まれていて感慨深かkjった。 70代女性
イザイホーの映像が見られた事は本当に良かった。
ハジチの事は祖母もしていのでもっときょうみを持って
聞いておけばよかったと思った。
祖母は結婚した女性と言っていた。 80代女性
イザイホウ 貴重な映像ですね。
ハジチ 祖母のハジチを思い出します。 80代女性
久高島のイザイホー復活できたらいいですが。
ハジチは痛いのにようがまんして良くやったと思う。 80代男性
胸がいっぱいになりました。
祖母の手を思い出しました。
貧しい時代に強く生き抜いた女たちを誇りに思います。 80代女性
沖縄の女性史を改めて知る事が出来ました。
ありがとうございました。 80代女性
見るのは2回目です。
とてもよかったので、又、機会があって
嬉しく思います。
本当にすばらしい記録映画。
その当時を知る手がかりと思います。
残して下さってありがとうございました。 80代女性
子供の頃、祖母のハジチを見ました。
その模様が五つ星だとはじめて知って涙が出ました。
模様にもそれぞれの意味があったことも。 90代女性
〈8月会を振り返って〉
「海燕社の小さな映画会2024」8月会。
ご鑑賞の106名のお客様、ありがとうございました。
『南島残照 女たちの針突』の上映を快く了承して下さいました「ヴィジュアルフォークロア」様、
北村皆雄監督、ありがとうございました。
会場「沖縄県立博物館美術館」様、ありがとうございました。
後援の「沖縄県」「那覇市」様、ありがとうございました。
宣伝にご協力下さいましたマスコミのみなさま、ありがとうございました。
SNSや口コミで宣伝下さいましたみなさま、ありがとうございました。
みなさまに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
海燕社の小さな映画会は海燕社が「観たい」「観て欲しい」映画を
一緒に観ませんか、というゆるやかな気持ちで開催している映画会です。
劇場ではなかなか上映されない映像作品や旧作映画を上映しています。
映画の多様性、特にドキュメンタリーの幅広さを知ってもらいたいという気持ちもあります。
2024年の映画会は10年目を記念してご鑑賞者にオリジナル「栞」をプレゼントしています。
4月会は「獅子」5月会は「木」…上映作品に合わせてテーマを決めてデザインしています。
記念品を「栞」にしたのは、私が映画を観る前や観た後に原作本や関連する本を読みたくなるからです。
映画会の思い出とともに読書の時に「栞」を愛用して頂けたらうれしいです。
「海燕社の小さな映画会2024」の8月会は、
『イザイホウ』(野村岳也監督)と『南島残照 女たちの針突』(北村皆雄監督)を上映しました。
わたしは2作品に『女の手』を想います。
イザイホウの祈りの手、
南島残照の針突の手、
記録されたかつての沖縄の女の手。
わたしの手につながっているだろう、かつての手、あの手、その手・・・
愛おしさと苦々しさと…言葉に上手く表現できないまま
それらの手をみつめていたように思います。
映像作品は完成後が大事だと思っています。
製作者としては観てもらうこと、観客としては観ること、
その二つを映画に贈りたいです。
「海燕社の小さな映画会」はその一役になって欲しいと願っています。
アンケートの提出して下さった71名様に感謝申し上げます。
アンケートのご協力ありがとうございました。
感想を書いて下さったのは63名様。感想ブログ掲載不可は2名様。
61名のお客様の感想を上記で紹介させて頂きました。
ブログでのお客様全員の感想を紹介する活動を続けています。
海燕社のスタッフだけで読むには惜しい内容の感想ばかりだからです。
映画会に来て下さった皆様と感想を共有したい、
映画製作者のみなさまにお客様の感想を伝えたい、
映画会に来れなかったみなさまに作品について伝えたい、
という思いで感想をブログで紹介しています。
これからも続けます。ご協力をよろしくお願いします。
城間あさみ
【2024.8.10(日)/沖縄県立博物館・美術館3階講堂
13:15受付開場/14:05上映開始/15:30終了】
鑑賞料:1200円(予約一般)/1500円(当日一般)
※高校生以下無料券(予約先着10名様まで)
〈上映作品〉
『イザイホウ 』
(1966年撮影/1967年製作/野村岳也監督/49分/海燕社)
『南島残照 女たちの針突』
(1984年撮影/2014年製作/北村皆雄監督/64分/ヴィジュアルフォークロア)
〈入場まで〉
1.受付:①予約の方-鑑賞券(1,200円)/当日の方-当日券(1,500円)
②資料配布
2.手指アルコール消毒(各自:劇場入口設置)
3.入場着席:自由席
※配布資料
ラインナップ1枚、8月会チラシ1枚、
アンケート用紙、案内希望カード、下敷き、クリアファイル、クリップ鉛筆
※ご来場者プレゼント
10年目記念オリジナル栞1枚(8月会デザインテーマ「女性と祈り」)
<プログラム>
※予告編上映『こどもの時間』(10月会)
1.開会
2.主催挨拶(城間あさみ)
3.『イザイホウ 』
(1966年撮影/1967年製作/野村岳也監督/49分/海燕社)
4.『南島残照 女たちの針突』
(1984年撮影/2014年製作/北村皆雄監督/64分/ヴィジュアルフォークロア)
5.閉会(アンケート記入)
<スタッフ> 4人(海燕社2人、同人1人、ボランティアスタッフ2人)
準備・片付け:全スタッフ
受付:(澤岻健/ボランティアスタッフ)
会場:(ボランティアスタッフ)
上映:(海燕社同人)
司会:(城間あさみ)
〈後援〉沖縄県/那覇市
【お客様の感想(アンケートより)】
イザイホウ、ハジチ、共にどのようなものか、
歴史等を知りたかったので観にきました。
貴重な映像を目にすることができました。
ありがとうございました。
X(Twitter)等でも海燕社さんの投稿も注目しています。 女性
ハジチもイザイホーもよかったです。
あらためて沖縄の歴史を振り返るいい映像ですね。
90代の女性たち、生き生きとしていて美しいですね。 女性
イザイホーとハジチ、
どちらも今はもう実際に見ることのかなわない
沖縄の風習を、映像の記録でみられてとても良かった。 10代男性
すばらしい2本立てでした。
作品を上映して下さり、ありがとうございました。
とても感動し、今はこれ以上のことばがみつかりません。
今日、感じたこと、考えたことを忘れずに生きてゆきたいと思います。 20代女性
大学の卒業論文でハジチについて調べている者です。
主眼は「ハジチの現在」についてです。
そもそもの基礎として本来の、かつてのハジチを理解することは重要であります。
今回の「南島残照」lは、ただ文献資料を眺めているだけでは決して分からない
ハジチの息遣いを伝えてくれる作品でした。
自分は男で、また内地の人間なので当事者になることは到底あり得ないですが、
少しでも理解の助けになったと感じています。ありがとうございました。 20代男性
テーマは違えど、同じ”失われた伝統”についての映画を見て、
価値観は時代によって変わっていくものであるので
このような伝統が消えていくのも
また時代のながれなんだろうな、と思いました。
今回のこの映画のようrに”記録”として残しておくことが大切だと思いました。
良い映画をみさせて頂きました。有難うございました。 30代女性
沖縄の女性たちの力強さと繊細さを感じる2本でした。
イザイホーの唄と掛け声が独特で、その場で見ると
すごく神秘的なのだろうなと思いました。
南島残照を観るのは二度目でしたが、
一度目とは違う視点で見ることができました。
一度目は針突を調査する側の視点で観ていましたが
今日は話者のおばあさんたちの表情や針突の文様を
じっくり観れました。アンコール上映、ありがとうございました。
※「老人と海」「糸満の女」をもう一度観たいです。 30代女性
素晴らしい作品を上映して頂いてありがとうございました。
念願叶って「イザイホウ」を観ることが出来、とても嬉しく思います。
作品の感想に関しては、想いがありすぎて、うまく今はまとめられませんが
上映中、向かって右側の時計(デジタル)が消灯すると見やすいです。 30代男性
貴重は映像をしっかり見れてよかったです。
関心の高さもあるので、
有識者の方々のトークなどもあるといいなと思いました。 30代女性
自分の住む南城市にある久高島。
とても素晴らしい島のある市なのだと改めて思った。
もう1度、久高に行きたいと思います。 30代女性
たまたま博物館に来た時に、上映会を知り、参加しました。
非常に価値のある、保存する意義のある記録だと思います。
ありがとうございました。 30代男性
イザイホウは見るのが3度目ですが、
観るたびに発見があり今日も新鮮に拝見しました。
南島残照は、2度目の感想でしたが、
糸満のタバコの女性が印象深く、
思い出して再び笑っていまいました。
個性的な皆さんのゆんたくが楽しく、ハジチの記録だけでなく、
沖縄の言葉を聞ける貴重な記録作品だと思いました。
ありがとうございました! 40代女性
久高島には、行ったことがないですが、
神の島として知られる島、その祈りの神事、
その全体の雰囲気を見ることができて、とても良かったです。
4日もかけて、神とつながる儀式を行っていたこと、男と女の役割があったこと、
今はどのような感じなのか、興味が湧きました。
でも、軽い気持ちで訪れるこてゃできないのかな・・・と思ったりしました。
ハジチ。
おばーがかわいかった。
ほこらしいという気持ち、その痛みをがまんしてまで、
行ったハジチ、すごいです! 40代女性
アンコールが無くとも、
毎年定期的に上映して頂きたい作品です。
ありがとうございました。
(イザイホウ)
1978年を以降消滅ということですが、
現在島に住んでおられる方たちにインタビューしていただきたいな、と思いました。
(南島残照)
”大和に連れていかれないためにハジチを打った”と。
当時、沖縄(琉球)の女性たちにとって本土はどのように映っていたのか?
多くの女性が”野ばん”という言葉が使われていたのが気に止まりました。 40代女性
沖縄の貴重な記録を残し公開して下さりありがとうございました。
イザイホウでの女性達は厳しい自然の中でくらしていく中で、
あらゆる苦難を受け入れ、消化して、すべてを包み込むような
優しさがつたわってきました。私もこうありたいと思いました。
ハジチの方は、当時のおばあ達の声(うちなーぐち)が聞けたことが
生の方言を聞く機会を失った私にとってなつかしくとても充実した時間でした。 40代女性
ハジチについて語る映像は初めて見ました。
女性が大人の仲間入りをする
誇り高き儀式のようなものだったんだと知れてよかったです。
イザイホーは、ウスデークのようだなと思いました。 40代女性
沖縄生まれ育ちですが、知らないことばかりでした。
貴重な映像を観せていただきありがとうございました。
文化や風習を映像で残すことはとても大事なことですね。
今の私たちのことも、
未来の人たちはどう感じるのだろう?と考えさせられました。 40代女性
インタビュー・映像を見せて頂いたことで、
文献などではわからない空気感と感じることができたので
とても良かったです。
初めて参加させてもらいましたが
2本だては、その関連性が見事でした。
貴重な機会をありがとうございました。 40代女性
南の小さな島で、役目を果たしながら
運命のままに生きた女性たちのたしかな軌跡を
イザイホーとハジチ、2つのアスペクトを通して知り、
感じることができた豊かな時間でした。 40代女性
2作品とも前から観たかった作品だったので
このような形で2本立て上映をしていただきありがとうございました。
2作品とも沖縄の女性の生きざまのようなものを
感じとても印象に残りました。
イザイホウもハジチも今は無くなってしまったものですが
2つのものに込められた思いのようなものは
ずっとこれからも忘れないでいたいなと感じました。 40代女性
母方の祖母がハジチをしていた様な記憶があります。
帰宅後、母(80代)に何か知っているか聞いてみようと思います。
4月上映の「茶の湯」に興味があります。
再映等の情報があれば知りたいです。
方言禁止法しかり、ハジチ禁止法に関しても政府の悪本だと思う。
失ってはじめて大切な物だと気付くものなんでしょうか? 50代女性
特にハジチのドキュメンタリーは印象深かったです。
最近、北谷にハジチを再現している
タトゥーアーティストがいると聞いている。
さすがに本物のタトゥーはできないにしても、
ヘナによるタトゥーは試してみたいと思った。
ウチナーンチュとして、
こういう文化習俗はずっとおぼえておきたい。 50代女性
先日、久高島へ行き、又、
「日本人の魂の原郷 沖縄久高島」という本を読んだばかりでしたので
イザイホーの貴重な映像を見ることができ感動しました。
ハジチには、当時の女性たちの祈りやまじないなどの気持ちが
こめられていたことを知りました。
当時の女性たちのほこりであり、
美しい残照であることを感じた。 50代女性
楽しみにして参りました。
はずかしそうにハジチを見せながら話しをする
お婆さんたちがまるで乙女のように見えました。
昔、そんな乙女たちがいたんだと今では夢のように
思えるのがなんだか切ないですね。 50代女性
イザイホー、ハジチ、
共に女性の生き方(当時の社会の中での)を理解できる内容でした。
上映会の開催、ありがとうございました。
ハジチについては、
1984年当時、私の祖母(明治44年生ー宮古島)にも
ハジチがあったと記憶しています。
くわしく知りたいと思いました。 50代女性
どちらも女性を中心にした映像でしたね。
南島残照は勉強になりました。
祖母にもハジチがありました(ナハ市首里の人)
生きていれば120くらいでしょうか。
どうしていハジチをしているのかと聞くと
祖母は「結婚した女がやるもの」と言ってましたが
本当のところはどうだったのか。
私が3つだった覚えです。
イザイホウは久しぶりに拝見しました。
島の現状にやるせなさも・・・
そして、10年目、おめでとうございます。
今後も楽しみにしています。 50代女性
おもしろかったです。
沖縄の歴史文化を記録に残してくれてありがとうございます。
南島残照はすばらしい記録映像です。 50代男性
映像として残すことの大切さを感じました。
頑張って下さい。 50代男性
貴重な映像資料だった。
2024年の今からは想像できないものだった。 50代男性
また再々上映して欲しい。 50代男性
私は今65才。
何才の頃が覚えていませんが、
ハジチのおばー達を実際に見ましたが
とても”こわかった”と覚えています。
今では1人も残っていない貴重な映像ありがとうございました。
60年前の記憶でしょうか?(私の)
次回も楽しみにしています。
イザイホーの記録も良かったです。 60代女性
大変よかった。 60代女性
知りたかった。
イザイホーの映写をみせてもらってよかったです。 60代女性
イザイホウ
当時の久高島の人々の生活の様子がわかりました。
針突
無知と迷信が生みだした悪習だったと思います。 60代男性
1978年の最後のイザイホウを学生時代にみました。
その12年後のイザイホウの開催年に
NHKで特集をしていましたが、外間ノロか誰か神人の方が、
開催されないことの無念と何の気持ちを込めてなのか、
当然、エーファイ!エーファイ!と神歌を歌い踊った(?)シーンが印象的でした。
この’66年の記録映像中に「次は開催されるか、わからんさぁね、
開催されなかったら、神様に開催されないことを報告するさぁ」と
言っていたシーンがズバリ、実現したことを感慨深く、今日の上映で想いました。
上映記録の中で「根人(ねびと)」とナレーションしていたのが気になりましが
久高島では根人(ニーッチュ)のことを
根人(ねびと)と呼ぶようになっていたのでしょうか。 60代男性
幼い頃の記憶がよみがえりなつかしく思いました。
神聖な空気感に触れる事や目に見えない神への畏怖の念が
日常の中、いたる所に息づいていた時代でした。
ありがとうございました。 60代女性
こんなに素敵な映像を残して下さり
ありがとうございました。
”老人と海”に続き最高でした。
ハジチの意味を知る事ができた事に感謝します。
亡き祖母の手にもありました。 60代女性
イザイホーは、だいぶ目にみて、
ものすごく衝撃を受けたことを憶えています。
それから上映を待ちわびて幾度かチャンスを逃して
やっと今日観る事がかないました。
ハジチは、祖母(明治生まれ)がしていて、
ハジチをしていないとヤマトに連れて行かれるという事で
突いたと言っていました。
理由が意味が判って良かったです。 60代女性
芸大でハジチをテーマに研究論文を書きたいという
学生がいましたので関心を持つようになりました。
「南島残照」が見られてよかったです。 60代女性
とても貴重な記録を見させて頂きありがとうございました。
これからも頑張って創って下さい。 60代女性
イザイホーはもう消滅した祭事ではあるが、
今もあの島にある祭事の元となっているのでしょう。
企画、ありがとう。 70代女性
ハジチは針突と書くことで意味が分かりました。
琉球の言葉は音を聞いて、全然理解できませんが
漢字に置き換えてもらうと分かるということは、
同じ原語になるのでしょうか。
中国語の漢字は、中国読みで、別な文化園と考えていまいますが、
大和につれて行かれなくなかったから、という声は、
生まれた所に住みたいと理解しました。
これは世界共通でしょう。仲間、家族の身を守るオキテは、
外部に出て行かせないためのものとも思えた。
少し琉球のことが分かって嬉しかった。ありがとう。 70代女性
貴重な映像を残していただきありがとうございました。
人々の生活の激しさの中で、たくましく、豊かな祈りをこめて
生活していることに感動しました。 70代女性
「イザイホウ」を見るのは、3回目だと思うが
なかなか私の体の中まで入ってこなくて、
今回で少しずつ分かったような気がした。
「ハジチ」も2回目だと思うが、ハジチをした理由や
模様はいろりおあるようで、最後の祈りや沖縄の歴史と
関わっているというコメントが特に心に残った。 70代女性
イザイホーの久高島に行ったことがあります。
祭そのもを見ることはできませんでしたが
神々の島だと感じることはできました。
映像を見て女性たちの宗教性はどこに在るのだろうと想像を巡らしました。
ハジチは子供の頃の、おばあさんたちを想い出しました。 70代女性
女達の生き方を見る時、つつしみ深く、強く生きる姿は、
どんな時代でも、感動をもらうものです。
女から生をもらった男達よ、女を大切にして下さい、と言いたい。
イザイホーは、ニュースで最後になると言う事を知っていました(当時)。
このように記録して下さりありがとうございます。
ハジチは、祖母の姉になる人がしていました(本島)。
子どもながらに、不気味なもののように思えました。
祖母からは、ヤマトにつれていかれないようにしていたとか、
祖母も、二・三年でしたか早ければさせられていたとか言っていました。 70代女性
イザイホー良かったです。
ハジチは、私の祖母(亡くなった)もやっていました。
小学生の頃、その指を見てよく聞いていたことを
(どうしてそうしたのかを)思い出しました。
今日の映画を見て意味がわかったように思います。
90代の人達、それぞれ頭のしっかりした方いて感心しました。 70代女性
二年前に平和通りの雑貨屋さんで若い女性が
シーサーの色付けをされていました。
彼女の指にはハジチが彫られていました。
私が動くハジチを見たのはこれが初めてで
色々とお話しました。大祖母がハジチを入れていて
写真を見て興味を持ち、自分に入れたと言っておられたような。
ふと、それを思い出しました。
ありがとうございました。 70代女性
ハジチは小学生の頃、近所のおばあちゃんの両手の甲に
黒い模様として見たことがあります。
前回上映でもハジチに関する情報が得られ感謝致しております。
今回も、ハジチの時代があったこと忘れないために足を運びました。
上映、ありがとうございました。
イザイホーの願。
30~42才の女性たちによる行事。 70代女性
ハジチはいろいろな意味があったのだと思いました。
幼い頃、2、3軒となりのおばあちゃんの手にあったのを思い出しました。
アイヌや南島の人達が手などに入れているのをみると
ファッション感覚であったのかなとも思いました。 70代女性
祖母がハジチをしていました。
その頃は私は高校生でした。
そうしていれずみがあるの?と聞いた時は
既婚者であるしるしと話していました。
その頃は、あちら、こちらで見かけたので、そうなんだと思い
深く考えませんでした。今となってはどうして深く聞かなかった事に
対してとても後悔しています。今日は貴重な映写でした。
とても感動しました。
誇りとして針突をしたいたのですね。
そらにはびっくりしました。一つのおしゃれでもあったんだと思いました。
ありがとうございました。 70代
南島残照女たちの針突
石垣島の実家の本家の屋号が「ティーツキヤー」と言われていて
石垣島に住んでいる時は「入墨」の施術をしている先祖がいるんだ、
くらいに考えていたのだが、最近「針突」に背景を知ることにより
「ティーツキ」についても理解が進むのではと申込みました。
地域によって、背景が違う、思いが違うこともありますが、
納得できる内容を知ることができました。
イザイホウ
現在は実施されていないのが残念。 70代女性
途中休憩が欲しかった。
イザイホウ。
昔の様子がよくわかる。
ハジチ。
だだのイレズミかと思ったら
いろんな文化が育まれていて感慨深かkjった。 70代女性
イザイホーの映像が見られた事は本当に良かった。
ハジチの事は祖母もしていのでもっときょうみを持って
聞いておけばよかったと思った。
祖母は結婚した女性と言っていた。 80代女性
イザイホウ 貴重な映像ですね。
ハジチ 祖母のハジチを思い出します。 80代女性
久高島のイザイホー復活できたらいいですが。
ハジチは痛いのにようがまんして良くやったと思う。 80代男性
胸がいっぱいになりました。
祖母の手を思い出しました。
貧しい時代に強く生き抜いた女たちを誇りに思います。 80代女性
沖縄の女性史を改めて知る事が出来ました。
ありがとうございました。 80代女性
見るのは2回目です。
とてもよかったので、又、機会があって
嬉しく思います。
本当にすばらしい記録映画。
その当時を知る手がかりと思います。
残して下さってありがとうございました。 80代女性
子供の頃、祖母のハジチを見ました。
その模様が五つ星だとはじめて知って涙が出ました。
模様にもそれぞれの意味があったことも。 90代女性
〈8月会を振り返って〉
「海燕社の小さな映画会2024」8月会。
ご鑑賞の106名のお客様、ありがとうございました。
『南島残照 女たちの針突』の上映を快く了承して下さいました「ヴィジュアルフォークロア」様、
北村皆雄監督、ありがとうございました。
会場「沖縄県立博物館美術館」様、ありがとうございました。
後援の「沖縄県」「那覇市」様、ありがとうございました。
宣伝にご協力下さいましたマスコミのみなさま、ありがとうございました。
SNSや口コミで宣伝下さいましたみなさま、ありがとうございました。
みなさまに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
海燕社の小さな映画会は海燕社が「観たい」「観て欲しい」映画を
一緒に観ませんか、というゆるやかな気持ちで開催している映画会です。
劇場ではなかなか上映されない映像作品や旧作映画を上映しています。
映画の多様性、特にドキュメンタリーの幅広さを知ってもらいたいという気持ちもあります。
2024年の映画会は10年目を記念してご鑑賞者にオリジナル「栞」をプレゼントしています。
4月会は「獅子」5月会は「木」…上映作品に合わせてテーマを決めてデザインしています。
記念品を「栞」にしたのは、私が映画を観る前や観た後に原作本や関連する本を読みたくなるからです。
映画会の思い出とともに読書の時に「栞」を愛用して頂けたらうれしいです。
「海燕社の小さな映画会2024」の8月会は、
『イザイホウ』(野村岳也監督)と『南島残照 女たちの針突』(北村皆雄監督)を上映しました。
わたしは2作品に『女の手』を想います。
イザイホウの祈りの手、
南島残照の針突の手、
記録されたかつての沖縄の女の手。
わたしの手につながっているだろう、かつての手、あの手、その手・・・
愛おしさと苦々しさと…言葉に上手く表現できないまま
それらの手をみつめていたように思います。
映像作品は完成後が大事だと思っています。
製作者としては観てもらうこと、観客としては観ること、
その二つを映画に贈りたいです。
「海燕社の小さな映画会」はその一役になって欲しいと願っています。
アンケートの提出して下さった71名様に感謝申し上げます。
アンケートのご協力ありがとうございました。
感想を書いて下さったのは63名様。感想ブログ掲載不可は2名様。
61名のお客様の感想を上記で紹介させて頂きました。
ブログでのお客様全員の感想を紹介する活動を続けています。
海燕社のスタッフだけで読むには惜しい内容の感想ばかりだからです。
映画会に来て下さった皆様と感想を共有したい、
映画製作者のみなさまにお客様の感想を伝えたい、
映画会に来れなかったみなさまに作品について伝えたい、
という思いで感想をブログで紹介しています。
これからも続けます。ご協力をよろしくお願いします。
城間あさみ
Posted by カイエンシャ at
22:28
│海燕社の小さな映画会
2024年07月23日
「海燕社の小さな映画会2024 7月会」 『老人と海』(※ディレクターズカット版)
海燕社の小さな映画会2024 7月会
【2024.7.21(日)/沖縄県立博物館・美術館3階講堂
13:15受付開場/14:05上映開始/15:30終了】
鑑賞料:1200円(予約一般)/1500円(当日一般)
※高校生以下無料券(予約先着10名様まで)
〈上映作品〉
『老人と海 』※ディレクターズカット版
(2010年/シグロ製作/ジャン・ユンカーマン監督/98分)
〈入場まで〉
1.受付:①予約の方-鑑賞券(1,200円)/当日の方-当日券(1,500円)
②資料配布
2.手指アルコール消毒(各自:劇場入口設置)
3.入場着席:自由席
※配布資料
ラインナップ1枚、7月会チラシ1枚、
アンケート用紙、案内希望カード、下敷き、クリアファイル、クリップ鉛筆
※ご来場者プレゼント
10年目記念オリジナル栞1枚(7月会デザインテーマ「老人と海」)
<プログラム>
1.開会
2.主催挨拶(城間あさみ)
3.『老人と海』※ディレクターズカット版
(2010年/シグロ製作/ジャン・ユンカーマン監督/98分)
5.閉会(アンケート記入)
<スタッフ> 4人(海燕社2人、同人1人、ボランティアスタッフ1人)
準備・片付け:全スタッフ
受付:(澤岻健/ボランティアスタッフ)
上映:(海燕社同人)
司会:(城間あさみ)
〈後援〉沖縄県/那覇市
【お客様の感想(アンケートより)】
与那国島の風を感じることができました。
当たり前のようにある魚も、誰かが命懸けで
取ってきてくれていること、改めて感謝することができました。
おじいがカジキと戦う様子をハラハラして見ていました。
漁から帰ってきたおじいの、なんとチャーミングなこと! 30代女性
サバニでのカジキ漁。
とても迫力がありました。
1990年の与那国島の暮らしも丁寧に描かれ、
見られてよかったなと思います。 30代女性
こうした記録映画の上映機会を増やして頂けると嬉しいです。 40代女性
今日もすばらしい映画もありがとうございます。
島民みんなでいきている感じがとてもいいなぁーと感じます。 40代女性
ヘミングウェイの老人と海が好きで
与那国で撮影された同タイトルの映画があると知り、
見たいな見たいなと楽しみにしていました。
サバニでカジキを釣る。
実際に映像で観ると、
ワイヤー使っていなかったり、
荒天の中、船を出て、ハラハラするシーンが
結構たくさんありました。
(「じいちゃん」にとっては日常かも知れませんが・・・)
与那国の海は波が高いイメージがあって、その海の中を
モリ1本でカジキをとるのはすごいなと思いました。
最後のろうどくもよかったです。 40代女性
ずっーと見たいと思っていた作品でした。
ラストでおじぃが思わず踊りだすシーンがとても良かったです。
サバニで漁に出る時、
おじぃがサバニにこすりつけていたのは、おしおですか?
漁の安全祈願したのでしょうか? 50代女性
良い映画を見せて頂きありがとうございました。
古い町並みが映り込んだ映画を観たかったのですが、
想定外に良い映画でよかったです。
この映画はもっと世に知られるべき傑作です。 50代男性
今となっては‶基地の島″になってしまった与那国島の
かつての風景を見ることが出来て、本当によかったと思います。
おじいだけでなく、与那国島の人々の日常の暮らしの中で見せる
自然な表情がとてもよかった。‶自然″の流れに逆らって生きる
我々人間の作り出した(都会の)社会で、
失ってしまったものが、そこにある気がしました。
30年以上たって、もうそこにはないかも知れない人々の姿に
懐かしさとうらやましさを感じずにはいられませんでした。
〈リクエスト〉できればアイヌの記録映像を見たいです。 50代女性
釣れてよかった!
海人は、どんな最後になるのだろうか。
34年前のヨナグニ、今はどうなんだろうか。 50代女性
ずいぶん前に観たはずなのですが、
記憶があやしいということもあって
まったく新鮮な気持ちで観ることができました。
与那国はここ数年大きな変化に見舞われているかと思います。
小さな共同体がどうなっているか、心配です。 50代男性
生きている。 50代女性
解説じみたナレーションがなく、
淡々と映像のみが続くという構成がとてもよいと思いました。 50代男性
ちびらーさん(すばらしい)!
先日、三上智恵さんのドキュメンタリー「戦雲 いくさふむ」を鑑賞したら、
作品中に与那国島の川田さんという元気な海人おじぃが登場していました。
三上さんによると「老人と海」が大好きで、
自分の作品でも海人おじぃを取り上げたかったとのお話でした。
終始、寡黙な糸数のおじぃとはだいぶ雰囲気は違いますけどね、と笑ってました。
「老人と海」は未見だったので
グッドタイミングということで今回の上映に駆けつけました。
そしたら、漁が不調で落ち込んでいる糸数おじぃに、
自分がとった魚をプレゼントして励ましている川田さんの若かりし頃の姿が!
あぁ、島の人々の姿がドキュメンタリー映画を通して引き継がれていると、感動しました。
「戦雲」は、島の軍事基地化にゆれる島人の現状を描いていて、とても胸がつまりました。
海や島の神に深い敬意をこめた、島の人々の誇り高い暮らしがいつまでも続くことを心から願います。
上映会、いっぺーにふぇーでーびたん(本当にありがとうございました)。
自社の作品のみならず、沖縄との関連も深い素敵なドキュメンタリー作品の
上映企画を続けている海燕社さんに心より感謝申し上げます。
10周年、かりーさびらー(おめでとうございます)! 50代男性
本気で生きることの大切さ感じました。 50代女性
与那国の海を舞台に
漁師たちのありのままの日常を
たんたんと映し、それが本当に心を打つ素晴らしい作品でした。
島の人々が祭りや生活を大切にしている様子が伝わりました。 50代男性
以前にこの作品を観て、与那国島に行ってみたいと思った私です。
糸数オジーの格好いいこと・・・カジキ釣りは命がけなんですね。
長らく獲れない時には眠ることもできない、必死に生きている、
すごくたくましく勇ましいと感じました。
機会があり、与那国島を訪れることができましたが、
今回、懐かしみながら観ることができました。
とても良かったです。ありがとうございました。 50代女性
全編ノーナレーションであることに
途中まで全く気がつかなかった(というか、気にならなかった)というくらい、
映像の説得力のすごいこと!引き込まれて観ていました。
おじいもおばあも背すじがピンとして、
ハーリーのチキにはビシッとドゥタティを着こなして、
めちゃくちゃかっこよかったです。
1980年代、私は那覇でテクノやロックやダンスミュージックを聴いて
都会に行きたい高校生でした。
その頃の与那国久部良を今観ることができて、
年を取った今だから感動しています。 50代女性
くる日もくる日も漁に出て、
釣れない場面は、こちらもつらくなりましたが、
カジキと格闘し、熟練の技で仕留めていく様はアッパレでした。
夜のうたげで、満面の笑みの糸数さん夫婦、
幸せな場面に心打たれました。 50代女性
私は与那国出身なので、
このチラシを見かけて見にくることを決めました。
この映画を観るのは三度ですが、
改めて当時のことを思い出し胸が熱くなりました。
映画のいいところは、そのままをずっと残してくれるところです。
糸数さんが大きなカジキと格闘するシーンに感動しました。
昔からこうやって人は自然とたたかってきたんですね。
上映してくれたことに感謝します。 50代女性
人のこさが同じ沖縄の人々とは思えなかった。
人間としてかっこいいと思った。
良い映画でした。
大人がいるところに子どもも一緒にいるのも
いいなーと思った。 50代女性
とてもいいドキュメンタリーでした。
映像の色もザラっとした質感で、すごく引き込まれました。 50代男性
偶然にも私が初めて1人で
沖縄に暮らしていた年のものでした。
なつかして、涙が出ました。
自分が好きだった沖縄がすべてありました。 50代女性
久々のドキュメンタリー映画を観ました。
すごい人がいたんだと思う。
懐かしさと憧れとで胸がいっぱいになりました。 60代女性
すばらしかったです!
漁師さんの‶力″を感じました!
与那国島へ行ってみたいです。 60代女性
1990年、3カ月ほど与那国島の農家に住み込んで
キビ倒しのアルバイトをしました。
海に出る機会はなかったので、
全く知らない与那国島の一面とはいえ
お世話になった島の方々をあざやかに思い出します。
貴重な機会を作っていただき、ありがとうございました。 60代男性
‶老人と海″すばらしい映像でした。
人間、海、カジキ、生命の原点をみる思いでした。
与那国島に生きる人たちの、生活の中に、自分が
幼い頃に見た風景を幾つも発見し、とてもなつかしい気持ちになりました。
私たちがこの大切なものを忘れないようにするために、
この映像を保存し、多くの人にみてもらい、伝えてもらいたいです。 60代女性
映像がほんとに素晴らしかった。
「老人」がとにかく格好良かった。
全てが美しかった。
モノクロームにみえる海や雲も、
ハーリーの躍動感も、みずみずしくて。
ラストの与那国の歌も、老人の舞(もうい?)も心を打つ。
何度でも観たい映画だと思う。 60代女性
楽しい時間ありがとうございました。
大変なお仕事で感動。
自然との戦いになるので、
魚がつれる日もあれば、ない時もある。
みんな笑顔で、がんばっている。
おふろでタワシでゴシゴシ、なつかしく思えた。
与那国もいい所ですね。一度は行ってみたいです。
ありがとうございました。 60代女性
40年前の20代前半の2年間を、与那国に過ごしました。
自衛隊基地の建設、住民の分断、住民の減少で、
伝統的な行事、日常の生活が変化させられていくことをさびしく思います。
サバニでのカジキ漁、貴重な映像と思います。 60代男性
とてもいい映画だった。
会場から、驚きの声が上がったり、
ホーッとため息が出たり、笑い顔、歓声が聞こえ、
沖縄の人にとって、大切な映画だと思った。
2カ月程前、「戦雲」という映画を観た。
テーマは全く違うものだが、現在の与那国の老カジキ漁師が出て来た。
ハーリーの顔ぶれが全く変わってしまったことを思うと
記録映画としてとても大切な作品であると思った。 60代女性
とても大切な事を思い出させて頂きました。
素晴らしい映像を観せて頂いた事に心より感謝申し上げます。
人間らしさとは、本当の豊かさとは、何かを、考えさせられました。
自然とともに生きる、丁寧にくらす、
自分の今を見つめ直してみたいです。
本当にありがとうございました。 60代女性
上映に感謝します。
かなり以前に東京の映画館で見て感動しました。
もう一度、観てみたい映画でした。
与那国には中々行けません。
ステキな島の風景がここ数年間の自衛隊の駐屯地拡大で
どの様に変わってしまったのか、とても気にかかります。 70代女性
30年以上前、老人と海、TVニュース?で見た。
それ以来、再上映を楽しみにしていた。
サバニによるカジキ漁はとても危険である。
釣り糸に巻かれるなどで命を落とす方もいる。
糸数さんも、漁の中で無くなっている。
でも、それが漁師の姿かも。
与那国の美しい自然と人々の生活を思うと
軍事基地化が進行することをとても残念(?)危惧している。 70代男性
ヘミングウェイの老人と海の本を読んだ事を
ペルーに居る友人へ話したら、
何でも、其のモデルはペルー人との事でした。
本映画の最後の場面は、少しヒヤヒヤしましたが
ありがとうございました。 70代男性
与那国島の貴重な生活や祭がわかるドキュメンタリーであった。
最後のカジキと老人の格闘は迫力がありよかったです。 70代男性
すばらしい。
与那国島のみなさんの楽しそうに生活してる
様子を記録して頂きありがとうございます。
今、与那国島はミサイルや戦車等が公道を通っている様です。
すばらしい自然、豊かな島、残したいですね。 70代女性
小さな船での漁はハラハラドキドキでした。
島の皆さんは明るく、とても幸せそうです。
じいさんは、品の良い方ですね。 70代女性
なつかしかったです。
60年も前、四国で父親も漁師でした。
あのポンポンという船にのせてもらったこと思い出しました。
失礼ながら海燕社を知りませんでした。
5月6月は、本土に行っていたので映画会にも気づきませんでした。
これからもがんばって下さい。見に来たいと思います。 70代女性
ありがとうございます。
シンプルに生きること、とても、胸があつくなります。
子供達が生き生きと楽しく大人と過ごしている姿はとても感動です。
私達大人は子供達に生きる力をしっかりみせることができるのでしょうか。
今こんな人間教育を創りあげられたらと思います。
もう、こんなことは夢なのか。 70代
すばらしい映画でした。
海ん人の生き方に無知でした。
魚がつれた一瞬が忘れられない一時でした。
村中で喜び、苦しみを共有して生活している
今の世代の海ん人もそうであって欲しい。 70代女性
孫たちの住む与那国へ行った。
ちょうどカジキ釣り大会だった。
今年は、シメ切ぎりぎりに大物が釣れたと言って大にぎわいだった。
優勝者の話を直接聞くことが出来た。
その時、あっ「老人と海だ」と思った。
その上映会があるとチラシに見つけるやすぐ予約した。
「人生 趣味を持たないとな」と
優勝者の声が日々リフレインしている。
よおーく見せてもらいました。ありがとう。
小さな舟で漁をし、生活をし、人生を楽しむ。
無駄がないですねぇ。 70代女性
「老人と海」観ることができてほんとに良かった。
お茶を飲むオジーオバー、
両手で持ち上げて感謝の意のしぐさも素敵でした。
サバニの小さな船と大きなカジキ戦!
彼が海へ落ちてしまいそうで、
ハラハラが最後までずっとー(笑)
ハーリー戦のサバニの先頭に小さな男の子がなんともカッコよすぎ。
男、女、オジー、オバーの思いやる心、印象的、ステキでした。
(音楽 小室等ノテロップもビックリ) 70代女性
不漁続きの末、大きなカジキを釣ってあとの
ラストシーンで老人の笑顔と唄三線、カチャーシーと、
喜びと誇らしさがにじみ出て、思わず、私、涙(ナダ)グルグル…
心が洗われました。 70代女性
漁師、糸数さん!おめでとう! 70代男性
前日に「戦雲」の映画を観て、
今日の「老人の海」を観て、
与那国の情景が気になります。
基地の島になっている。
舟のエンジンの音が生きる力を感じて残ります。 70代男性
上映会をいつも楽しみにしております。
学ぶことの多い映画は素晴らしいです。
TVではお笑い番組や、食べる事も大事ですが
食べ過ぎて健康を害する事、クスリの話や
コマーシャル…いい事はありません。
いつも映画は人生に参考になります。
サバニは今もうないという事でありますが大変良かった。
漁師の心意気を感じました。
ありがとうございました。又、良い映画を期待! 80代男性
聞きとりずらい所が多々ありましたが、
時々聞こえた部分は思わずタイミングよく笑いをそそる部分が多かった。
子供たちが介入してくるところも微笑ましく昔の子供の頃の風景を思い出す。
また時々観客からの笑い声も、さもありなんというタイミングだった。
もう30年以上もたった。その時撮っておいてくれて、ありがとうと云いたい。 80代男性
前にも見たのですが…良いので、
又見ようと思いました。
オジーイ、良くガンバッタです。 80代男性
与那国の海にサバニで大カジキとの格闘!
以前も観たのですが、又、観たい!
その時の記念ボトルが飾ってあります。
与那国の素晴らしい海や景色に
今は自衛隊が戦争の準備をしている。
馬が歩く道路に戦車が走っている!
この国は何をしようとしているのか! 80代女性
〈7月会を振り返って〉
「海燕社の小さな映画会2024」7月会。
ご鑑賞の58名のお客様、ありがとうございました。
作品上映を快く了承して下さいました「シグロ」様、
ジャン・ユンカーマン監督、ありがとうございました。
会場「沖縄県立博物館美術館」様、ありがとうございました。
後援の「沖縄県」「那覇市」様、ありがとうございました。
宣伝にご協力下さいましたマスコミのみなさま、ありがとうございました。
SNSや口コミで宣伝下さいましたみなさま、ありがとうございました。
みなさまに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
海燕社の小さな映画会は海燕社が「観たい」「観て欲しい」映画を
一緒に観ませんか、というゆるやかな気持ちで開催している映画会です。
劇場ではなかなか上映されない映像作品や旧作映画を上映しています。
映画の多様性、特にドキュメンタリーの幅広さを知ってもらいたいという気持ちがあります。
2024年の映画会は10年目を記念してご鑑賞者にオリジナル「栞」をプレゼントしています。
4月会は「獅子」5月会は「木」…上映作品に合わせてテーマを決めてデザインしています。
記念品を「栞」にしたのは、私が映画を観る前や観た後に原作本や関連する本を読みたくなるからです。
映画会の思い出とともに読書の時に「栞」を愛用して頂けたらうれしいです。
「海燕社の小さな映画会2024」の7月会は、
『老人と海』(ディレクターズカット版)を上映しました。
一度も与那国に行ってことのない私ですが、懐かしさとその美しさに今も浸っています。
なつかしい沖縄に久しぶりに再会したようで胸を打たれました。
「人と自然が共に生きる暮らし」沖縄の原風景につながっているように思えました。
ナレーションを全く入れず、テレップもほとんどない。
映像制作の理想の形です。その心地よさと美しさにも浸っていました。
舟の手入れ、仕掛けづくり、舟の上の作業、黙々とただ黙々と。祈りのようで美しい。
おじいさんとおばあさんのしずかな暮らしが、祈りのようで美しい。
大海原で一人カジキを追い最後に釣り上げた糸数さんが、祈りのようで美しい。
このように生きられたらと思いました。生き方としても私の理想の形です。
与那国島は今、どうなっているのでしょうか。
与那国島のみなさんの、糸数さんご夫婦の、「祈りのような美しいくらし」を想っています。
与那国島に、戦雲が、浮かんでいるのなら、消えて欲しいです。
鑑賞の機会を逸していた三上智恵監督『戦雲』を観たいと思います。
映像作品は完成後が大事だと思っています。
製作者としては観てもらうこと、観客としては観ること、
その二つを映画に贈りたいです。
「海燕社の小さな映画会」はその一役になって欲しいと願っています。
アンケートの提出して下さった58名様に感謝申し上げます。
アンケートのご協力ありがとうございました。
感想を書いて下さったのは53名様。感想ブログ掲載不可は4名様。
49名のお客様の感想を上記で紹介させて頂きました。
ブログでのお客様全員の感想を紹介する活動を続けています。
海燕社のスタッフだけで読むには惜しい内容の感想ばかりだからです。
映画会に来て下さった皆様と感想を共有したい、
映画製作者のみなさまにお客様の感想を伝えたい、
映画会に来れなかったみなさまに作品について伝えたい、
という思いで感想をブログで紹介しています。
これからも続けます。ご協力をよろしくお願いします。
城間あさみ
【2024.7.21(日)/沖縄県立博物館・美術館3階講堂
13:15受付開場/14:05上映開始/15:30終了】
鑑賞料:1200円(予約一般)/1500円(当日一般)
※高校生以下無料券(予約先着10名様まで)
〈上映作品〉
『老人と海 』※ディレクターズカット版
(2010年/シグロ製作/ジャン・ユンカーマン監督/98分)
〈入場まで〉
1.受付:①予約の方-鑑賞券(1,200円)/当日の方-当日券(1,500円)
②資料配布
2.手指アルコール消毒(各自:劇場入口設置)
3.入場着席:自由席
※配布資料
ラインナップ1枚、7月会チラシ1枚、
アンケート用紙、案内希望カード、下敷き、クリアファイル、クリップ鉛筆
※ご来場者プレゼント
10年目記念オリジナル栞1枚(7月会デザインテーマ「老人と海」)
<プログラム>
1.開会
2.主催挨拶(城間あさみ)
3.『老人と海』※ディレクターズカット版
(2010年/シグロ製作/ジャン・ユンカーマン監督/98分)
5.閉会(アンケート記入)
<スタッフ> 4人(海燕社2人、同人1人、ボランティアスタッフ1人)
準備・片付け:全スタッフ
受付:(澤岻健/ボランティアスタッフ)
上映:(海燕社同人)
司会:(城間あさみ)
〈後援〉沖縄県/那覇市
【お客様の感想(アンケートより)】
与那国島の風を感じることができました。
当たり前のようにある魚も、誰かが命懸けで
取ってきてくれていること、改めて感謝することができました。
おじいがカジキと戦う様子をハラハラして見ていました。
漁から帰ってきたおじいの、なんとチャーミングなこと! 30代女性
サバニでのカジキ漁。
とても迫力がありました。
1990年の与那国島の暮らしも丁寧に描かれ、
見られてよかったなと思います。 30代女性
こうした記録映画の上映機会を増やして頂けると嬉しいです。 40代女性
今日もすばらしい映画もありがとうございます。
島民みんなでいきている感じがとてもいいなぁーと感じます。 40代女性
ヘミングウェイの老人と海が好きで
与那国で撮影された同タイトルの映画があると知り、
見たいな見たいなと楽しみにしていました。
サバニでカジキを釣る。
実際に映像で観ると、
ワイヤー使っていなかったり、
荒天の中、船を出て、ハラハラするシーンが
結構たくさんありました。
(「じいちゃん」にとっては日常かも知れませんが・・・)
与那国の海は波が高いイメージがあって、その海の中を
モリ1本でカジキをとるのはすごいなと思いました。
最後のろうどくもよかったです。 40代女性
ずっーと見たいと思っていた作品でした。
ラストでおじぃが思わず踊りだすシーンがとても良かったです。
サバニで漁に出る時、
おじぃがサバニにこすりつけていたのは、おしおですか?
漁の安全祈願したのでしょうか? 50代女性
良い映画を見せて頂きありがとうございました。
古い町並みが映り込んだ映画を観たかったのですが、
想定外に良い映画でよかったです。
この映画はもっと世に知られるべき傑作です。 50代男性
今となっては‶基地の島″になってしまった与那国島の
かつての風景を見ることが出来て、本当によかったと思います。
おじいだけでなく、与那国島の人々の日常の暮らしの中で見せる
自然な表情がとてもよかった。‶自然″の流れに逆らって生きる
我々人間の作り出した(都会の)社会で、
失ってしまったものが、そこにある気がしました。
30年以上たって、もうそこにはないかも知れない人々の姿に
懐かしさとうらやましさを感じずにはいられませんでした。
〈リクエスト〉できればアイヌの記録映像を見たいです。 50代女性
釣れてよかった!
海人は、どんな最後になるのだろうか。
34年前のヨナグニ、今はどうなんだろうか。 50代女性
ずいぶん前に観たはずなのですが、
記憶があやしいということもあって
まったく新鮮な気持ちで観ることができました。
与那国はここ数年大きな変化に見舞われているかと思います。
小さな共同体がどうなっているか、心配です。 50代男性
生きている。 50代女性
解説じみたナレーションがなく、
淡々と映像のみが続くという構成がとてもよいと思いました。 50代男性
ちびらーさん(すばらしい)!
先日、三上智恵さんのドキュメンタリー「戦雲 いくさふむ」を鑑賞したら、
作品中に与那国島の川田さんという元気な海人おじぃが登場していました。
三上さんによると「老人と海」が大好きで、
自分の作品でも海人おじぃを取り上げたかったとのお話でした。
終始、寡黙な糸数のおじぃとはだいぶ雰囲気は違いますけどね、と笑ってました。
「老人と海」は未見だったので
グッドタイミングということで今回の上映に駆けつけました。
そしたら、漁が不調で落ち込んでいる糸数おじぃに、
自分がとった魚をプレゼントして励ましている川田さんの若かりし頃の姿が!
あぁ、島の人々の姿がドキュメンタリー映画を通して引き継がれていると、感動しました。
「戦雲」は、島の軍事基地化にゆれる島人の現状を描いていて、とても胸がつまりました。
海や島の神に深い敬意をこめた、島の人々の誇り高い暮らしがいつまでも続くことを心から願います。
上映会、いっぺーにふぇーでーびたん(本当にありがとうございました)。
自社の作品のみならず、沖縄との関連も深い素敵なドキュメンタリー作品の
上映企画を続けている海燕社さんに心より感謝申し上げます。
10周年、かりーさびらー(おめでとうございます)! 50代男性
本気で生きることの大切さ感じました。 50代女性
与那国の海を舞台に
漁師たちのありのままの日常を
たんたんと映し、それが本当に心を打つ素晴らしい作品でした。
島の人々が祭りや生活を大切にしている様子が伝わりました。 50代男性
以前にこの作品を観て、与那国島に行ってみたいと思った私です。
糸数オジーの格好いいこと・・・カジキ釣りは命がけなんですね。
長らく獲れない時には眠ることもできない、必死に生きている、
すごくたくましく勇ましいと感じました。
機会があり、与那国島を訪れることができましたが、
今回、懐かしみながら観ることができました。
とても良かったです。ありがとうございました。 50代女性
全編ノーナレーションであることに
途中まで全く気がつかなかった(というか、気にならなかった)というくらい、
映像の説得力のすごいこと!引き込まれて観ていました。
おじいもおばあも背すじがピンとして、
ハーリーのチキにはビシッとドゥタティを着こなして、
めちゃくちゃかっこよかったです。
1980年代、私は那覇でテクノやロックやダンスミュージックを聴いて
都会に行きたい高校生でした。
その頃の与那国久部良を今観ることができて、
年を取った今だから感動しています。 50代女性
くる日もくる日も漁に出て、
釣れない場面は、こちらもつらくなりましたが、
カジキと格闘し、熟練の技で仕留めていく様はアッパレでした。
夜のうたげで、満面の笑みの糸数さん夫婦、
幸せな場面に心打たれました。 50代女性
私は与那国出身なので、
このチラシを見かけて見にくることを決めました。
この映画を観るのは三度ですが、
改めて当時のことを思い出し胸が熱くなりました。
映画のいいところは、そのままをずっと残してくれるところです。
糸数さんが大きなカジキと格闘するシーンに感動しました。
昔からこうやって人は自然とたたかってきたんですね。
上映してくれたことに感謝します。 50代女性
人のこさが同じ沖縄の人々とは思えなかった。
人間としてかっこいいと思った。
良い映画でした。
大人がいるところに子どもも一緒にいるのも
いいなーと思った。 50代女性
とてもいいドキュメンタリーでした。
映像の色もザラっとした質感で、すごく引き込まれました。 50代男性
偶然にも私が初めて1人で
沖縄に暮らしていた年のものでした。
なつかして、涙が出ました。
自分が好きだった沖縄がすべてありました。 50代女性
久々のドキュメンタリー映画を観ました。
すごい人がいたんだと思う。
懐かしさと憧れとで胸がいっぱいになりました。 60代女性
すばらしかったです!
漁師さんの‶力″を感じました!
与那国島へ行ってみたいです。 60代女性
1990年、3カ月ほど与那国島の農家に住み込んで
キビ倒しのアルバイトをしました。
海に出る機会はなかったので、
全く知らない与那国島の一面とはいえ
お世話になった島の方々をあざやかに思い出します。
貴重な機会を作っていただき、ありがとうございました。 60代男性
‶老人と海″すばらしい映像でした。
人間、海、カジキ、生命の原点をみる思いでした。
与那国島に生きる人たちの、生活の中に、自分が
幼い頃に見た風景を幾つも発見し、とてもなつかしい気持ちになりました。
私たちがこの大切なものを忘れないようにするために、
この映像を保存し、多くの人にみてもらい、伝えてもらいたいです。 60代女性
映像がほんとに素晴らしかった。
「老人」がとにかく格好良かった。
全てが美しかった。
モノクロームにみえる海や雲も、
ハーリーの躍動感も、みずみずしくて。
ラストの与那国の歌も、老人の舞(もうい?)も心を打つ。
何度でも観たい映画だと思う。 60代女性
楽しい時間ありがとうございました。
大変なお仕事で感動。
自然との戦いになるので、
魚がつれる日もあれば、ない時もある。
みんな笑顔で、がんばっている。
おふろでタワシでゴシゴシ、なつかしく思えた。
与那国もいい所ですね。一度は行ってみたいです。
ありがとうございました。 60代女性
40年前の20代前半の2年間を、与那国に過ごしました。
自衛隊基地の建設、住民の分断、住民の減少で、
伝統的な行事、日常の生活が変化させられていくことをさびしく思います。
サバニでのカジキ漁、貴重な映像と思います。 60代男性
とてもいい映画だった。
会場から、驚きの声が上がったり、
ホーッとため息が出たり、笑い顔、歓声が聞こえ、
沖縄の人にとって、大切な映画だと思った。
2カ月程前、「戦雲」という映画を観た。
テーマは全く違うものだが、現在の与那国の老カジキ漁師が出て来た。
ハーリーの顔ぶれが全く変わってしまったことを思うと
記録映画としてとても大切な作品であると思った。 60代女性
とても大切な事を思い出させて頂きました。
素晴らしい映像を観せて頂いた事に心より感謝申し上げます。
人間らしさとは、本当の豊かさとは、何かを、考えさせられました。
自然とともに生きる、丁寧にくらす、
自分の今を見つめ直してみたいです。
本当にありがとうございました。 60代女性
上映に感謝します。
かなり以前に東京の映画館で見て感動しました。
もう一度、観てみたい映画でした。
与那国には中々行けません。
ステキな島の風景がここ数年間の自衛隊の駐屯地拡大で
どの様に変わってしまったのか、とても気にかかります。 70代女性
30年以上前、老人と海、TVニュース?で見た。
それ以来、再上映を楽しみにしていた。
サバニによるカジキ漁はとても危険である。
釣り糸に巻かれるなどで命を落とす方もいる。
糸数さんも、漁の中で無くなっている。
でも、それが漁師の姿かも。
与那国の美しい自然と人々の生活を思うと
軍事基地化が進行することをとても残念(?)危惧している。 70代男性
ヘミングウェイの老人と海の本を読んだ事を
ペルーに居る友人へ話したら、
何でも、其のモデルはペルー人との事でした。
本映画の最後の場面は、少しヒヤヒヤしましたが
ありがとうございました。 70代男性
与那国島の貴重な生活や祭がわかるドキュメンタリーであった。
最後のカジキと老人の格闘は迫力がありよかったです。 70代男性
すばらしい。
与那国島のみなさんの楽しそうに生活してる
様子を記録して頂きありがとうございます。
今、与那国島はミサイルや戦車等が公道を通っている様です。
すばらしい自然、豊かな島、残したいですね。 70代女性
小さな船での漁はハラハラドキドキでした。
島の皆さんは明るく、とても幸せそうです。
じいさんは、品の良い方ですね。 70代女性
なつかしかったです。
60年も前、四国で父親も漁師でした。
あのポンポンという船にのせてもらったこと思い出しました。
失礼ながら海燕社を知りませんでした。
5月6月は、本土に行っていたので映画会にも気づきませんでした。
これからもがんばって下さい。見に来たいと思います。 70代女性
ありがとうございます。
シンプルに生きること、とても、胸があつくなります。
子供達が生き生きと楽しく大人と過ごしている姿はとても感動です。
私達大人は子供達に生きる力をしっかりみせることができるのでしょうか。
今こんな人間教育を創りあげられたらと思います。
もう、こんなことは夢なのか。 70代
すばらしい映画でした。
海ん人の生き方に無知でした。
魚がつれた一瞬が忘れられない一時でした。
村中で喜び、苦しみを共有して生活している
今の世代の海ん人もそうであって欲しい。 70代女性
孫たちの住む与那国へ行った。
ちょうどカジキ釣り大会だった。
今年は、シメ切ぎりぎりに大物が釣れたと言って大にぎわいだった。
優勝者の話を直接聞くことが出来た。
その時、あっ「老人と海だ」と思った。
その上映会があるとチラシに見つけるやすぐ予約した。
「人生 趣味を持たないとな」と
優勝者の声が日々リフレインしている。
よおーく見せてもらいました。ありがとう。
小さな舟で漁をし、生活をし、人生を楽しむ。
無駄がないですねぇ。 70代女性
「老人と海」観ることができてほんとに良かった。
お茶を飲むオジーオバー、
両手で持ち上げて感謝の意のしぐさも素敵でした。
サバニの小さな船と大きなカジキ戦!
彼が海へ落ちてしまいそうで、
ハラハラが最後までずっとー(笑)
ハーリー戦のサバニの先頭に小さな男の子がなんともカッコよすぎ。
男、女、オジー、オバーの思いやる心、印象的、ステキでした。
(音楽 小室等ノテロップもビックリ) 70代女性
不漁続きの末、大きなカジキを釣ってあとの
ラストシーンで老人の笑顔と唄三線、カチャーシーと、
喜びと誇らしさがにじみ出て、思わず、私、涙(ナダ)グルグル…
心が洗われました。 70代女性
漁師、糸数さん!おめでとう! 70代男性
前日に「戦雲」の映画を観て、
今日の「老人の海」を観て、
与那国の情景が気になります。
基地の島になっている。
舟のエンジンの音が生きる力を感じて残ります。 70代男性
上映会をいつも楽しみにしております。
学ぶことの多い映画は素晴らしいです。
TVではお笑い番組や、食べる事も大事ですが
食べ過ぎて健康を害する事、クスリの話や
コマーシャル…いい事はありません。
いつも映画は人生に参考になります。
サバニは今もうないという事でありますが大変良かった。
漁師の心意気を感じました。
ありがとうございました。又、良い映画を期待! 80代男性
聞きとりずらい所が多々ありましたが、
時々聞こえた部分は思わずタイミングよく笑いをそそる部分が多かった。
子供たちが介入してくるところも微笑ましく昔の子供の頃の風景を思い出す。
また時々観客からの笑い声も、さもありなんというタイミングだった。
もう30年以上もたった。その時撮っておいてくれて、ありがとうと云いたい。 80代男性
前にも見たのですが…良いので、
又見ようと思いました。
オジーイ、良くガンバッタです。 80代男性
与那国の海にサバニで大カジキとの格闘!
以前も観たのですが、又、観たい!
その時の記念ボトルが飾ってあります。
与那国の素晴らしい海や景色に
今は自衛隊が戦争の準備をしている。
馬が歩く道路に戦車が走っている!
この国は何をしようとしているのか! 80代女性
〈7月会を振り返って〉
「海燕社の小さな映画会2024」7月会。
ご鑑賞の58名のお客様、ありがとうございました。
作品上映を快く了承して下さいました「シグロ」様、
ジャン・ユンカーマン監督、ありがとうございました。
会場「沖縄県立博物館美術館」様、ありがとうございました。
後援の「沖縄県」「那覇市」様、ありがとうございました。
宣伝にご協力下さいましたマスコミのみなさま、ありがとうございました。
SNSや口コミで宣伝下さいましたみなさま、ありがとうございました。
みなさまに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
海燕社の小さな映画会は海燕社が「観たい」「観て欲しい」映画を
一緒に観ませんか、というゆるやかな気持ちで開催している映画会です。
劇場ではなかなか上映されない映像作品や旧作映画を上映しています。
映画の多様性、特にドキュメンタリーの幅広さを知ってもらいたいという気持ちがあります。
2024年の映画会は10年目を記念してご鑑賞者にオリジナル「栞」をプレゼントしています。
4月会は「獅子」5月会は「木」…上映作品に合わせてテーマを決めてデザインしています。
記念品を「栞」にしたのは、私が映画を観る前や観た後に原作本や関連する本を読みたくなるからです。
映画会の思い出とともに読書の時に「栞」を愛用して頂けたらうれしいです。
「海燕社の小さな映画会2024」の7月会は、
『老人と海』(ディレクターズカット版)を上映しました。
一度も与那国に行ってことのない私ですが、懐かしさとその美しさに今も浸っています。
なつかしい沖縄に久しぶりに再会したようで胸を打たれました。
「人と自然が共に生きる暮らし」沖縄の原風景につながっているように思えました。
ナレーションを全く入れず、テレップもほとんどない。
映像制作の理想の形です。その心地よさと美しさにも浸っていました。
舟の手入れ、仕掛けづくり、舟の上の作業、黙々とただ黙々と。祈りのようで美しい。
おじいさんとおばあさんのしずかな暮らしが、祈りのようで美しい。
大海原で一人カジキを追い最後に釣り上げた糸数さんが、祈りのようで美しい。
このように生きられたらと思いました。生き方としても私の理想の形です。
与那国島は今、どうなっているのでしょうか。
与那国島のみなさんの、糸数さんご夫婦の、「祈りのような美しいくらし」を想っています。
与那国島に、戦雲が、浮かんでいるのなら、消えて欲しいです。
鑑賞の機会を逸していた三上智恵監督『戦雲』を観たいと思います。
映像作品は完成後が大事だと思っています。
製作者としては観てもらうこと、観客としては観ること、
その二つを映画に贈りたいです。
「海燕社の小さな映画会」はその一役になって欲しいと願っています。
アンケートの提出して下さった58名様に感謝申し上げます。
アンケートのご協力ありがとうございました。
感想を書いて下さったのは53名様。感想ブログ掲載不可は4名様。
49名のお客様の感想を上記で紹介させて頂きました。
ブログでのお客様全員の感想を紹介する活動を続けています。
海燕社のスタッフだけで読むには惜しい内容の感想ばかりだからです。
映画会に来て下さった皆様と感想を共有したい、
映画製作者のみなさまにお客様の感想を伝えたい、
映画会に来れなかったみなさまに作品について伝えたい、
という思いで感想をブログで紹介しています。
これからも続けます。ご協力をよろしくお願いします。
城間あさみ
Posted by カイエンシャ at
17:44
│海燕社の小さな映画会
2024年07月20日
「海燕社の小さな映画会2024 6月会」『はだしのゲンが伝えたいこと』『ふじ学徒隊』
海燕社の小さな映画会2024 6月会
【2024.6.22(日)/沖縄県立博物館・美術館3階講堂
13:15受付開場/14:05上映開始/15:30終了】
鑑賞料:1200円(予約一般)/1500円(当日一般)
※高校生以下無料券(予約先着10名様まで)
〈上映作品〉
『はだしのゲンが伝えたいこと 』
(2011年製作/石田優子監督/シグロ・トモコーポレーション/32分)
『ふじ学徒隊 』
(2012年製作/野村岳也監督/海燕社/48分)
〈入場まで〉
1.受付:①予約の方-鑑賞券(1,200円)/当日の方-当日券(1,500円)
②資料配布
2.手指アルコール消毒(各自:劇場入口設置)
3.入場着席:自由席
※配布資料
ラインナップ1枚、6月会チラシ1枚、
アンケート用紙、案内希望カード、下敷き、クリアファイル、クリップ鉛筆
※ご来場者プレゼント
10年目記念オリジナル栞1枚(6月会デザインテーマ「命どぅ宝」)
<プログラム>
1.開会
2.主催挨拶(城間あさみ)
3.『はだしのゲンが伝えたいこと 』
(2011年製作/石田優子監督/シグロ・トモコーポレーション/30分)
4.『ふじ学徒隊 』
(2012年製作/野村岳也監督/海燕社/48分)
5.閉会(アンケート記入)
<スタッフ> 4人(海燕社2人、同人1人、ボランティアスタッフ1人)
準備・片付け:全スタッフ
受付:(澤岻健/ボランティアスタッフ)
上映:(海燕社同人)
司会:(城間あさみ)
〈後援〉沖縄県/那覇市
【お客様の感想(アンケートより)】
戦前、戦中を知っている人がいなくなってる今、
私たち若ものが平和を作るための行動を
やめてはならないと改めて感じました。
‶二度と自分と同じ思いをしてほしくない”という
被爆者や学徒隊の方々の思いを忘れずに
これからも平和な世界になるように学び続けたいです。
ありがとうございました。また来ます。 10代女性
戦争体験を私たち若い世代は忘れてはならず、
今後も伝えていかなければと強く感じました。
私の祖父母も沖縄戦体験者ですが、
若い人は戦争を知らない人も多くとても悲しくなります。
実体験を聞く機会はあまりないので、
このような映画を通して考えることができて良かったです。 20代女性
私たちがなぜ戦争に反対するのか、
証言を直接きくことができなくなる今だからこそ、
その必要性を強く感じます。
私も広島出身で被爆者の話をきいてきました。
今、大学で平和教育を学んでおり、
今日は友人と東京から学びに来ました。
戦争体験者の生きた証に学び続け
私にもできることをがんばりたいです。
共にたたかいましょう。 20代女性
戦争のおそろしさ、
そして、沖縄戦で何が起きたか、ということがわかった。
国のために死ぬことのバカバカしさを知ることができ、
これから後世のために、二度と戦争を起こしてはいけないと思った。
戦争経験者が少なくなる中、継承していかなければと思った。 20代男性
感想を書きたいですが、
今は言葉が見つかりません。申し訳ないです。
この感情をどう整理したらよいのか、
整理できるのか分かりませんが
今、この平和な世の中に生きていられることに感謝して
明日の慰霊の日を迎えたいと思います。 30代男性
大切にしたくてどうしていいのか。
分からないこと(命、大切な人達、人生、大人になること)が
本当に大切な自分のいのちなこと、生きていきたいと思いました。
本当にありがとうございました。 30代女性
慰霊の日の前日に
この2つの映画を見ることができてよかったです。
はだしのゲンに関しても子どもの頃からよく読んでいたので
それと頭の中でイメージしながらみれたので
頭に心にはいっってきやすかったです。
ふじ学徒隊の方の映画での証言も
「戦争は絶対いけない」と改めて思い平和のために
自分が自分なりにできることをしていかないとと思わされました。
戦争を生き抜いてきた1人1人に
命をつないでもらっていることにも感謝です。
戦後も苦しんでいるのはつらい・・・。 40代女性
「はだしのゲン」
小学生の頃、はだしのゲンを読んでいました。
その時の強烈な描写はずっと頭から離れず
戦争は何が理由でもやらない方がいいと思いました。
その時はなんで皮フをたらして人が歩いているのか
きちんとわかってなかったけど、今日はその答え合わせのようでした。
大人になってわかることがあるので、この機会に恵まれて感謝です。
「ふじ学徒隊」
ふじは知りませんでした。
戦争の中、生きることの大切さを伝えた隊長もいたんだと思いました。
戦争の記憶がその人の人生を変えてします罪深さを感じました。 40代女性
「ふじ学徒隊」とても見たかった映画でした。
戦争の記憶がうすれていく中、元学徒隊の言葉が
とても心にささりました。生きて私たちに当時のことを
伝えて下さりありがとうございました。
『はだしのゲンが伝えたいこと』
中沢さんのお話に引き込まれた。
彼の描いた原爆直後の広島の様子が強烈だった。 40代女性
はだしのゲン
作者の中沢さんの生々しい回想が
現実の重さを私たちの心に届きました。
戦争をしないことが大切だと改めて思いました。
ふじ学徒隊
その時、なにがあったのかを
つらい体験にもかかわらず話を聞くことができて
今生きている私たちは二度と戦争をしてはならないと思いました。 50代女性
ふじ学徒隊
無駄な犠牲者を出さなかったことは
指揮する側の考え方によるところ大きかったと感じました。
はだしのゲンが伝えたいこと
中沢さんの想いが、若い世代にも伝わって欲しいと思いました。 50代男性
今日の目的は「はだしのゲンが伝えたいこと」だったのと、
「ふじ学徒隊」は見た事があった為、用事で遅れても見れると思って
期待していたもののチラシの順番が入れ違っていて残念だった。
が、「ふじ学徒隊」の臨場感のある映像と語りに圧倒され、
2度目だったのであやふやだった面がクリアになり有意義な時間を過ごせた。
「はだしのゲンが伝えたいこと」は、
中沢さんのインタビュー部分しか見られなかったものの
あれだけの重い体験を客観的に明るく伝えていて、
拍子抜け感とそれだから作品作りを通した想像を越えた体験の超越が
あったんだろうなと強さを感じた。凄い力のある作品だった。 50代男性
はだしのゲンが伝えたいこと、
今まで聞いていた広島原爆の凄まじさ、事に、この映画で知りました。
マンガのタイトルは知っていましたが、読んだ事がなかったと思います。
もう一度見たいと改めて考えさせられました。
ふじ学徒隊、何度見ても涙が出て
戦争は絶対にしてはならないと考えさせられます。 50代女性
原爆や沖縄戦の映画は、正直、観ることがつらくて
上映会に足を運ぶことができませんでしたが、今日は参加しました。
思っていたより、つらくなかったのは、なぜだろうか?と考えました。
中沢啓治の笑顔、語る言葉の力強さ、
ふじ学徒隊の皆さんの明るい温かな人柄が
伝わってきたからでしょうか。
映画のつくり手側の意図がすばらしいなと感じました。
明日の慰霊の日を前に、ふたつの作品を観ることができてよかったです。 50代女性
今年も映画でハルちゃん達と会えました。
つらい体験を語ってくださりありがとうございますという気持ちでいっぱいです。
体験者が少なくなってきた今だからこそ、
この映画の存在は本当に大切だと思っています。
中沢啓治さんの体験を知ることができて良かったです。
はだしのゲンは小学生の頃から読んでいましたが
改めてまた読んでみたいと思いました。
今日は若い方も多数観にこられていたのが印象的でした。 50代女性
日本語だと麦はムギ(↓でギを下げる図付)というアクセントです。
日本語の文章を朗読するのは難しいのならやめた方がいいです。
今回の文章の中で重要なワードが沖縄訛りで読まれると興ざめです。 50代女性
ここでしか見ることのできない作品の上映、
ありがとうございます。今回2回目の来場ですが、
今後もここでしか見ることの出来ない作品の上映を楽しみにしています。 50代女性
二度と戦争をしてはいけない。何度も言いたい。
‶命どぅ宝”その一言につきる。
上映下さりありがとうございました。 50代女性
実は「はだしのゲン」は読んだことがなく
ぜひ読んでみたいと思った。
「ふじ学徒隊」は前にも観た。
何も知らず観たら親せきの方が証言者のひとりだった。
田崎芳子さんは父のいとこだと思う。
ただ、すごく近い親せきというわけでもないので
そうそう会う人でもなかった。
映画を観た時には父はもう亡くなっており、
田崎さんもそれから3年後ぐらいに亡くなった。
私の知らない10代後半を過ごしたのだと知った。 60代女性
ひめゆり部隊だけではない、女子学徒。 60代男性
ここ数年前、同窓生であった母と一緒に見て以来、
何度もみていますが、見るたびに、心に響き、
戦争の理不尽さ、悲しさ、怖さを感じ、涙があふれてきました。
世界では、自国主義を通し、戦争を起こす大国、
沖縄のように、ある日戦地となり、そこで平和に暮らしていた人々が
亡くなっていく様子が平然とニュースで流れ、
人間の怖さ、おろかさに、くやしい思いです。
私は今日、戦争に心を痛めただけで、
どこかに反戦の思いが届くといいのですが・・・ 60代女性
今年で3度目の映画『ふじ学徒隊』。
何度も観ることは、なかなかないこと。
見るたびに違う発見があり、
今年は、小池隊長のもとにいたから、
他の学徒たちとは違って、生きのびたのだなぁ、と思いました。
生きて、次の世代を育てるのだということばも心に残りました。
この場所で、映画をみることで、平和を考えて、
祈りの気持ちを思い出しています。ありがとうございます。
『はだしのゲン』の作者、中沢さんのお話、
とてもたても臨場感(どいうと違う気もするのです。本当に
その場にいたのですから。すみません。ことばがみつからず)があり、
人は、こんなにおそろしいものをつくり、人を死に至らしめ、
苦しめているのだと思いました。
オッペンハイマーの映画を思い出しつつ。 60代女性
ほんの一瞬で、地獄と化したげんばく広島の惨状・・・
国に命をささげ、お国のためと信じ、
あまりにも残酷な思いをしてしまった女生徒たち
両方とも見るのも聞くのもつらかったです。
ゼッタイに戦争はダメと改めて思いました。
他の学校の学徒隊に比べて、死者は少ないとは言え、
悲しくつらい思いをされたことと思います。
隊長さんの「絶対に死んではならない」という言葉は、本当に重い。
あの人間が狂ってしまうような状況の戦争の中で
生きることを訴えてくれた人がいたことに感謝したい。
今日はありがつございました。内地の人にも伝えたいです。 60代女性
今回、はじめて沖縄に来ました。
戦争の事は‶他人事‶のように思っていましたが、
見学している間に、身に沁みて感じる事ができ、
平和の大きさを、とても感じる事ができ、よかったです。
今回の映画も良かったです。ありがとうございました。
これからも頑張って続けて下さい。 60代女性
初めて参加させて頂きました。
貴重な映画を観ることが出来、感動しました。
指導者の考え方ひとつで、犠牲者が増えるということが、よく分かった。
今日、今から名古屋へ帰る合間で観ることができて本当に良かったと思います。 60代男性
はだしのゲンについて、
中沢氏の被爆の体験には言葉になりません。
”ノーモアヒロシマ、ノーモアナガサキ”は人類にとっての
守るべき最重要な宣言だと思った。 60代男性
戦争と言う言葉を目にしない日はないほど
世界のどこかで日常茶飯事になっている。
犠牲者はほとんどが将来ある子ども達だ。胸がいたい。
終わらせる日は来るのだろうか。その日を待ち望む。 70代女性
一生、頑張って生きる! 70代女性
生々しい証言を、全国、余すことなく、
上映して、戦争の悲惨さを伝えて欲しい。
戦争は、勝っても、負けても、地球を破滅に導きます。 70代
離島から久々に出掛けてきました。
東京で現役時代の頃「はだしのゲン」の事は知っていました。
案内で懐かしく思い出され是非観たいと思い来ました。
明日の慰霊祭は島でも開催しますが、折角、那覇まで来たついでに、
「平和の礎」に行ける機会にめぐり合わせました。
ゲンさん「中沢さん」が伝えたい事、ご本人の言葉で伝えてもらい
改めて新たに「平和」への願いを一緒にしたいと思います。
いつもご案内頂いてなかなかこれませんでしたが、今回はご縁ですね。
明日につなげていただきました。ありがとうございます。 70代女性
戦争を知らない子ども達のために
平和へのメッセージとして
これからも上映して下さい。
今日はありがとうございました。 70代女性
これまで何度か視聴したが、6.23を前に考えたくて見学した。
かつての同僚がふじ学徒であり、
前回、見学した時のことを再度思いながらー。
はだしのゲンは、散草地の小さなガマを思い出しながら見学。
教育は大事ですね。 70代男性
平和がいかに大事であるか痛感した。
はだしのゲン、マンガを20代、30代の頃に読んだが
作者の中沢さんの生々しい話をきき
あらためて悲惨な状況をしることができました。
忘れてしまわないようにこういう映像は、本当にもっともっと
多くの人に知らせていくべきだと思った。もったいないです。
最近、きな臭いニュースが日増しに強くなっているように思う。 70代女性
「ふじ学徒隊」これで2回目みました。
12年前によくぞ撮ってくれました。
毎年見たいと思います。
「はだしのゲン」マンガも昔みました。
上映みてあらためて、すばらしいマンガを残してくれたと思います。 70代女性
2つのドキュメンタリー映画は
戦争を知らない(私もその1人ですが・・・)
若い世代に6月23日慰霊の日の前までに
中学校、高校生にぜひ観てもらいたいです。
今日の会場には、年輩が目立ちました。
平和教育、平和の大切さは、特に次の時代を背負う若者から
熟年層の意識の中にインプットして欲しいと思います。
戦争をさせない為にも、
一人一人の平和維持の為の実践が大切と思います。
今日は参加できて良かったです。 70代女性
ありがとうございました。 70代男性
あさみさんと呼ばせて下さい。
私が存じ上げてから数年、よく頑張ってくださっています。
ありがとうございます。これからも頑張ってお願い致します。
そして、後継者も仲間もたくさん増えますように!
いつもありがとうございます。 70代女性
何度みても心いたむ。
子や孫達にも、伝えなければ、いけない。 70代女性
ふじ学徒隊は去年も見ましたが
今日も涙が止まりませんでした。
本当に戦争が憎いです。
はだしのゲンはマンガを見ていたのですが
本人の証言は忘れられません。 70代女性
はだしのゲンが伝えたいこと。
「子どもたち自らが平和を追求し続けてほしいということだ」
今は、大人になった私たちも平和を追求しなくてはならないと思った。行動しよう。
ふじ学徒隊。
「積徳高等女学校学徒隊」
そのとき母は、10.10空襲の前に、故郷に帰ったと聞いた。
母は、学生時代のことは、語らなかった。
母の元気なとき、詳しく聞けなかった。
もしかしたら母の写真があるか、記念誌を調べたい。 70代女性
慰霊の日の近く
理にかなった企画だと思います。
人間は過去を反省せねばいけないのに
同じ事をくり返しています。
おろかです。 70代
「はだしのゲンが伝えたいこと」
中沢さんの語りが胸をうちました。
平和の尊さ大切さをあらためて思いました。
「ふじ学徒隊」
青春時代をうばわれた学徒のみなさんが
どんなに無念だったkと思うと心が痛みます。
平和を願わずにはいられません。 70代女性
はだしのゲンの作家 中沢啓治さんの生き方や
今まで歩んで来た道を話して下さり
世界へ通じる作品を作り上げて来た
パワー、パッションを知ることが出来、良かったです。 70代女性
二度と戦争を起こさせてはならない。
その思いが更に強くなりました。
有難うございました。 70代男性
体験者の皆様の言葉に強い衝撃を受けました。
今、平和に暮らしている私達は幸せだと思います。 70代女性
はだしのゲンの作者の生の声が聞けて大変よかったです。
ふじ学徒隊。
この時期、機会があると毎回観ています。
今後も、特に若い人達に、多くの方々に、
観て頂きたいと強く思いました。
本日はありがとうございました。 70代女性
とてもよかったです。
なかなか見れない映画をみることが出来とてもよかった。
皆様のご活躍うれしく思います。 70代女性
戦争の悲惨な事を、改めて知りました。
家族が倒れた家の下敷きになっても救えなかった事
とても胸が痛くなりました。 70代男性
来年も見る。 70代男性
ふじ学徒隊の事を知らない人達が周囲に多く
マスコミに発信して欲しい。 70代女性
慰霊の日の前日にあたる日の今日の2本の上映
とても意義深いものでした。ゲンも、ふじも、改めて戦後の平和に
思い至る大事な証言映画でした。よい企画でした。ありがとう。 70代男性
生々しい映像で見ていて苦しかったが
体験した人々のことを思うとつらいです。
戦争は絶対にやってはいけないとの思いでいっぱいです。
ダメなものはダメと言えるようがんばります。
ありがとうございました。 70代女性
戦争はダメです。
この沖縄はどうなるのでしょうか。 70代女性
はだしのゲンについて
以前にマンガで全編を読んでいましたが
今回は作者の中沢啓治さんに会えるという期待をもっていました。
充分にそれが満たされた映画でした。
よくぞ、傷を受ける事なく、中沢さんが生き延び、また
お母さんと共に生きることで、仕事をなしとげられた。
その仕合せに感謝する次第です。
ふじ学徒隊について
以前、1フィート運動会の仕事で、語りをお願いして
お家にも伺った仲里ハルさんに再び会えて良かったです。
当時の軍人をどう評価するかは難しい面があると改めて感じます。
みちさの「ふじの花」とても心にしみました。 70代女性
ふじ学徒隊を見るのは2度目です。
今日、6月22日に見てよかったと思いました。
多くの日本人(大和人)に見て欲しいと思いますが
無理なのかも知れないとも思っています。 70代女性
1943年生まれ。
父、母の戦後の生活が思い出されて
父、母に苦労をかけられない子(私)だった事が・・・ 80代女性
はだしのゲンがもっとくわいく知りたいと思いました。
話は聞いていましたが原爆の恐ろしさを知りました。
次はひめゆり部隊も知りたいなと思いました。 80代女性
はだしのゲンが伝えたいこと
中途半端な用な・・・
もう一度、完璧なものが見たいです。
ふじ学徒隊は時期的にも非常によかったと思います。
これからも頑張って下さい。 80代女性
ふじ学徒隊
大変見てつらく、又、感動しました。
戦争の生々しさを多くの人に見てもらいたいです。
はだしのゲン
同じ戦争でも原爆の恐ろしさを感じました。 80代女性
貴重な記録の上映、ありがとうござました。
改めて戦争の悲惨さ、劇しさを
そして平和とは・・・感じるのが多いと思う。
「台湾有事」などとあおって、米国、日本の植民地化として
南西諸島を軍事基地化して、戦争準備に向かっている。
大和の政治家どもに怒りを感じます! 80代男性
はだしのゲンが伝えたいこと。
戦争の悲惨は異なるように感じる。
ふじ学徒隊。
絶対に戦争はやるべきではないと痛感しました。 90代女性
戦争を知らない世代が85%以上となり、
いかにして二度と戦争を起こさないようにするか。
79年目となる6月23日の慰霊の日にあたって
考えさせられる映画上映であった。 90代男性
〈6月会を振り返って〉
「海燕社の小さな映画会2024」6月会。
ご鑑賞の82名のお客様、ありがとうございました。
作品上映を快く了承して下さいました「シグロ」様、
「トモ・コーポレーション」様、石田優子監督、ありがとうございました。
会場「沖縄県立博物館美術館」様、ありがとうございました。
後援の「沖縄県」「那覇市」様、ありがとうございました。
宣伝にご協力下さいましたマスコミのみなさま、ありがとうございました。
SNSや口コミで宣伝下さいましたみなさま、ありがとうございました。
みなさまに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
海燕社の小さな映画会は海燕社が「観たい」「観て欲しい」映画を
一緒に観ませんか、というゆるやかな気持ちで開催している映画会です。
劇場ではなかなか上映されない(旧作)映画を選んでいます。
映画の多様性、特にドキュメンタリーの幅広さを知ってもらいたいという気持ちがあります。
2024年の映画会は10年目を記念してご鑑賞者にオリジナル「栞」をプレゼントしています。
4月会は「獅子」5月会は「木」…上映作品に合わせてテーマを決めてデザインしています。
記念品を「栞」にしたのは、私が映画を観る前や観た後に原作本や関連する本を読みたくなるからです。
映画会の思い出とともに読書の時に「栞」を愛用して頂けたらうれしいです。
「海燕社の小さな映画会2024」の6月会は、
『はだしのゲンが伝えたいこと』 と『ふじ学徒隊 』の二作品を上映しました。
『はだしのゲンが伝えたいこと』
漫画『はだしのゲン』は小学生の頃に読んだことがあります。描写の激しさに気圧されて「怖い」という感情が先に立ち正直苦手な漫画でしたがふしぎと心に「残る」一冊でもありました。漫画にもう一度向き合いたいとこの映画を観ました。そしてこどもの頃の揺れた思いの答えがわかったような気がしました。「怖い」は知らなさが生んでいたこと、「残る」は知ることから生まれるのだと。この映画は『はだしのゲン』が描いた広島の原爆を「知ること」それを手助けしてくれる映画です。海燕社の小さな映画会は毎年6月は海燕社製作の『ふじ学徒隊』を上映すると決めています。その併映という形でもう一作品の映画を選んでいますので毎回1時間未満の映画になります。今回の映画も本編の映画ではなくその短縮版を選ばざるを得ませんでした。機会があれば本編の映画『はだしのゲンが見たヒロシマ』をぜひ観て頂きたいと思います。
『ふじ学徒隊』は12年目の上映でした。
今年もふじ学徒隊、ふじ同窓会、ご家族など17名に招待状を送りました。ふじ学徒隊はみなさまご高齢ですのでお越し下さるのは難しいと分かっているのですが…毎年ご案内しています。今年はふじ同窓会役員のご家族様2名様にお越しいただけました。ありがとうございました。上映の度に、他界されたみなさまのことが思い出されます。みなさんとのご縁に感謝しかありません。新垣道子会長、與儀尚子副会長、映画で避難民の証言をして下さった大城正棋さん、映画製作委員会の福地曠昭さん、古謝将嘉さん、星雅彦さん、ふじ学徒隊の仲里ハルさん、真喜志善子さん、渡久地敏子さん、そして、野村岳也監督。旅立たれたみなさまも、きっと上映会場で観て頂いていると信じて身を引き締めて上映しました。そして、今回、映画会のアンケートで思いがけず田崎芳子さんの訃報を知りました。田崎さんは仲里ハルさん名城文子さんとともに「語り部」として積徳高等女学校看護隊の戦争体験を若い方に語ってきた方です。「語り部」としての自信と情熱が溢れる方でした。田崎さんの思い出で最も心に残っているがインタビューです。インタビュー撮影中、ふじ学徒隊のみなさまから収録方法について訴えられたことがありました。そのとき、代表してみなさんの思いを私に話されたのが田崎さんでした。「私達は全部話したいのに話させてくれない。聞きたいことだけ聞くのは止めて欲しい。全部聞いて下さい。」北谷のスタジオの外で、ふじ学徒隊のみなさんの前に立って、私に訴える田崎さんの責任感溢れる姿が忘れられません。私は謝罪し野村監督にみなさんの思いを伝え、後日インタビューは再収録されました。田崎芳子さんのご冥福をお祈り申し上げます。アンケートで田崎さんのことを教えて下さった方に感謝申し上げます。戦争体験者ではない私たちに、これからを生きる私たちのために、二度と自分達のようなことになって欲しくないという思いで、原爆体験を、漫画に描き訴え、更に映画で証言した中沢啓治さんと、思い出すのも辛い沖縄戦の体験を映画で証言したふじ学徒隊に、感謝と敬意を表します。私達に託された想いをどう引き継げばいいのでしょうか。私は戦争につながるどんなことにも「NO」と言い続けることだと思います。「NO」と行動することだと思います。海燕社は映画『ふじ学徒隊』上映活動を主軸にこの思いを伝えていきたいと思います。
映像作品は完成後が大事だと思っています。
製作者としては観てもらうこと、観客としては観ること、
その二つを映画に贈りたいです。
「海燕社の小さな映画会」はその一役になって欲しいと願っています。
アンケートの提出して下さった69名様に感謝申し上げます。
アンケートのご協力ありがとうございました。
感想を書いて下さったのは67名様。感想ブログ掲載不可は4名様。
63名のお客様の感想を上記で紹介させて頂きました。
ブログでのお客様全員の感想を紹介する活動を続けています。
海燕社のスタッフだけで読むには惜しい内容の感想ばかりだからです。
映画会に来て下さった皆様と感想を共有したい、
映画製作者のみなさまにお客様の感想を伝えたい、
映画会に来れなかったみなさまに作品について伝えたい、
という思いで感想をブログで紹介しています。
これからも続けます。ご協力をよろしくお願いします。
城間あさみ
【2024.6.22(日)/沖縄県立博物館・美術館3階講堂
13:15受付開場/14:05上映開始/15:30終了】
鑑賞料:1200円(予約一般)/1500円(当日一般)
※高校生以下無料券(予約先着10名様まで)
〈上映作品〉
『はだしのゲンが伝えたいこと 』
(2011年製作/石田優子監督/シグロ・トモコーポレーション/32分)
『ふじ学徒隊 』
(2012年製作/野村岳也監督/海燕社/48分)
〈入場まで〉
1.受付:①予約の方-鑑賞券(1,200円)/当日の方-当日券(1,500円)
②資料配布
2.手指アルコール消毒(各自:劇場入口設置)
3.入場着席:自由席
※配布資料
ラインナップ1枚、6月会チラシ1枚、
アンケート用紙、案内希望カード、下敷き、クリアファイル、クリップ鉛筆
※ご来場者プレゼント
10年目記念オリジナル栞1枚(6月会デザインテーマ「命どぅ宝」)
<プログラム>
1.開会
2.主催挨拶(城間あさみ)
3.『はだしのゲンが伝えたいこと 』
(2011年製作/石田優子監督/シグロ・トモコーポレーション/30分)
4.『ふじ学徒隊 』
(2012年製作/野村岳也監督/海燕社/48分)
5.閉会(アンケート記入)
<スタッフ> 4人(海燕社2人、同人1人、ボランティアスタッフ1人)
準備・片付け:全スタッフ
受付:(澤岻健/ボランティアスタッフ)
上映:(海燕社同人)
司会:(城間あさみ)
〈後援〉沖縄県/那覇市
【お客様の感想(アンケートより)】
戦前、戦中を知っている人がいなくなってる今、
私たち若ものが平和を作るための行動を
やめてはならないと改めて感じました。
‶二度と自分と同じ思いをしてほしくない”という
被爆者や学徒隊の方々の思いを忘れずに
これからも平和な世界になるように学び続けたいです。
ありがとうございました。また来ます。 10代女性
戦争体験を私たち若い世代は忘れてはならず、
今後も伝えていかなければと強く感じました。
私の祖父母も沖縄戦体験者ですが、
若い人は戦争を知らない人も多くとても悲しくなります。
実体験を聞く機会はあまりないので、
このような映画を通して考えることができて良かったです。 20代女性
私たちがなぜ戦争に反対するのか、
証言を直接きくことができなくなる今だからこそ、
その必要性を強く感じます。
私も広島出身で被爆者の話をきいてきました。
今、大学で平和教育を学んでおり、
今日は友人と東京から学びに来ました。
戦争体験者の生きた証に学び続け
私にもできることをがんばりたいです。
共にたたかいましょう。 20代女性
戦争のおそろしさ、
そして、沖縄戦で何が起きたか、ということがわかった。
国のために死ぬことのバカバカしさを知ることができ、
これから後世のために、二度と戦争を起こしてはいけないと思った。
戦争経験者が少なくなる中、継承していかなければと思った。 20代男性
感想を書きたいですが、
今は言葉が見つかりません。申し訳ないです。
この感情をどう整理したらよいのか、
整理できるのか分かりませんが
今、この平和な世の中に生きていられることに感謝して
明日の慰霊の日を迎えたいと思います。 30代男性
大切にしたくてどうしていいのか。
分からないこと(命、大切な人達、人生、大人になること)が
本当に大切な自分のいのちなこと、生きていきたいと思いました。
本当にありがとうございました。 30代女性
慰霊の日の前日に
この2つの映画を見ることができてよかったです。
はだしのゲンに関しても子どもの頃からよく読んでいたので
それと頭の中でイメージしながらみれたので
頭に心にはいっってきやすかったです。
ふじ学徒隊の方の映画での証言も
「戦争は絶対いけない」と改めて思い平和のために
自分が自分なりにできることをしていかないとと思わされました。
戦争を生き抜いてきた1人1人に
命をつないでもらっていることにも感謝です。
戦後も苦しんでいるのはつらい・・・。 40代女性
「はだしのゲン」
小学生の頃、はだしのゲンを読んでいました。
その時の強烈な描写はずっと頭から離れず
戦争は何が理由でもやらない方がいいと思いました。
その時はなんで皮フをたらして人が歩いているのか
きちんとわかってなかったけど、今日はその答え合わせのようでした。
大人になってわかることがあるので、この機会に恵まれて感謝です。
「ふじ学徒隊」
ふじは知りませんでした。
戦争の中、生きることの大切さを伝えた隊長もいたんだと思いました。
戦争の記憶がその人の人生を変えてします罪深さを感じました。 40代女性
「ふじ学徒隊」とても見たかった映画でした。
戦争の記憶がうすれていく中、元学徒隊の言葉が
とても心にささりました。生きて私たちに当時のことを
伝えて下さりありがとうございました。
『はだしのゲンが伝えたいこと』
中沢さんのお話に引き込まれた。
彼の描いた原爆直後の広島の様子が強烈だった。 40代女性
はだしのゲン
作者の中沢さんの生々しい回想が
現実の重さを私たちの心に届きました。
戦争をしないことが大切だと改めて思いました。
ふじ学徒隊
その時、なにがあったのかを
つらい体験にもかかわらず話を聞くことができて
今生きている私たちは二度と戦争をしてはならないと思いました。 50代女性
ふじ学徒隊
無駄な犠牲者を出さなかったことは
指揮する側の考え方によるところ大きかったと感じました。
はだしのゲンが伝えたいこと
中沢さんの想いが、若い世代にも伝わって欲しいと思いました。 50代男性
今日の目的は「はだしのゲンが伝えたいこと」だったのと、
「ふじ学徒隊」は見た事があった為、用事で遅れても見れると思って
期待していたもののチラシの順番が入れ違っていて残念だった。
が、「ふじ学徒隊」の臨場感のある映像と語りに圧倒され、
2度目だったのであやふやだった面がクリアになり有意義な時間を過ごせた。
「はだしのゲンが伝えたいこと」は、
中沢さんのインタビュー部分しか見られなかったものの
あれだけの重い体験を客観的に明るく伝えていて、
拍子抜け感とそれだから作品作りを通した想像を越えた体験の超越が
あったんだろうなと強さを感じた。凄い力のある作品だった。 50代男性
はだしのゲンが伝えたいこと、
今まで聞いていた広島原爆の凄まじさ、事に、この映画で知りました。
マンガのタイトルは知っていましたが、読んだ事がなかったと思います。
もう一度見たいと改めて考えさせられました。
ふじ学徒隊、何度見ても涙が出て
戦争は絶対にしてはならないと考えさせられます。 50代女性
原爆や沖縄戦の映画は、正直、観ることがつらくて
上映会に足を運ぶことができませんでしたが、今日は参加しました。
思っていたより、つらくなかったのは、なぜだろうか?と考えました。
中沢啓治の笑顔、語る言葉の力強さ、
ふじ学徒隊の皆さんの明るい温かな人柄が
伝わってきたからでしょうか。
映画のつくり手側の意図がすばらしいなと感じました。
明日の慰霊の日を前に、ふたつの作品を観ることができてよかったです。 50代女性
今年も映画でハルちゃん達と会えました。
つらい体験を語ってくださりありがとうございますという気持ちでいっぱいです。
体験者が少なくなってきた今だからこそ、
この映画の存在は本当に大切だと思っています。
中沢啓治さんの体験を知ることができて良かったです。
はだしのゲンは小学生の頃から読んでいましたが
改めてまた読んでみたいと思いました。
今日は若い方も多数観にこられていたのが印象的でした。 50代女性
日本語だと麦はムギ(↓でギを下げる図付)というアクセントです。
日本語の文章を朗読するのは難しいのならやめた方がいいです。
今回の文章の中で重要なワードが沖縄訛りで読まれると興ざめです。 50代女性
ここでしか見ることのできない作品の上映、
ありがとうございます。今回2回目の来場ですが、
今後もここでしか見ることの出来ない作品の上映を楽しみにしています。 50代女性
二度と戦争をしてはいけない。何度も言いたい。
‶命どぅ宝”その一言につきる。
上映下さりありがとうございました。 50代女性
実は「はだしのゲン」は読んだことがなく
ぜひ読んでみたいと思った。
「ふじ学徒隊」は前にも観た。
何も知らず観たら親せきの方が証言者のひとりだった。
田崎芳子さんは父のいとこだと思う。
ただ、すごく近い親せきというわけでもないので
そうそう会う人でもなかった。
映画を観た時には父はもう亡くなっており、
田崎さんもそれから3年後ぐらいに亡くなった。
私の知らない10代後半を過ごしたのだと知った。 60代女性
ひめゆり部隊だけではない、女子学徒。 60代男性
ここ数年前、同窓生であった母と一緒に見て以来、
何度もみていますが、見るたびに、心に響き、
戦争の理不尽さ、悲しさ、怖さを感じ、涙があふれてきました。
世界では、自国主義を通し、戦争を起こす大国、
沖縄のように、ある日戦地となり、そこで平和に暮らしていた人々が
亡くなっていく様子が平然とニュースで流れ、
人間の怖さ、おろかさに、くやしい思いです。
私は今日、戦争に心を痛めただけで、
どこかに反戦の思いが届くといいのですが・・・ 60代女性
今年で3度目の映画『ふじ学徒隊』。
何度も観ることは、なかなかないこと。
見るたびに違う発見があり、
今年は、小池隊長のもとにいたから、
他の学徒たちとは違って、生きのびたのだなぁ、と思いました。
生きて、次の世代を育てるのだということばも心に残りました。
この場所で、映画をみることで、平和を考えて、
祈りの気持ちを思い出しています。ありがとうございます。
『はだしのゲン』の作者、中沢さんのお話、
とてもたても臨場感(どいうと違う気もするのです。本当に
その場にいたのですから。すみません。ことばがみつからず)があり、
人は、こんなにおそろしいものをつくり、人を死に至らしめ、
苦しめているのだと思いました。
オッペンハイマーの映画を思い出しつつ。 60代女性
ほんの一瞬で、地獄と化したげんばく広島の惨状・・・
国に命をささげ、お国のためと信じ、
あまりにも残酷な思いをしてしまった女生徒たち
両方とも見るのも聞くのもつらかったです。
ゼッタイに戦争はダメと改めて思いました。
他の学校の学徒隊に比べて、死者は少ないとは言え、
悲しくつらい思いをされたことと思います。
隊長さんの「絶対に死んではならない」という言葉は、本当に重い。
あの人間が狂ってしまうような状況の戦争の中で
生きることを訴えてくれた人がいたことに感謝したい。
今日はありがつございました。内地の人にも伝えたいです。 60代女性
今回、はじめて沖縄に来ました。
戦争の事は‶他人事‶のように思っていましたが、
見学している間に、身に沁みて感じる事ができ、
平和の大きさを、とても感じる事ができ、よかったです。
今回の映画も良かったです。ありがとうございました。
これからも頑張って続けて下さい。 60代女性
初めて参加させて頂きました。
貴重な映画を観ることが出来、感動しました。
指導者の考え方ひとつで、犠牲者が増えるということが、よく分かった。
今日、今から名古屋へ帰る合間で観ることができて本当に良かったと思います。 60代男性
はだしのゲンについて、
中沢氏の被爆の体験には言葉になりません。
”ノーモアヒロシマ、ノーモアナガサキ”は人類にとっての
守るべき最重要な宣言だと思った。 60代男性
戦争と言う言葉を目にしない日はないほど
世界のどこかで日常茶飯事になっている。
犠牲者はほとんどが将来ある子ども達だ。胸がいたい。
終わらせる日は来るのだろうか。その日を待ち望む。 70代女性
一生、頑張って生きる! 70代女性
生々しい証言を、全国、余すことなく、
上映して、戦争の悲惨さを伝えて欲しい。
戦争は、勝っても、負けても、地球を破滅に導きます。 70代
離島から久々に出掛けてきました。
東京で現役時代の頃「はだしのゲン」の事は知っていました。
案内で懐かしく思い出され是非観たいと思い来ました。
明日の慰霊祭は島でも開催しますが、折角、那覇まで来たついでに、
「平和の礎」に行ける機会にめぐり合わせました。
ゲンさん「中沢さん」が伝えたい事、ご本人の言葉で伝えてもらい
改めて新たに「平和」への願いを一緒にしたいと思います。
いつもご案内頂いてなかなかこれませんでしたが、今回はご縁ですね。
明日につなげていただきました。ありがとうございます。 70代女性
戦争を知らない子ども達のために
平和へのメッセージとして
これからも上映して下さい。
今日はありがとうございました。 70代女性
これまで何度か視聴したが、6.23を前に考えたくて見学した。
かつての同僚がふじ学徒であり、
前回、見学した時のことを再度思いながらー。
はだしのゲンは、散草地の小さなガマを思い出しながら見学。
教育は大事ですね。 70代男性
平和がいかに大事であるか痛感した。
はだしのゲン、マンガを20代、30代の頃に読んだが
作者の中沢さんの生々しい話をきき
あらためて悲惨な状況をしることができました。
忘れてしまわないようにこういう映像は、本当にもっともっと
多くの人に知らせていくべきだと思った。もったいないです。
最近、きな臭いニュースが日増しに強くなっているように思う。 70代女性
「ふじ学徒隊」これで2回目みました。
12年前によくぞ撮ってくれました。
毎年見たいと思います。
「はだしのゲン」マンガも昔みました。
上映みてあらためて、すばらしいマンガを残してくれたと思います。 70代女性
2つのドキュメンタリー映画は
戦争を知らない(私もその1人ですが・・・)
若い世代に6月23日慰霊の日の前までに
中学校、高校生にぜひ観てもらいたいです。
今日の会場には、年輩が目立ちました。
平和教育、平和の大切さは、特に次の時代を背負う若者から
熟年層の意識の中にインプットして欲しいと思います。
戦争をさせない為にも、
一人一人の平和維持の為の実践が大切と思います。
今日は参加できて良かったです。 70代女性
ありがとうございました。 70代男性
あさみさんと呼ばせて下さい。
私が存じ上げてから数年、よく頑張ってくださっています。
ありがとうございます。これからも頑張ってお願い致します。
そして、後継者も仲間もたくさん増えますように!
いつもありがとうございます。 70代女性
何度みても心いたむ。
子や孫達にも、伝えなければ、いけない。 70代女性
ふじ学徒隊は去年も見ましたが
今日も涙が止まりませんでした。
本当に戦争が憎いです。
はだしのゲンはマンガを見ていたのですが
本人の証言は忘れられません。 70代女性
はだしのゲンが伝えたいこと。
「子どもたち自らが平和を追求し続けてほしいということだ」
今は、大人になった私たちも平和を追求しなくてはならないと思った。行動しよう。
ふじ学徒隊。
「積徳高等女学校学徒隊」
そのとき母は、10.10空襲の前に、故郷に帰ったと聞いた。
母は、学生時代のことは、語らなかった。
母の元気なとき、詳しく聞けなかった。
もしかしたら母の写真があるか、記念誌を調べたい。 70代女性
慰霊の日の近く
理にかなった企画だと思います。
人間は過去を反省せねばいけないのに
同じ事をくり返しています。
おろかです。 70代
「はだしのゲンが伝えたいこと」
中沢さんの語りが胸をうちました。
平和の尊さ大切さをあらためて思いました。
「ふじ学徒隊」
青春時代をうばわれた学徒のみなさんが
どんなに無念だったkと思うと心が痛みます。
平和を願わずにはいられません。 70代女性
はだしのゲンの作家 中沢啓治さんの生き方や
今まで歩んで来た道を話して下さり
世界へ通じる作品を作り上げて来た
パワー、パッションを知ることが出来、良かったです。 70代女性
二度と戦争を起こさせてはならない。
その思いが更に強くなりました。
有難うございました。 70代男性
体験者の皆様の言葉に強い衝撃を受けました。
今、平和に暮らしている私達は幸せだと思います。 70代女性
はだしのゲンの作者の生の声が聞けて大変よかったです。
ふじ学徒隊。
この時期、機会があると毎回観ています。
今後も、特に若い人達に、多くの方々に、
観て頂きたいと強く思いました。
本日はありがとうございました。 70代女性
とてもよかったです。
なかなか見れない映画をみることが出来とてもよかった。
皆様のご活躍うれしく思います。 70代女性
戦争の悲惨な事を、改めて知りました。
家族が倒れた家の下敷きになっても救えなかった事
とても胸が痛くなりました。 70代男性
来年も見る。 70代男性
ふじ学徒隊の事を知らない人達が周囲に多く
マスコミに発信して欲しい。 70代女性
慰霊の日の前日にあたる日の今日の2本の上映
とても意義深いものでした。ゲンも、ふじも、改めて戦後の平和に
思い至る大事な証言映画でした。よい企画でした。ありがとう。 70代男性
生々しい映像で見ていて苦しかったが
体験した人々のことを思うとつらいです。
戦争は絶対にやってはいけないとの思いでいっぱいです。
ダメなものはダメと言えるようがんばります。
ありがとうございました。 70代女性
戦争はダメです。
この沖縄はどうなるのでしょうか。 70代女性
はだしのゲンについて
以前にマンガで全編を読んでいましたが
今回は作者の中沢啓治さんに会えるという期待をもっていました。
充分にそれが満たされた映画でした。
よくぞ、傷を受ける事なく、中沢さんが生き延び、また
お母さんと共に生きることで、仕事をなしとげられた。
その仕合せに感謝する次第です。
ふじ学徒隊について
以前、1フィート運動会の仕事で、語りをお願いして
お家にも伺った仲里ハルさんに再び会えて良かったです。
当時の軍人をどう評価するかは難しい面があると改めて感じます。
みちさの「ふじの花」とても心にしみました。 70代女性
ふじ学徒隊を見るのは2度目です。
今日、6月22日に見てよかったと思いました。
多くの日本人(大和人)に見て欲しいと思いますが
無理なのかも知れないとも思っています。 70代女性
1943年生まれ。
父、母の戦後の生活が思い出されて
父、母に苦労をかけられない子(私)だった事が・・・ 80代女性
はだしのゲンがもっとくわいく知りたいと思いました。
話は聞いていましたが原爆の恐ろしさを知りました。
次はひめゆり部隊も知りたいなと思いました。 80代女性
はだしのゲンが伝えたいこと
中途半端な用な・・・
もう一度、完璧なものが見たいです。
ふじ学徒隊は時期的にも非常によかったと思います。
これからも頑張って下さい。 80代女性
ふじ学徒隊
大変見てつらく、又、感動しました。
戦争の生々しさを多くの人に見てもらいたいです。
はだしのゲン
同じ戦争でも原爆の恐ろしさを感じました。 80代女性
貴重な記録の上映、ありがとうござました。
改めて戦争の悲惨さ、劇しさを
そして平和とは・・・感じるのが多いと思う。
「台湾有事」などとあおって、米国、日本の植民地化として
南西諸島を軍事基地化して、戦争準備に向かっている。
大和の政治家どもに怒りを感じます! 80代男性
はだしのゲンが伝えたいこと。
戦争の悲惨は異なるように感じる。
ふじ学徒隊。
絶対に戦争はやるべきではないと痛感しました。 90代女性
戦争を知らない世代が85%以上となり、
いかにして二度と戦争を起こさないようにするか。
79年目となる6月23日の慰霊の日にあたって
考えさせられる映画上映であった。 90代男性
〈6月会を振り返って〉
「海燕社の小さな映画会2024」6月会。
ご鑑賞の82名のお客様、ありがとうございました。
作品上映を快く了承して下さいました「シグロ」様、
「トモ・コーポレーション」様、石田優子監督、ありがとうございました。
会場「沖縄県立博物館美術館」様、ありがとうございました。
後援の「沖縄県」「那覇市」様、ありがとうございました。
宣伝にご協力下さいましたマスコミのみなさま、ありがとうございました。
SNSや口コミで宣伝下さいましたみなさま、ありがとうございました。
みなさまに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
海燕社の小さな映画会は海燕社が「観たい」「観て欲しい」映画を
一緒に観ませんか、というゆるやかな気持ちで開催している映画会です。
劇場ではなかなか上映されない(旧作)映画を選んでいます。
映画の多様性、特にドキュメンタリーの幅広さを知ってもらいたいという気持ちがあります。
2024年の映画会は10年目を記念してご鑑賞者にオリジナル「栞」をプレゼントしています。
4月会は「獅子」5月会は「木」…上映作品に合わせてテーマを決めてデザインしています。
記念品を「栞」にしたのは、私が映画を観る前や観た後に原作本や関連する本を読みたくなるからです。
映画会の思い出とともに読書の時に「栞」を愛用して頂けたらうれしいです。
「海燕社の小さな映画会2024」の6月会は、
『はだしのゲンが伝えたいこと』 と『ふじ学徒隊 』の二作品を上映しました。
『はだしのゲンが伝えたいこと』
漫画『はだしのゲン』は小学生の頃に読んだことがあります。描写の激しさに気圧されて「怖い」という感情が先に立ち正直苦手な漫画でしたがふしぎと心に「残る」一冊でもありました。漫画にもう一度向き合いたいとこの映画を観ました。そしてこどもの頃の揺れた思いの答えがわかったような気がしました。「怖い」は知らなさが生んでいたこと、「残る」は知ることから生まれるのだと。この映画は『はだしのゲン』が描いた広島の原爆を「知ること」それを手助けしてくれる映画です。海燕社の小さな映画会は毎年6月は海燕社製作の『ふじ学徒隊』を上映すると決めています。その併映という形でもう一作品の映画を選んでいますので毎回1時間未満の映画になります。今回の映画も本編の映画ではなくその短縮版を選ばざるを得ませんでした。機会があれば本編の映画『はだしのゲンが見たヒロシマ』をぜひ観て頂きたいと思います。
『ふじ学徒隊』は12年目の上映でした。
今年もふじ学徒隊、ふじ同窓会、ご家族など17名に招待状を送りました。ふじ学徒隊はみなさまご高齢ですのでお越し下さるのは難しいと分かっているのですが…毎年ご案内しています。今年はふじ同窓会役員のご家族様2名様にお越しいただけました。ありがとうございました。上映の度に、他界されたみなさまのことが思い出されます。みなさんとのご縁に感謝しかありません。新垣道子会長、與儀尚子副会長、映画で避難民の証言をして下さった大城正棋さん、映画製作委員会の福地曠昭さん、古謝将嘉さん、星雅彦さん、ふじ学徒隊の仲里ハルさん、真喜志善子さん、渡久地敏子さん、そして、野村岳也監督。旅立たれたみなさまも、きっと上映会場で観て頂いていると信じて身を引き締めて上映しました。そして、今回、映画会のアンケートで思いがけず田崎芳子さんの訃報を知りました。田崎さんは仲里ハルさん名城文子さんとともに「語り部」として積徳高等女学校看護隊の戦争体験を若い方に語ってきた方です。「語り部」としての自信と情熱が溢れる方でした。田崎さんの思い出で最も心に残っているがインタビューです。インタビュー撮影中、ふじ学徒隊のみなさまから収録方法について訴えられたことがありました。そのとき、代表してみなさんの思いを私に話されたのが田崎さんでした。「私達は全部話したいのに話させてくれない。聞きたいことだけ聞くのは止めて欲しい。全部聞いて下さい。」北谷のスタジオの外で、ふじ学徒隊のみなさんの前に立って、私に訴える田崎さんの責任感溢れる姿が忘れられません。私は謝罪し野村監督にみなさんの思いを伝え、後日インタビューは再収録されました。田崎芳子さんのご冥福をお祈り申し上げます。アンケートで田崎さんのことを教えて下さった方に感謝申し上げます。戦争体験者ではない私たちに、これからを生きる私たちのために、二度と自分達のようなことになって欲しくないという思いで、原爆体験を、漫画に描き訴え、更に映画で証言した中沢啓治さんと、思い出すのも辛い沖縄戦の体験を映画で証言したふじ学徒隊に、感謝と敬意を表します。私達に託された想いをどう引き継げばいいのでしょうか。私は戦争につながるどんなことにも「NO」と言い続けることだと思います。「NO」と行動することだと思います。海燕社は映画『ふじ学徒隊』上映活動を主軸にこの思いを伝えていきたいと思います。
映像作品は完成後が大事だと思っています。
製作者としては観てもらうこと、観客としては観ること、
その二つを映画に贈りたいです。
「海燕社の小さな映画会」はその一役になって欲しいと願っています。
アンケートの提出して下さった69名様に感謝申し上げます。
アンケートのご協力ありがとうございました。
感想を書いて下さったのは67名様。感想ブログ掲載不可は4名様。
63名のお客様の感想を上記で紹介させて頂きました。
ブログでのお客様全員の感想を紹介する活動を続けています。
海燕社のスタッフだけで読むには惜しい内容の感想ばかりだからです。
映画会に来て下さった皆様と感想を共有したい、
映画製作者のみなさまにお客様の感想を伝えたい、
映画会に来れなかったみなさまに作品について伝えたい、
という思いで感想をブログで紹介しています。
これからも続けます。ご協力をよろしくお願いします。
城間あさみ
Posted by カイエンシャ at
08:11
│海燕社の小さな映画会
2024年05月29日
[海燕社の小さな映画会2024 5月会」 『奥会津の木地師 』『木の生命よみがえる 川北良造の木工芸』
海燕社の小さな映画会2024 5月会
【2024.5.19(日)/沖縄県立博物館・美術館3階講堂
13:15受付開場/14:05上映開始/15:30終了】
鑑賞料:1200円(予約一般)/1500円(当日一般)
※高校生以下無料券(予約先着10名様まで)
〈上映作品〉
『奥会津の木地師 福島県田島町針生 』
(1989年製作/民族文化映像研究所 製作/30分)
『木の生命よみがえる 川北良造の木工芸 』
(1981年製作/ポーラ伝統文化振興財団/桜映画社/30分)
〈入場まで〉
1.受付:①予約の方-鑑賞券(1,200円)/当日の方-当日券(1,500円)
②資料配布
2.手指アルコール消毒(各自:劇場入口設置)
3.入場着席:自由席
※配布資料
ラインナップ1枚、5月会チラシ1枚、
パンフレット(ポーラ伝統文化振興財団様より提供)、
アンケート用紙、案内希望カード、下敷き、クリアファイル、クリップ鉛筆
※ご来場者プレゼント
10年目記念オリジナル栞1枚(5月会デザインテーマ「木」)
<プログラム>
1.開会
2.主催挨拶(城間あさみ)
3.『奥会津の木地師 福島県田島町針生 』(1989年/民族文化映像研究所製作/30分)
4.『木の生命よみがえる 川北良造の木工芸 』
(1981年/ポーラ伝統文化振興財団製作/村山英治監督(桜映画社)/30分)
5.閉会(アンケート記入)
<スタッフ> 3人(海燕社2人、ボランティアスタッフ1人)
準備・片付け:全スタッフ
受付:(澤岻健/ボランティアスタッフ)
上映:(城間あさみ)
司会:(城間あさみ)
〈後援〉沖縄県/那覇市/ポーラ伝統文化振興財団
【お客様の感想(アンケートより)】
川北氏の木に対する愛が伝わってきた。 20代女性
4月に他県から沖縄に越して来て、
このような素晴らしい映画会が開催されるのを
偶然立ち寄った喫茶店の張り紙で知りました。
また来月も見に来たいと思います。
10周年、おめでとうございます。
これからも頑張ってください。
(作品の感想じゃなくてごめんなさい)
作品は、ただただ技術に圧倒されました。 30代女性
普段使いとしての木工、芸術品としての木工
どちらも美しく魅了されました。
「奥会津の木地師」で登場した作業小屋が印象的です。
全て自然に還るものを利用していて
〝山に生きる‶姿勢がそこに表れているようでした。
☆アンコール上映、すごく嬉しいです。
見逃したものを見ることができるので! 30代女性
途絶えてしまった手引きロクロの映像が見れて良かったです。
木地師がどのように山で生きていたか、
己の手のみで仕事をしていたことに、ただただ驚きました。 30代女性
素晴らしい映画でした。
木を切る時の音の柔らかさ、
職人さんのきれいなお顔や無駄のない言葉、
ムクムクとした手が、なんとも魅力的でした。
自然に敬意を持ちながら、できる仕事は貴重だと思います。
この映画が製作された時代から、
さらに私達は乖離した世界で生活してる実感を持ちます。
道具を使うことが危ない感覚を子どもたちに伝えてしまってる気がします。
充分に動く自分の手足を大切に、もっと使って、生活したいです。
ありがとうございました。 30代女性
木地師という仕事についてはじめて知った。
映画の中で木地師の生活、仕事が紹介され、
現代では忘れられている大切なことを教えられたように感じた。
今回、映画会を通して、この映画を観ることができてよかった。
また次回の映画会にも足を運んでみようと思います。
ありがとうございました。 40代女性
奥会津の木地師は、小屋作りから始まるとても貴重な映像でした。
1本の木をおので切り、切った側から碗を何個もほり出していく所、
荒く削るのは女の人が削っていた所もとても興味深かったです。
山中の川北さんは、木地師として極めた人で、
奥会津とはまた違うアーティスト的な面もあり、
全然違う土台でできる木地の違いも面白かったです。
良い作品をありがとうございました。 40代女性
昔の木地師のリアルな暮らしと仕事ぶりを興味深く拝見した。
大変有意義な映画鑑賞でした。 40代女性
2本ともとてもすばらしい映画でした。
今は物があふれている時代ですが改めて物を大切に、
本当に必要な物か考えて買いたいと思います。
海燕社の映画会を見るといつも先人たちのすごさがわかります。
いい映画をありがとうございました。 40代女性
沖縄の失われた工芸の研究をしているので、
そのヒントになりそうなものがありました。
ありがとうございました。 40代男性
初めて木地師の事を知りました。
自然と共に生き、木(自然)への畏敬の念を抱いて
生活し仕事をする。
私達が日常生活で忘れている心(自然と共生する)を
教えてくれたと思います。 50代女性
木地師という言葉とその方たちの生活を知りました。
自然の中でのくらし、住居や仕事道具、作品も全て、
人の手で海ださsれ手いたのにとても感動しました。
その方たちの中にはいつも感謝の気持ちがあって
謙虚なたたずまいには、あるべき人間の姿だろうなと思いました。
次回いつか‶アイヌの知る″‶林竹二″の
リバイバル上映が観れたらうれしいです。 50代女性
今回もご案内をありがとうございました。
丁度、宮本常一著『山に生きる人々』を読了したところで、
かつての木地師の小屋や仕事、くらしにとても関心が高まっていたので
みに来られて本当によかったです。
私が幼少の頃にはまだこの様な技を持った人々がご存命だったのですね。
お会いしてみたかったです。貴重な映像資料を残して下さった方々や
今回の上映会を企画して下さった皆様に感謝申し上げます。
これからも良質な映画の上映を続けて頂けましたら幸いです。
(前回の上映会、残念ながら都合がつかずに来れませんでした。
『うむい獅子』もみてみたいので何年か後でもかまいません。
ぜひ、また上映をお願いします。) 50代女性
貴重な映像をありがとうございました。
他では見ることの出来ないすばらしい時間でした。
次回は県内の映画を見におじゃましたいと思います。 50代女性
奥会津の木地師は2回目でしたがとてもよかったです。
何度見ても祈りの場面は背筋を正したくなります。
川北良造さんの「木は動く」
「木すじを見極めて思いきって切ってしまう」等
とても心に残りました。 50代女性
木工に興味があるのでとても楽しかった。
私も作りたいなと思った。
あの時だから再現できて映像に残せたんだと思う。
今では…むりですものね…
残してくれてありがとう。 50代女性
とても貴重な映像を見ることができて、感謝します。
お山のほったて小屋作りがすばらしかった!
皆の協力ですごい早さで暮らしが整えられていき感動しました。
お山の豊かさ、木の力が体感できる映画たちでした。 50代女性
こうした玄人の技の映像はとても興味深く
今後もこうした作品を上映して下さい。
ホームページがあまり更新されていないようで、
できればそちらもお願いします。 50代男性
自然に認められた職人、木地師さん達の作品と向き合う。
作品の素となる自然からの贈り物に対する畏敬の念、想いが
言葉ひとつひとつと共に伝わってきた。 50代女性
「奥会津の木地師」はずっと観たかった映画でした。
本日は観ることができてとてもうれしいです。
もう1本の「木の生命よみがえる」もとてもよかったです。
大きな木、健全な山があってこその恵みだと思いました。
ありがとうございます。 50代女性
2本とも職人技の素晴らしさにとても感動しました。
出来上がった作品には、
とてつもない努力が注がれていることも認識しました。 60代男性
職人の手の動きが好きです。
真剣な芽の動き、作品との対峙
なにもかもに魅かれます。
木のかおりがせまってくるようでした。 60代女性
上映前に城間さんが映画会が始まって10年になるが、
これまでの傾向として‶ものづくり〟のものが多いとおっしゃていました。
でもそれは、ちょっと大げさかもしれないが人間のそなわっている気質、
自分で何かをつくりたいという要求がそなわっているからではないかと思いました。
会場のすべての人が映像に魅入られているように感じました。
特に奥会津の映像には驚きました。 60代女性
人の手って、すごいなぁー
木って、すごいなぁー
人の手って、なんでもつくれるんだ・・・
木って、いとしいなぁー
一つの器が人間の美しさ、木の美しさを
みせてくれた様な気がします。 60代女性
とてもすばらしい映画会でした。
本や資料で見聞きしたいた木地師のくらしを
映像で見ることができて大変よかった。 60代女性
山と川から成る森、木が生れ、器となる。
木工芸をいとなむ人々の情熱、
山の精に魅いだされた木地師、木工芸者。
奥会津の記録はとても貴いものに思えたが今はない。 60代男性
ありがとうございます。
伝統工芸を守り、引き継いでいく
伝統工芸人に感謝申し上げます。 70代女性
木工芸、日本の木、沖縄には大木が無いので
大木の中で生活し、古来からの伝統を引き継ぎ
木を切り、ろくろをひき、非常に細かい作業、
丁寧な作業に心を打たれた。
又、うるしの木を植え、生うるしを作品に何度も使用し
木目の美しさを引き出し、すごい工芸品が出来る
次代の若者達にぜひ引き継いで欲しい。 70代女性
会津塗の器をもってます。
お盆などつい粗末に大事に使用してなくて反省してます。
時代の進化をつくづく感じました。
この様な映像を大事に伝える大事さを感じました。 70代女性
細かな工程を経て生まれる器(木工芸)にとても感動しました。
また、山間地での木地師の移動と山と一体化した小屋造りに
変わってゆくもののはかなさを感じました。 70代男性
木工芸の製作法を改めて認識しました。
今後は津軽三味線の記録映画も上映して欲しいです。 70代男性
自然にあるもので小屋を作る技術、
それを受け継ぎ作り上げていけたことに驚きました。
その小屋を作っていた人々が木地師ではなく、
里の人々、いろんなことがつながって結びついて
成り立っていたのだなと感じた。
何年もかけて育つ気の美しさ、貴重さ、改めて感じた。 70代女性
2作品ともすばらしい。
この先も木工芸が発展することを願っています。
ため息が出るほどステキな上映ありがとうございました。
沖縄の琉球松の木目も大好きで毎年沖展での作品も楽しみなんです。
木工芸、あたたかみがありいいですね。
木がずっと生きているのワードにも感動しました。 70代女性
木が新たな生命を頂いて
私達に語りかけてくれている事に
感激致しました。
又、次回楽しみにしています。 70代女性
人間ってすごいの一言に尽きる。
子ども達に鑑賞の機会を与えて欲しい。 70代女性
木工の世界、素晴らしかったです。
お椀や器が木という素材からこんなふうにして
食卓に上がるのかと興味深く観ました。
多くの人の時間と手間と力が込められているのですね。
両方ともとても良かったです。感動しました。 70代女性
手造りの貴重な宝であることを知らされました。 70代男性
2つ合わせてとてもよかったです。 70代男性
素晴らしい作品でした。
木地師、木工芸師の強い想いが伝わりました。
有難うございます! 70代男性
毎回感動のみ。
次回楽しみにしています。 70代女性
奥会津の木地師の生活をしている人々の姿に
ただ口をポカンと開けて見入っていました。
溜め生きではなく、体の中から出てくる
空気の声みたいなものが出ました。
生活の技、いや、人間の至高の技か。
ただただ口をポカンと開けて見ました。
素晴らしい映画でした。 70代女性
木の器を作る厳しさを教えられました。
これまでとは違った目で見ることと思う。
そして愛おしさが増すことでしょう。 80代女性
作品名、木の生命よみがえる。
幼木から老木、そして見事なうるし、感動しました。 90代女性
木工芸の工程、おもしろかったです。
名木が木工芸として器となり
人々に使われ
まさしく生命がよみがえるようでした。
〈5月会を振り返って〉
「海燕社の小さな映画会2024」5月会。
ご鑑賞の59名のお客様、ありがとうございました。
作品上映を快く了承して下さいました「民族映像文化研究所」様、
「ポーラ伝統文化振興財団」様、「桜映画社」様、ありがとうございました。
会場「沖縄県立博物館美術館」様、ありがとうございました。
後援の「沖縄県」「那覇市」「ポーラ伝統文化振興財団」様、ありがとうございました。
宣伝にご協力下さいましたマスコミのみなさま、ありがとうございました。
SNSや口コミで宣伝下さいましたみなさま、ありがとうございました。
みなさまに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
海燕社の小さな映画会は海燕社が「観たい」「観て欲しい」映画を一緒に観ませんか、という
ゆるやかでたおやかな気持ちで開催している映画会です。
映画館ではなかなか上映されない映画を選んでいます。
映画の多様性、特にドキュメンタリーの幅広さを知ってもらいたいという気持ちがあります。
2024年の映画会は10年目を記念してご鑑賞者にオリジナル「栞」をプレゼントしています。
4月会は「獅子」5月会は「木」…上映作品に合わせてテーマを決めてデザインしています。
「栞」にしたのは、私が映画を観た後、原作本や関連する本を読みたくなるからです。
映画会の思い出とともに読書の友として「栞」を使ってもらえたらと思います。
「海燕社の小さな映画会2024」の5月会は、
『奥会津の木地師 福島県田島町針生 』(民族文化映像研究所 ) と『木の生命よみがえる 川北良造の木工芸 』(ポーラ伝統文化振興財団/桜映画社)の二作品を上映しました。
『奥会津の木地師』はアンコール上映です。はじめてみたときの衝撃が忘れられません。木地師が山で切り倒した木からその場で碗の形の塊を削り掘り出す。その塊を素手や素足で掴みそこに刃物を振り下ろし更に削りこむ。圧巻のシーンです。何度観てもその技の見事さにただただ感嘆します。テスト試写も含めると何度も観ているこの作品。今回はちょっとしたシーンにも目が向きました。その一つが、木地師の銜えたばこ。かっこいい。私が幼い頃はよくみかけた大人の男の人の姿です。故野村岳也監督もかつて銜えたばこで16ミリフィルム編集していたこともなつかしく思い出されました。
『木の生命よみがえる-川北良造の木工芸-』は沖縄初上映です。旋盤の技。その美しさに魅了されます。回転とともに表れる器の形と削り出る木くず。どれも愛おしい。川北さんが、器となる部位と木くずになる部位、残る材と残されない材、両方への想いを語られていて共感しました。映像制作も同じだからです。撮影時、編集時、悩みます。選んだこと、選ばなかったこと、どちらにも想いがあります。また鑑賞中、沖縄の琉球漆器を想っていました。今、浦添美術館に行きたくなっています。5月会の2作品は、木を通して、自然の貴さ、手で、足で、体で…自ら生み出すことの貴さ、そして、人と人、自然と人が助け合う貴さ、を教えてくれたように思います。
映像作品は完成後が大事だと思っています。
製作者としては観てもらうこと、観客としては観ること、
その二つを映画に贈りたいです。
「海燕社の小さな映画会」はその一役になって欲しいと願っています。
アンケートの提出して下さった52名様に感謝申し上げます。
アンケートのご協力ありがとうございました。
感想を書いて下さったのは48名様。感想ブログ掲載不可は4名様。
44名のお客様の感想を上記で紹介させて頂きました。
ブログでのお客様全員の感想を紹介する活動を続けています。
海燕社のスタッフだけで読むには惜しい内容の感想ばかりだからです。
映画会に来て下さった皆様と感想を共有したい、
映画製作者のみなさまにお客様の感想を伝えたい、
映画会に来れなかったみなさまに作品について伝えたい、
という思いで感想をブログで紹介しています。
これからも続けます。ご協力をよろしくお願いします。
城間あさみ
【2024.5.19(日)/沖縄県立博物館・美術館3階講堂
13:15受付開場/14:05上映開始/15:30終了】
鑑賞料:1200円(予約一般)/1500円(当日一般)
※高校生以下無料券(予約先着10名様まで)
〈上映作品〉
『奥会津の木地師 福島県田島町針生 』
(1989年製作/民族文化映像研究所 製作/30分)
『木の生命よみがえる 川北良造の木工芸 』
(1981年製作/ポーラ伝統文化振興財団/桜映画社/30分)
〈入場まで〉
1.受付:①予約の方-鑑賞券(1,200円)/当日の方-当日券(1,500円)
②資料配布
2.手指アルコール消毒(各自:劇場入口設置)
3.入場着席:自由席
※配布資料
ラインナップ1枚、5月会チラシ1枚、
パンフレット(ポーラ伝統文化振興財団様より提供)、
アンケート用紙、案内希望カード、下敷き、クリアファイル、クリップ鉛筆
※ご来場者プレゼント
10年目記念オリジナル栞1枚(5月会デザインテーマ「木」)
<プログラム>
1.開会
2.主催挨拶(城間あさみ)
3.『奥会津の木地師 福島県田島町針生 』(1989年/民族文化映像研究所製作/30分)
4.『木の生命よみがえる 川北良造の木工芸 』
(1981年/ポーラ伝統文化振興財団製作/村山英治監督(桜映画社)/30分)
5.閉会(アンケート記入)
<スタッフ> 3人(海燕社2人、ボランティアスタッフ1人)
準備・片付け:全スタッフ
受付:(澤岻健/ボランティアスタッフ)
上映:(城間あさみ)
司会:(城間あさみ)
〈後援〉沖縄県/那覇市/ポーラ伝統文化振興財団
【お客様の感想(アンケートより)】
川北氏の木に対する愛が伝わってきた。 20代女性
4月に他県から沖縄に越して来て、
このような素晴らしい映画会が開催されるのを
偶然立ち寄った喫茶店の張り紙で知りました。
また来月も見に来たいと思います。
10周年、おめでとうございます。
これからも頑張ってください。
(作品の感想じゃなくてごめんなさい)
作品は、ただただ技術に圧倒されました。 30代女性
普段使いとしての木工、芸術品としての木工
どちらも美しく魅了されました。
「奥会津の木地師」で登場した作業小屋が印象的です。
全て自然に還るものを利用していて
〝山に生きる‶姿勢がそこに表れているようでした。
☆アンコール上映、すごく嬉しいです。
見逃したものを見ることができるので! 30代女性
途絶えてしまった手引きロクロの映像が見れて良かったです。
木地師がどのように山で生きていたか、
己の手のみで仕事をしていたことに、ただただ驚きました。 30代女性
素晴らしい映画でした。
木を切る時の音の柔らかさ、
職人さんのきれいなお顔や無駄のない言葉、
ムクムクとした手が、なんとも魅力的でした。
自然に敬意を持ちながら、できる仕事は貴重だと思います。
この映画が製作された時代から、
さらに私達は乖離した世界で生活してる実感を持ちます。
道具を使うことが危ない感覚を子どもたちに伝えてしまってる気がします。
充分に動く自分の手足を大切に、もっと使って、生活したいです。
ありがとうございました。 30代女性
木地師という仕事についてはじめて知った。
映画の中で木地師の生活、仕事が紹介され、
現代では忘れられている大切なことを教えられたように感じた。
今回、映画会を通して、この映画を観ることができてよかった。
また次回の映画会にも足を運んでみようと思います。
ありがとうございました。 40代女性
奥会津の木地師は、小屋作りから始まるとても貴重な映像でした。
1本の木をおので切り、切った側から碗を何個もほり出していく所、
荒く削るのは女の人が削っていた所もとても興味深かったです。
山中の川北さんは、木地師として極めた人で、
奥会津とはまた違うアーティスト的な面もあり、
全然違う土台でできる木地の違いも面白かったです。
良い作品をありがとうございました。 40代女性
昔の木地師のリアルな暮らしと仕事ぶりを興味深く拝見した。
大変有意義な映画鑑賞でした。 40代女性
2本ともとてもすばらしい映画でした。
今は物があふれている時代ですが改めて物を大切に、
本当に必要な物か考えて買いたいと思います。
海燕社の映画会を見るといつも先人たちのすごさがわかります。
いい映画をありがとうございました。 40代女性
沖縄の失われた工芸の研究をしているので、
そのヒントになりそうなものがありました。
ありがとうございました。 40代男性
初めて木地師の事を知りました。
自然と共に生き、木(自然)への畏敬の念を抱いて
生活し仕事をする。
私達が日常生活で忘れている心(自然と共生する)を
教えてくれたと思います。 50代女性
木地師という言葉とその方たちの生活を知りました。
自然の中でのくらし、住居や仕事道具、作品も全て、
人の手で海ださsれ手いたのにとても感動しました。
その方たちの中にはいつも感謝の気持ちがあって
謙虚なたたずまいには、あるべき人間の姿だろうなと思いました。
次回いつか‶アイヌの知る″‶林竹二″の
リバイバル上映が観れたらうれしいです。 50代女性
今回もご案内をありがとうございました。
丁度、宮本常一著『山に生きる人々』を読了したところで、
かつての木地師の小屋や仕事、くらしにとても関心が高まっていたので
みに来られて本当によかったです。
私が幼少の頃にはまだこの様な技を持った人々がご存命だったのですね。
お会いしてみたかったです。貴重な映像資料を残して下さった方々や
今回の上映会を企画して下さった皆様に感謝申し上げます。
これからも良質な映画の上映を続けて頂けましたら幸いです。
(前回の上映会、残念ながら都合がつかずに来れませんでした。
『うむい獅子』もみてみたいので何年か後でもかまいません。
ぜひ、また上映をお願いします。) 50代女性
貴重な映像をありがとうございました。
他では見ることの出来ないすばらしい時間でした。
次回は県内の映画を見におじゃましたいと思います。 50代女性
奥会津の木地師は2回目でしたがとてもよかったです。
何度見ても祈りの場面は背筋を正したくなります。
川北良造さんの「木は動く」
「木すじを見極めて思いきって切ってしまう」等
とても心に残りました。 50代女性
木工に興味があるのでとても楽しかった。
私も作りたいなと思った。
あの時だから再現できて映像に残せたんだと思う。
今では…むりですものね…
残してくれてありがとう。 50代女性
とても貴重な映像を見ることができて、感謝します。
お山のほったて小屋作りがすばらしかった!
皆の協力ですごい早さで暮らしが整えられていき感動しました。
お山の豊かさ、木の力が体感できる映画たちでした。 50代女性
こうした玄人の技の映像はとても興味深く
今後もこうした作品を上映して下さい。
ホームページがあまり更新されていないようで、
できればそちらもお願いします。 50代男性
自然に認められた職人、木地師さん達の作品と向き合う。
作品の素となる自然からの贈り物に対する畏敬の念、想いが
言葉ひとつひとつと共に伝わってきた。 50代女性
「奥会津の木地師」はずっと観たかった映画でした。
本日は観ることができてとてもうれしいです。
もう1本の「木の生命よみがえる」もとてもよかったです。
大きな木、健全な山があってこその恵みだと思いました。
ありがとうございます。 50代女性
2本とも職人技の素晴らしさにとても感動しました。
出来上がった作品には、
とてつもない努力が注がれていることも認識しました。 60代男性
職人の手の動きが好きです。
真剣な芽の動き、作品との対峙
なにもかもに魅かれます。
木のかおりがせまってくるようでした。 60代女性
上映前に城間さんが映画会が始まって10年になるが、
これまでの傾向として‶ものづくり〟のものが多いとおっしゃていました。
でもそれは、ちょっと大げさかもしれないが人間のそなわっている気質、
自分で何かをつくりたいという要求がそなわっているからではないかと思いました。
会場のすべての人が映像に魅入られているように感じました。
特に奥会津の映像には驚きました。 60代女性
人の手って、すごいなぁー
木って、すごいなぁー
人の手って、なんでもつくれるんだ・・・
木って、いとしいなぁー
一つの器が人間の美しさ、木の美しさを
みせてくれた様な気がします。 60代女性
とてもすばらしい映画会でした。
本や資料で見聞きしたいた木地師のくらしを
映像で見ることができて大変よかった。 60代女性
山と川から成る森、木が生れ、器となる。
木工芸をいとなむ人々の情熱、
山の精に魅いだされた木地師、木工芸者。
奥会津の記録はとても貴いものに思えたが今はない。 60代男性
ありがとうございます。
伝統工芸を守り、引き継いでいく
伝統工芸人に感謝申し上げます。 70代女性
木工芸、日本の木、沖縄には大木が無いので
大木の中で生活し、古来からの伝統を引き継ぎ
木を切り、ろくろをひき、非常に細かい作業、
丁寧な作業に心を打たれた。
又、うるしの木を植え、生うるしを作品に何度も使用し
木目の美しさを引き出し、すごい工芸品が出来る
次代の若者達にぜひ引き継いで欲しい。 70代女性
会津塗の器をもってます。
お盆などつい粗末に大事に使用してなくて反省してます。
時代の進化をつくづく感じました。
この様な映像を大事に伝える大事さを感じました。 70代女性
細かな工程を経て生まれる器(木工芸)にとても感動しました。
また、山間地での木地師の移動と山と一体化した小屋造りに
変わってゆくもののはかなさを感じました。 70代男性
木工芸の製作法を改めて認識しました。
今後は津軽三味線の記録映画も上映して欲しいです。 70代男性
自然にあるもので小屋を作る技術、
それを受け継ぎ作り上げていけたことに驚きました。
その小屋を作っていた人々が木地師ではなく、
里の人々、いろんなことがつながって結びついて
成り立っていたのだなと感じた。
何年もかけて育つ気の美しさ、貴重さ、改めて感じた。 70代女性
2作品ともすばらしい。
この先も木工芸が発展することを願っています。
ため息が出るほどステキな上映ありがとうございました。
沖縄の琉球松の木目も大好きで毎年沖展での作品も楽しみなんです。
木工芸、あたたかみがありいいですね。
木がずっと生きているのワードにも感動しました。 70代女性
木が新たな生命を頂いて
私達に語りかけてくれている事に
感激致しました。
又、次回楽しみにしています。 70代女性
人間ってすごいの一言に尽きる。
子ども達に鑑賞の機会を与えて欲しい。 70代女性
木工の世界、素晴らしかったです。
お椀や器が木という素材からこんなふうにして
食卓に上がるのかと興味深く観ました。
多くの人の時間と手間と力が込められているのですね。
両方ともとても良かったです。感動しました。 70代女性
手造りの貴重な宝であることを知らされました。 70代男性
2つ合わせてとてもよかったです。 70代男性
素晴らしい作品でした。
木地師、木工芸師の強い想いが伝わりました。
有難うございます! 70代男性
毎回感動のみ。
次回楽しみにしています。 70代女性
奥会津の木地師の生活をしている人々の姿に
ただ口をポカンと開けて見入っていました。
溜め生きではなく、体の中から出てくる
空気の声みたいなものが出ました。
生活の技、いや、人間の至高の技か。
ただただ口をポカンと開けて見ました。
素晴らしい映画でした。 70代女性
木の器を作る厳しさを教えられました。
これまでとは違った目で見ることと思う。
そして愛おしさが増すことでしょう。 80代女性
作品名、木の生命よみがえる。
幼木から老木、そして見事なうるし、感動しました。 90代女性
木工芸の工程、おもしろかったです。
名木が木工芸として器となり
人々に使われ
まさしく生命がよみがえるようでした。
〈5月会を振り返って〉
「海燕社の小さな映画会2024」5月会。
ご鑑賞の59名のお客様、ありがとうございました。
作品上映を快く了承して下さいました「民族映像文化研究所」様、
「ポーラ伝統文化振興財団」様、「桜映画社」様、ありがとうございました。
会場「沖縄県立博物館美術館」様、ありがとうございました。
後援の「沖縄県」「那覇市」「ポーラ伝統文化振興財団」様、ありがとうございました。
宣伝にご協力下さいましたマスコミのみなさま、ありがとうございました。
SNSや口コミで宣伝下さいましたみなさま、ありがとうございました。
みなさまに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
海燕社の小さな映画会は海燕社が「観たい」「観て欲しい」映画を一緒に観ませんか、という
ゆるやかでたおやかな気持ちで開催している映画会です。
映画館ではなかなか上映されない映画を選んでいます。
映画の多様性、特にドキュメンタリーの幅広さを知ってもらいたいという気持ちがあります。
2024年の映画会は10年目を記念してご鑑賞者にオリジナル「栞」をプレゼントしています。
4月会は「獅子」5月会は「木」…上映作品に合わせてテーマを決めてデザインしています。
「栞」にしたのは、私が映画を観た後、原作本や関連する本を読みたくなるからです。
映画会の思い出とともに読書の友として「栞」を使ってもらえたらと思います。
「海燕社の小さな映画会2024」の5月会は、
『奥会津の木地師 福島県田島町針生 』(民族文化映像研究所 ) と『木の生命よみがえる 川北良造の木工芸 』(ポーラ伝統文化振興財団/桜映画社)の二作品を上映しました。
『奥会津の木地師』はアンコール上映です。はじめてみたときの衝撃が忘れられません。木地師が山で切り倒した木からその場で碗の形の塊を削り掘り出す。その塊を素手や素足で掴みそこに刃物を振り下ろし更に削りこむ。圧巻のシーンです。何度観てもその技の見事さにただただ感嘆します。テスト試写も含めると何度も観ているこの作品。今回はちょっとしたシーンにも目が向きました。その一つが、木地師の銜えたばこ。かっこいい。私が幼い頃はよくみかけた大人の男の人の姿です。故野村岳也監督もかつて銜えたばこで16ミリフィルム編集していたこともなつかしく思い出されました。
『木の生命よみがえる-川北良造の木工芸-』は沖縄初上映です。旋盤の技。その美しさに魅了されます。回転とともに表れる器の形と削り出る木くず。どれも愛おしい。川北さんが、器となる部位と木くずになる部位、残る材と残されない材、両方への想いを語られていて共感しました。映像制作も同じだからです。撮影時、編集時、悩みます。選んだこと、選ばなかったこと、どちらにも想いがあります。また鑑賞中、沖縄の琉球漆器を想っていました。今、浦添美術館に行きたくなっています。5月会の2作品は、木を通して、自然の貴さ、手で、足で、体で…自ら生み出すことの貴さ、そして、人と人、自然と人が助け合う貴さ、を教えてくれたように思います。
映像作品は完成後が大事だと思っています。
製作者としては観てもらうこと、観客としては観ること、
その二つを映画に贈りたいです。
「海燕社の小さな映画会」はその一役になって欲しいと願っています。
アンケートの提出して下さった52名様に感謝申し上げます。
アンケートのご協力ありがとうございました。
感想を書いて下さったのは48名様。感想ブログ掲載不可は4名様。
44名のお客様の感想を上記で紹介させて頂きました。
ブログでのお客様全員の感想を紹介する活動を続けています。
海燕社のスタッフだけで読むには惜しい内容の感想ばかりだからです。
映画会に来て下さった皆様と感想を共有したい、
映画製作者のみなさまにお客様の感想を伝えたい、
映画会に来れなかったみなさまに作品について伝えたい、
という思いで感想をブログで紹介しています。
これからも続けます。ご協力をよろしくお願いします。
城間あさみ
Posted by カイエンシャ at
10:12
│海燕社の小さな映画会