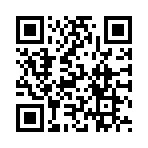2024年12月06日
「海燕社の小さな映画会2024 11月会」『武州藍』『芭蕉布を織る女たち-連帯の手わざ-』
海燕社の小さな映画会2024 11月会
【2024.11.17(日)/沖縄県立博物館・美術館3階講堂
13:15受付開場/14:00開会/15:30終了】
鑑賞料:無料(要予約)
沖縄県立博物館・美術館 特別展『芭蕉布展』×海燕社の小さな映画会2024 コラボ企画
〈上映作品〉
『武州藍』
(1986年製作/民族文化映像研究所 製作/43分)
『芭蕉布を織る女たち-連帯の手わざ-』
(1981年製作/ポーラ伝統文化振興財団製作/桜映画社 村山英治監督/30分)
〈入場まで〉
1.受付:①10周年記念栞進呈
②資料配布
2.手指アルコール消毒(各自任意:劇場入口設置)
3.入場着席:自由席
※配布資料
(チラシ2枚、アンケート用紙、案内カード、下敷き、クリアファイル、鉛筆)
<プログラム>
1.開会
2.主催挨拶(城間あさみ)
3.『武州藍』(1986年/民族文化映像研究所製作/43分)
4.『芭蕉布を織る女たち-連帯の手わざ-』
(1981年/ポーラ伝統文化振興財団製作/桜映画社 村山英治監督/30分)
5.アンケート記入
6.閉会
<スタッフ> 5人(海燕社2人、アルバイトスタッフ2人、映写スタッフ1人)
準備・片付け:全スタッフ
受付会場全体総括(海燕社2人)
受付:(アルバイトスタッフ2名)
上映:(映写スタッフ)
司会:(城間あさみ)
〈後援〉沖縄県/那覇市
【お客様の感想(アンケートより)】
だいぶ着物姿も見れなくなりましたね。
芭蕉布を続けてほしいです。
大変なお仕事ですね。
頭が下がります。
頑張って下さい。 女性
埼玉での藍は、疲れたとき、清酒を入れていたが、
沖縄では、泡盛を使用していた。正に藍づくりは、
地域に根ざしているものだと感じた。 10代男性
今まで藍染めや芭蕉布について全然しらなかったけれども、
今回の映画会を通してとても興味が湧きました。 10代女性
「武州藍」と「芭蕉布を織る女たち」
どちらも歴史ある職人の技という印象をうけて、
それをこのような映像にのこして、今の私たちでも
見ることができ伝えられているのがとても良いことだと思い、
昔の人の努力やよく考えられた技術が伝わってきました。
また、芭蕉布で藍が出てきたのも、前に観れていたのも
関係性がよく知れて良かったです。 10代男性
今回の映画会は、
大学の課題の内の一つにあり、興味を持ったので観にきました。
昔の映像と共に藍の作り方使い方を知れてよかったです。
特に、藍が団子になっているものや、
藍で染めた織物を作っているのも初めて知って驚きました。 10代男性
昔ながらの伝統を引き継いで協力している姿に感動した。
藍は生きているということを感じられた。 20代女性
芭蕉布展とのコラボ企画ありがとうございました。
布の背景にある生活の息づかいを感じさせる映像を
これだけたくさんの人にみてもらえて嬉しいです。 20代女性
面白いです。
よく芭蕉と藍染のことを知った。 20代女性
このタイミングで藍と合わせての上映、大変良かったです。 20代女性
映像で見たことで、芭蕉布づくりの大変さを感じることができた。
これから芭蕉布展に行こうと思うので、事前に詳しくなれてよかった。 20代男性
何工程もかけて作る職人の思いというものが
よく伝わる良い映画だったと思います。 20代男性
とても興味深い内容で良い学びになりました。 20代男性
身近にある染物が作成される過程には
農耕の知恵や工夫が詰められており、
農家、染物職人、織物職人、
様々な人の苦労や努力が知れて勉強になった。 20代男性
先人達の知恵や工夫を沢山知ることができて良かった。 20代男性
藍や芭蕉布について今まで知らなかったので、とても興味深かったです。
もしアンコール上映があればまた観たいと思いました。 20代女性
芭蕉布が出来るまでの工程の多さ、複雑さに驚きました。
こういうものにお金を出したいと思いました。
芭蕉布を購入できる機会があれば、是非購入させて頂きます。
戦争中での辛い記憶も乗り越え、喜如嘉の芭蕉布を守ってくださった
平良さんと喜如嘉の女性方のおかげで、無形文化財にも選ばれ、
彼女たちにとっては日常の一部かもしれませんが
沖縄に大きな貢献をされており、素晴らしいと思うと共に、
もっと知られてほしいと思いました。
このような機会がなければ知ることができなかったので、
もっと大衆的に知ってもらえるようなきっかけが必要だと思いました。
この度は素敵な上映会をありがとうございました。 20代女性
武州藍と芭蕉布の2本立てで観ましたが、
日本、沖縄の農耕文化に根差した手仕事に感動します。
植物の栽培の過程から、染め織物につくり上げていくまでの
全体をつかむのにとてもいい教材でもあると思います。
定期的に見直したい映像作品と感じます。 30代男性
藍と芭蕉布あわせて観ることができてよかったです。
とても良い企画でした。
芭蕉布展の案内もありがとうございました。 30代女性
芭蕉布を作るためにあれだけの手順と
手間があったことにおどろきました。
沖縄の伝統として残してくれたことに感謝します。 30代女性
藍はどの地域でも‶生き物‶として扱っていて興味深かったです。
また、芭蕉布(布)になるまでの工程が多く、
手間が掛かっているからこそ
触れた時にあたたかみを感じるのだと思いました。 30代女性
藍染も芭蕉布も存在は知っていたが
その製造過程は知らなかったので、今回映像で見ることで
複雑かつ繊細な工程を知ることができました。
いずれも手間暇かかった細かい手作業で、
その技術を絶やさぬよう取り組まれた方々に敬意を抱きます。
変わっていくもの、変わらないもの、人の価値感もそれぞれですが、
伝統というものは絶えず残って欲しいと思いました。 30代女性
喜如嘉の女性の美しさを感じました。
暮らしのなかに仕事があって、
自然のなかで人が生きているという感じがしました。
誰と競うでもなく、自らの手で、そして
地域社会の和のなかで生きる幸せを、
現代や将来の社会でも引き継いでいけたらと思います。 30代男性
貴重な映像が観れて、とても嬉しいです。
県外の工芸になかなか触れる機会がなかったので
埼玉の藍について学べて良かったです。
芭蕉は、昔と今の様子を照らし合わせて見ました。
また、改めて、機会があれば観たいです。
何度観ても学べる映画でした。
ありがとうございました! 30代女性
内容もとても勉強になりました。
スタッフの方も丁寧に案内して下さり、
チラシも集落内いたるところで拝見して良かったです。
次回の上映をとても楽しみにしています。
できれば、北部での上映会も企画して下さることを望みます。 40代女性
「武州藍」の職人さん方の手仕事にほれぼれしました。
工程ごとのこだわり、
藍を生き物として大切に向き合う姿に感動しました。
喜如嘉の女性たちのきずな、
村で大切にされている共同作業の様子がすばらしかった。
人の想いやくらしが織りこまれ編まれた布だと思いました。
平良敏子さんのお若い頃の姿を拝見できるだけで胸がいっぱいになりました。 40代女性
素晴らしい上映会でした。
古い撮影でも沖縄の伝統工芸や
それに関するテーマの映画を上映し続けて下さい。 40代男性
芭蕉布がたくさんの人の手によってつくられ、
またたくさんの人を支える存在だったのかなと思い、
その美しさの理由のひとつを見た気がしました。
どちらも貴重な資料映像で、見られてありがたいです。 40代女性
貴重な映像を見せていただき、大変勉強になりました。
その時代の風景や服装などとてもおもしろかったです。 40代女性
藍、芭蕉布と作り手の「想い」を学ばせていただきました。
しっかり心に刻みたいと思います。
貴重な映像をありがとうございました。 40代男性
すばらしく良い時間でした。
今後も楽しみにしています。続けてがんばって下さい。
他の沖縄のディープをクローズアップ楽しみにしています。 40代男性
とても良かったです。
ありがとうございました。 40代男性
今日、はじめて参加、とても良かったです。
特別イベントの上映会にも感動しました。
「芭蕉布」が生きもののよううに見えてきました。
とても好きになりました。
芭蕉布がもっと身近なものになることを願っています。
ありがとう、又、上映会に参加したいです。
スタッフさんおつかれさまです。 40代女性
どちらの映像も当時のありのままの様子や風景
(武州藍のほうでは子供がちゃんちゃんこを着ていたり、
芭蕉布のほうでは昔の那覇バスターミナルが写っていたり)が
記録されていて、とてもなつかしくノルタルジーな気持ちを味わいました。
前回に引き続き貴重な映像をこの場にいる方々と同時に共有することができ
嬉しく思うと同時に感謝の気持ちでいっぱいです。
芭蕉布につきましては、平良敏子先生のありし日の姿を拝見することができ
リアルタイムでお会いすることができなかった私には
ありがたい機会となりました。今回もありがとうございました。 40代女性
藍も芭蕉布も手間が掛かるものとは思っていましたが
ここまで大変な作業とは知りませんでした。
これからも日本の伝統、沖縄の伝統として
守っていって頂きたいと思います。 50代女性
今年、大宜味村の喜如嘉芭蕉布会館へお邪魔しましたが
今回の映画ほど詳しく理解することができていなかったなと痛感。
当映画にてより理解が増しました。
もっと多くの上映機会があるといいと思います。 50代女性
平良敏子さん、すばらしい人ですね。
芭蕉布展からの流れで鑑賞しましたが、
とても感銘を受けました。
お手配してくれた沖縄の友人に感謝です。 50代女性
武州藍
藍染めの工程、文化を知る事ができて、勉強になりました。
「小禄クンジーも同様な文化だったのかな⁈」と、
小禄出身なので想いをはせました。
とても興味深い内容でした。
芭蕉布を織る女たち-連帯の手わざ-
芭蕉布展(沖縄県立博物館美術館)
風にゆられて芭蕉布ワンピース展(南風原町立南風原文化センター)
喜如嘉の芭蕉布展(沖縄芸大)
を楽しんだ後なので「本当に丁寧な手仕事で素晴らしい文化だなぁ、」と
改めて感じました。 50代女性
すばらしかった。平良敏子さんはすごい。 50代女性
芭蕉布のできるまでを部分では見たことがありますが、
ここまで詳しいのは初めてみました。
わかりやすくてよかったです。平良さん、お若いですね。
前に倉敷に旅行にいったとき、大原美術館(?)で
経緯を知り、感動しました。 50代女性
この様な複雑な技が
どうして開発されたのか、
見ていてとても不思議だった。 50代男性
鑑賞できてよかったです。
ありがとうございました。 50代女性
日本、沖縄の素晴らしい手仕事、
豊かな暮らしを観ることができてとても良かった。
日本人であることをほこりに思えた。
伝統的なものをもっと生活に取り入れたい。 50代女性
映像と解説で武州藍と喜如嘉の芭蕉布について
よく知ることがでいました。
すばらしい映画の上映会を催して下さって
ありがとうございました。 50代女性
大変感動しました。
沖芸大の方でも芭蕉布展をやっていて、
たまたまこちらでは映画の上映もあるという事で
参加させて頂きました。
普段、米国に住んでいるという事もあり、
中々、沖縄の文化にふれる機会は少ないですが
(NYCではJapanSocieyで組踊などは見た事がありますが)
ぜひ、この映画、そして展示会をNYCの方、アメリカの方でも
やって頂いて、沖縄のすばらしいテキスタイル文化を知ってもらいたいですね。
今回はこういう機会を頂けて感謝しております。 50代女性
県内に産まれ育っていてもなかなか沖縄(琉球)の文化財について
学ぶ機会がなく細かな事まで学ぶ事が出来る良い時間を頂けました。
芭蕉布は知っていましたが、大宜味村喜如嘉にいらっしゃる女性の方の力で
現在まで受け継がれている事がすごくすばらしくこれから先も
沖縄の貴重な文化財として大切に守られて欲しいと思いました。 50代女性
村のどこそこでいつも芭蕉布の糸を積む女性たちが
いた時代の映像を見ることができました。
現代の風景とは違いますが、
たしかに今につながっているんだと思いました。
ありがとうございました。 50代女性
入館が遅くなってしまい、終わり15分前の鑑賞になりました。
でも、芭蕉布を織るのに、また織った後の作業の多さに
力仕事とこまやかさも必要だということを知ることができ
こんどから芭蕉布を見る時その作業を思いうかべたいと思いました。 50代女性
私の母も与那国織をしていて、
子や孫のために反物を織り、プレゼントしてくれた。
でも、映画で紹介されていたような工程をへて
織物が完成することを知らずに私は60歳を
目前に控えている。こんな自分を恥と思う。
織物をやっている人達の苦労を知らずにいたことが恥。
そして、平良さんの芭蕉布を守った心に感動した。 50代女性
なつかしい沖縄の風景とともに
大宜味、喜如嘉で、芭蕉布を再生、後世へとつないで
下さった平良敏子さんの姿に感動しました。
強い思いでつづけてこられたのだとしみじみ感じました。
芭蕉布は、ひとつひとつ丁寧な工程のたまものだと思います。
沖縄のほこるべき宝です。
今年、たまたま奥州浴衣を購入しました。
藍染の長板の工程など知ることができました。
浴衣を大切にしたいと思います。 50代女性
とても貴重な映像をありがとうございました。
芭蕉布が糸~布になるまで、大変な手間ひま、ご苦労がわかり
そんな芭蕉にとても興味がもてました。 50代女性
喜如嘉の村に生活の一部として根づいている芭蕉布織り。
村の女性達が協力し合い、伝統を守り、布を織っている姿に感動した。
これからもぜひ守り引き継がれていってほしい。
2つの映画とも自然の植物を相手に、染め、糸づくり、布を織ることを
記録していて、こういう記録を残すことが、これからの世代へとバトンが
引き継がれていくのでとても大切だと思った。
このような機会をこれからも設けてほしい。 50代女性
芭蕉布がこんなに手間ひまのかかるものだとは知らずにいました。
たくさんの沖縄の人に観てほしい作品です。
平良敏子先生のおだやかな表情ときびきび働くお姿が
とても素晴らしく感動しました。
すばらしい作品だと思います。ありがとうございました。 50代女性
藍、芭蕉布ともに良かったです。
藍は、種まきから染めまで見る事ができてよかったです。
芭蕉布は糸づくりから仕上げ、普段の生活の様子も見る事が
できてわかりやすかったです。平良先生、美恵子さん、お若い!
年をとっても、もの作りをする方々はお元気で輝いてすてきです。
先週の水害が心配ですが、どうかこの光景がずっと続くことを願います。 50代女性
武州が藍の産地ということは、大河ドラマを観て知ってはいましたが
実際どのように作られるのかは知りませんでした。
芭蕉もそうですが、まず植物を育てることからはじまって、
製品ができあがるまでにこんなに複雑な工程があり、たくさんの人々の手で
作られているのだということが、すごいと思いました。
今も、その技術は受け継がれているのでしょうか?
芭蕉布は高価でとても手に入れることはできませんが、
藍染の服は一着持っているので、
着るときには今回の映画を思いながら着ようと思いました。 50代女性
どちらの映像も、その土地に根付いた人々の営みとともに
栄えていった手仕事である事、そしてひとつひとつの作業の工程にかかる
手間ひま、難儀が、とても美しくどの作業も省略できない事が
私にはとても素晴らしく映りました。
武州藍も芭蕉布もどちらも(藍を育てていく、糸芭蕉を育てていくなど)
長い時間をかけて作られている事を改めて知る事ができて大変貴重な時間でした。
織りも染めもやはり祈りと希望がいつもそこに存在し、
作り手の方々の生きる喜びが共にあると強く感じました。
ありがとうございました。 50代女性
武州藍
藍染めの奥深さ、工程の細やかな作業を、初めて知ることができました。
泡のぶくぶくした状態になるまでには、数々の工程があるのですね。
職人さんの藍色に染まった手が格好よかったです。
芭蕉布を織る女たち
平良敏子さんの若かりし頃の映像を見るにたくましさをひしひしと感じました。
長く重い芭蕉布を、たらいでじゃぶじゃぶ洗う姿に
足腰の強さを感じずにはいられませんでした。
あの小さな体からあふれ出るパワーが
しっかり引き継がれていくことを心から願っています。
このようなすばらしいドキュメンタリー2本を
無料で鑑賞させていただきありがとうございました。 50代女性
とても勉強になりました。
ありがとうございました。 60代女性
芭蕉布は戦前、県内各地に在り、多くの担い手がいた。
戦後、喜如嘉だけがその伝統を守り存続したのは
平良敏子さんの力によるものだろう。
その想いはどこから来るものだろう。
喜如嘉の風土の力か。 60代男性
神奈川から来沖している友人を案内して参加。
芭蕉布展も観て、とても感銘したようだ。お連れできてよかった。
私も何度も観せていただいているが、次回の「むんじゅう笠」は
DVDを持っているので今回はパスします。 60代女性
衣料品の大量廃棄などが問題になっている
今だからこそ、ていねいな物づくりは
重要で必要になのだと感じました。 60代女性
もっと多くの方に観て頂きたいと思える素敵な映画だと思います。
今回、二度目でしたが、次の機会があれば又観に来ます。
ありがとうございました。 60代女性
藍について昔からの作り方、染め方、大変参考になった。
芭蕉布 制作工程はもちろん、
沖縄の昔ながらの民家や生活感がとても見れた事が良かった。 60代女性
大雨の中、まよいながら来たのだが
とても心おだやかで美しい作品でした。
ありがとうございます。
喜如嘉へ行ってその風を感じたい。
藍染は男の仕事なんだと思った。 60代女性
平良敏子が亡くなったのは残念です。
後継者が多数いることを願います。
武州藍を初めて知りましたが、とても素晴らしい芸術品ですね。
職人の知恵と技にただただ感心しました。 60代男性
「武州藍」の途中からしか鑑賞できなかったので
もう一度別の機会に上映してほしい。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
毎回見たいと思いました。 60代女性
素晴らしい映画上映をありがとうございました。
平良さんは御自分の使命をまっとうされたのだなぁと感じました。
喜如嘉の芭蕉布が一人の人の想いから
亡ばずに本当に良かったと思いました。
大原様に感謝です。
喜如嘉の芭蕉布を守り、生かしてくださったことに感謝です。
又、アンコール上映されることを願います。 60代女性
芭蕉布を織るのに手数がかかるというのは聞いていたが
これほどだと初めて知る。戦争やいろいろなことで
ほとんどすたれてしまったものが、喜如嘉でまた復興したというのは
ほんとうに奇跡で岡山の紡績工場の社長さんや柳宗悦さんには感謝である。
人間国宝にまでなった平良敏子さんの人となりと今に受け継がれるいしずえと
なった歩みがこの映画を見て知れてほんとうに有意義な時間でした。 60代女性
芭蕉布を守って育てた人々(女性)の生き様に大変感謝しました。 60代男性
昔の人のすばらしさにほんとうにカンプクの一言。
これからもいろいろなものをみてみたいです。 60代女性
平良さんには、ただただ頭が下がる思いです。 60代男性
芭蕉布作り、いろいろ手間などかけていて、すばらしい。
次世代の人々につないでほしい。又、県はもちろん
国などで代々守って欲しい。
武州藍、たくさんの人々の過程、手をかりて、すばらしい。
藍染めができて、すばらしい。これも日本の藍として守ってほしい。
ありがとうございます。 60代女性
喜如嘉にある芭蕉と木灰とシャリンバイから糸が生まれ
紡がれ織られ布になる。生産性向上や付加価値や品質管理はここにない。
あるのは、生活と連帯と感謝。
現代の日本がどこかに置いてきたものがここには全てある。 70代男性
見たい映画たくさんあります。 70代女性
良かったです。 70代男性
時間と労力をかけて紡がれる織の世界。
いつまでも継がれる事を祈るばかり。
平良敏子さんの情熱と村への思いを伝える上映でした。 70代女性
良かったです。
とくに「芭蕉布を織る女たち」は
観ているうちに涙が出てきました。 70代女性
宴会の余興等で着るぐらいしか機会のない芭蕉布でしたが
こんなにも手間ひまかけて布に織りあがるのだと初めて知りました。
ものすごく貴重な布なのですね。
芭蕉の木から布に織りあがるまでの過程がよくわかり感動しました。 70代男性
多くの方の協力で素晴らしい作品が生れてるのがわかりました。 70代女性
たいへん良い映画をありがとうございます。 70代男性
細かい作業や作品が一人一人の思いによって
できあがることを知ってよかたです。 70代女性
手仕事のすばらしさ、作品をみることができてよかったです。
ありがとうございました。 70代女性
若者へ
伝統の芭蕉布をつづける努力、
芭蕉布展をつづけてほしい。 70代男性
芭蕉布、藍染め、どちらもすばらしいですね!
生活の中に取り入れていきたいと思いました。
手間ひまのすごくかかった仕上げのもと
ステキな作品となるのですね。 70代女性
芭蕉布の工程については本も読んでおりましたので
ある程度は知っている心算でしたが、複雑で、気の遠くなるような工程は
予想を遥かに超えていました。このことは、武州藍についても同様です。
ただ、年月日も知りたかったです。
平良敏子さんの若いお姿は何歳位だったのでしょうか。 70代女性
[質問の回答]平良敏子さんの年齢について
平良敏子さんは1921年生まれのようです。『芭蕉布を織る女たち』の
製作年が1981年ですので、59才か60才だと思います。
芭蕉も藍も沢山の工程を経るのですね。
それを苦労っぽくなく、こなして楽しそうにやっていることがすごい。 70代女性
良かったです。
芭蕉布の値段が高いのがわかります。 70代女性
大変すばらしい映画でした。感動です。
喜如嘉の方々、芭蕉布作りを映像でみることが出来
また、映画を作ってくれたことに大変すばらしく、すばらしいことです。
平良敏子さん、芭蕉布をしている方々、とにかくすごいと思います。
上映会に来ることが出来、勉強になりました。ありがとうございます。 70代女性
自然と共に生きる、先人の知恵、
相手とじっくり付き合いながら、ひとつの物を作りあげていくことの喜び
今の時代に大切な事を教えてくれる作品でした。
感動しました。ありがとうございます。 70代女性
「芭蕉布を織る女たち」は以前にも見ましたが
「武州藍」は初めてで、藍の種をまくところから
藍染めができるまで詳しく工程が分かって良かった。
藍は沖縄では日かげか半日かげで栽培されていると聞いているが
日なたで育てているので驚いた。
沖縄の藍と違うのだろうか。 70代女性
[質問の回答]リュウキュウアイは日かげを好みますね。
藍の種類によって違うようです。武州藍のタデアイは
日光を好み日当たりのよい場所で育ててましたね。
武州藍、芭蕉布も、ひとつひとつの工程が
きちんとていねいに行われて布が完成していることがすばらしく、
生活の場と密着していることがよく映像化されていると感じました。
特に喜如嘉の女性達の生き生きとした姿が印象に残った。
今も喜如嘉にひきつがれていると感じる。 70代女性
とても大変なお仕事だと、ご苦労をおもいました。
現代においてずっと続けていく事は困難な作業だと思います。
記録を残すことがどんなに重要なことか、特に映像の力が大きいと思います。 70代女性
11/2に芸大で平良美恵子先生のお話を聞き
芭蕉布の事を初めて知り(県外人なので)映画も初めて見たのですが
びっくりする事ばかりでした。博物館のチラシで平良先生のお話しや
映画会がある事を知り、11/16、11/17と2日は博物館に来ました。
本当に皆さん苦労して文化をつないでこられたのだと頭が下がります。 70代女性
いづれにも共通する事だが
手間ひまが掛かり頭がさがる。
着物が好きで購入もするが、
琉球の伝統工芸は高額で手が出ない。
工程を知ってしまうと納得なのだが… 70代女性
感動致しました。 70代女性
すばらしい映画でした。 70代男性
今回の映画会は大変良かった。
芭蕉布の出来上がり、歴史の重みを感じました。
これからも小さな映画会がますます大きな映画会になりますように。
ありがとうございました。 80代男性
毎回、新たな感動を得ます。
手作業、伝統の奥深さを有難く見せてもらっています。
ありがとうございます。 80代女性
大変すばらしい。
沖縄の世界にほこる、すばらしいと思います。
「バショウ」の衣は、良い物です。
無地でバショウを作り、後であやを入れたらどうかと思いました。 80代男性
芭蕉布が布になるまですごい工程ですね。
昔の年配の人は、着物や洋服で着けていたのを思い出します。
祖母もバサーを洗たくする時は、クニブ(みかん)で洗ってました。
みかんで洗うとそれはきれいに鮮明に汚れも落ちていました。 80代女性
1.2編共大変良かった。
1本づつ上映した方が良かったのではないか。
2.取材時期が分からなかったが、最後に入れるべきと考える。
3.「芭蕉布を織る女たち」では、一着尺にどの程度の芭蕉布が使われ
どの位の時間がかかり、最終的にいくら位で取引されるのかが知りたかった。 80代男性
工芸の素晴らしさを再確認しました。
大変勉強になりました。 80代女性
・知識を広めるためとてもよかったと思います。
・手仕事のきびしさがわかった。
・奥深いきびしさがあることがわかった。 80代女性
こんなに素晴らしい映画を見ることが出来たのは
生涯忘れることが出来ない程感激した。反省するのみ。
平良先生を常に念頭に置き、残された時間を大切に生きたいと思いました。
先生を中心に織られた方達皆さんの
生き(活き)生きした姿をみることができたのも良かったです。 80代女性
芭蕉布工房で若い頃の敏子、美恵子さんのなつかしいお姿。
伝統を守ることのむずかしさ、受け継がれるのも御苦労様です。 80代男性
気の遠くなる程の過程を経て、出来上がる芭蕉布。
根気と愛で出来る布。永らく継承できる事を祈る。 90代女性
〈11月会を振り返って〉
「海燕社の小さな映画会2024」11月会、
ご鑑賞の143名のお客様、ありがとうございました。
「ポーラ伝統文化振興財団」様、「桜映画社」様、ありがとうございました。
「民族文化映像研究所」様、ありがとうございました。
11月会は沖縄県立博物館美術館『芭蕉布展』とのコラボ上映会が実現しました。
おかげさまでお客様に映画を無料でご鑑賞頂けることができました。
「沖縄県立博物館美術館」様、ありがとうございました。
後援の「沖縄県」「那覇市」様、ありがとうございました。
宣伝にご協力下さいましたマスコミのみなさま、ありがとうございました。
SNSや口コミで宣伝下さいましたみなさま、ありがとうございました。
みなさまに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
海燕社の小さな映画会は海燕社が「観たい」「観て欲しい」映画を
一緒に観ませんか、というスタンスで開催している映画会です。
劇場ではなかなか上映されない映像作品や旧作映画を上映しています。
映画の多様性、特にドキュメンタリーの幅広さを知ってもらいたいという気持ちもあります。
2024年の映画会は10年目を記念してご鑑賞者にオリジナル「栞」をプレゼントしています。
4月会は「獅子」5月会は「木」…上映作品に合わせてテーマを決めてデザインしています。
記念品を「栞」にしたのは、私が映画を観る前や観た後に原作本や関連する本を読みたくなるからです。
映画会の思い出とともに読書の時に「栞」を愛用して頂けたらうれしいです。
「海燕社の小さな映画会2024」の11月会は、
『武州藍』『芭蕉布を織る女たち-連帯の手わざ-』(以下『芭蕉布の織る女たち』)の二作品を上映しました。
沖縄初上映作品『武州藍』とアンコール3回目上映作品『芭蕉布を織る女たち』
この二本立を企画した理由を主催者挨拶で話しました。
きっかけは『芭蕉布を織る女たち』です。この作品で私が印象に残った言葉が「藍の花」です。
藍を、花のように見る、人のように思いやる、そこに惹かれました。
藍と藍をつなぐ上映会をしたいと『武州藍』と『芭蕉布を織る女たち』の二本立を決めました。
映像作品は完成後が大事だと思っています。
製作者としては観てもらうこと、観客としては観ること、
その二つを映画に贈りたいです。
「海燕社の小さな映画会」はその一役になって欲しいと願っています。
アンケートの提出して下さった139名様に感謝申し上げます。
アンケートのご協力ありがとうございました。
感想を書いて下さったのは120名様。感想ブログ掲載不可は15名様。
105名のお客様の感想を上記で紹介させて頂きました。
ブログでのお客様全員の感想を紹介する活動を続けています。
海燕社のスタッフだけで読むには惜しい内容の感想ばかりだからです。
映画会に来て下さった皆様と感想を共有したい、
映画製作者のみなさまにお客様の感想を伝えたい、
映画会に来れなかったみなさまに作品について伝えたい、
という思いで感想をブログで紹介しています。
これからも続けます。ご協力をよろしくお願いします。
城間あさみ
【2024.11.17(日)/沖縄県立博物館・美術館3階講堂
13:15受付開場/14:00開会/15:30終了】
鑑賞料:無料(要予約)
沖縄県立博物館・美術館 特別展『芭蕉布展』×海燕社の小さな映画会2024 コラボ企画
〈上映作品〉
『武州藍』
(1986年製作/民族文化映像研究所 製作/43分)
『芭蕉布を織る女たち-連帯の手わざ-』
(1981年製作/ポーラ伝統文化振興財団製作/桜映画社 村山英治監督/30分)
〈入場まで〉
1.受付:①10周年記念栞進呈
②資料配布
2.手指アルコール消毒(各自任意:劇場入口設置)
3.入場着席:自由席
※配布資料
(チラシ2枚、アンケート用紙、案内カード、下敷き、クリアファイル、鉛筆)
<プログラム>
1.開会
2.主催挨拶(城間あさみ)
3.『武州藍』(1986年/民族文化映像研究所製作/43分)
4.『芭蕉布を織る女たち-連帯の手わざ-』
(1981年/ポーラ伝統文化振興財団製作/桜映画社 村山英治監督/30分)
5.アンケート記入
6.閉会
<スタッフ> 5人(海燕社2人、アルバイトスタッフ2人、映写スタッフ1人)
準備・片付け:全スタッフ
受付会場全体総括(海燕社2人)
受付:(アルバイトスタッフ2名)
上映:(映写スタッフ)
司会:(城間あさみ)
〈後援〉沖縄県/那覇市
【お客様の感想(アンケートより)】
だいぶ着物姿も見れなくなりましたね。
芭蕉布を続けてほしいです。
大変なお仕事ですね。
頭が下がります。
頑張って下さい。 女性
埼玉での藍は、疲れたとき、清酒を入れていたが、
沖縄では、泡盛を使用していた。正に藍づくりは、
地域に根ざしているものだと感じた。 10代男性
今まで藍染めや芭蕉布について全然しらなかったけれども、
今回の映画会を通してとても興味が湧きました。 10代女性
「武州藍」と「芭蕉布を織る女たち」
どちらも歴史ある職人の技という印象をうけて、
それをこのような映像にのこして、今の私たちでも
見ることができ伝えられているのがとても良いことだと思い、
昔の人の努力やよく考えられた技術が伝わってきました。
また、芭蕉布で藍が出てきたのも、前に観れていたのも
関係性がよく知れて良かったです。 10代男性
今回の映画会は、
大学の課題の内の一つにあり、興味を持ったので観にきました。
昔の映像と共に藍の作り方使い方を知れてよかったです。
特に、藍が団子になっているものや、
藍で染めた織物を作っているのも初めて知って驚きました。 10代男性
昔ながらの伝統を引き継いで協力している姿に感動した。
藍は生きているということを感じられた。 20代女性
芭蕉布展とのコラボ企画ありがとうございました。
布の背景にある生活の息づかいを感じさせる映像を
これだけたくさんの人にみてもらえて嬉しいです。 20代女性
面白いです。
よく芭蕉と藍染のことを知った。 20代女性
このタイミングで藍と合わせての上映、大変良かったです。 20代女性
映像で見たことで、芭蕉布づくりの大変さを感じることができた。
これから芭蕉布展に行こうと思うので、事前に詳しくなれてよかった。 20代男性
何工程もかけて作る職人の思いというものが
よく伝わる良い映画だったと思います。 20代男性
とても興味深い内容で良い学びになりました。 20代男性
身近にある染物が作成される過程には
農耕の知恵や工夫が詰められており、
農家、染物職人、織物職人、
様々な人の苦労や努力が知れて勉強になった。 20代男性
先人達の知恵や工夫を沢山知ることができて良かった。 20代男性
藍や芭蕉布について今まで知らなかったので、とても興味深かったです。
もしアンコール上映があればまた観たいと思いました。 20代女性
芭蕉布が出来るまでの工程の多さ、複雑さに驚きました。
こういうものにお金を出したいと思いました。
芭蕉布を購入できる機会があれば、是非購入させて頂きます。
戦争中での辛い記憶も乗り越え、喜如嘉の芭蕉布を守ってくださった
平良さんと喜如嘉の女性方のおかげで、無形文化財にも選ばれ、
彼女たちにとっては日常の一部かもしれませんが
沖縄に大きな貢献をされており、素晴らしいと思うと共に、
もっと知られてほしいと思いました。
このような機会がなければ知ることができなかったので、
もっと大衆的に知ってもらえるようなきっかけが必要だと思いました。
この度は素敵な上映会をありがとうございました。 20代女性
武州藍と芭蕉布の2本立てで観ましたが、
日本、沖縄の農耕文化に根差した手仕事に感動します。
植物の栽培の過程から、染め織物につくり上げていくまでの
全体をつかむのにとてもいい教材でもあると思います。
定期的に見直したい映像作品と感じます。 30代男性
藍と芭蕉布あわせて観ることができてよかったです。
とても良い企画でした。
芭蕉布展の案内もありがとうございました。 30代女性
芭蕉布を作るためにあれだけの手順と
手間があったことにおどろきました。
沖縄の伝統として残してくれたことに感謝します。 30代女性
藍はどの地域でも‶生き物‶として扱っていて興味深かったです。
また、芭蕉布(布)になるまでの工程が多く、
手間が掛かっているからこそ
触れた時にあたたかみを感じるのだと思いました。 30代女性
藍染も芭蕉布も存在は知っていたが
その製造過程は知らなかったので、今回映像で見ることで
複雑かつ繊細な工程を知ることができました。
いずれも手間暇かかった細かい手作業で、
その技術を絶やさぬよう取り組まれた方々に敬意を抱きます。
変わっていくもの、変わらないもの、人の価値感もそれぞれですが、
伝統というものは絶えず残って欲しいと思いました。 30代女性
喜如嘉の女性の美しさを感じました。
暮らしのなかに仕事があって、
自然のなかで人が生きているという感じがしました。
誰と競うでもなく、自らの手で、そして
地域社会の和のなかで生きる幸せを、
現代や将来の社会でも引き継いでいけたらと思います。 30代男性
貴重な映像が観れて、とても嬉しいです。
県外の工芸になかなか触れる機会がなかったので
埼玉の藍について学べて良かったです。
芭蕉は、昔と今の様子を照らし合わせて見ました。
また、改めて、機会があれば観たいです。
何度観ても学べる映画でした。
ありがとうございました! 30代女性
内容もとても勉強になりました。
スタッフの方も丁寧に案内して下さり、
チラシも集落内いたるところで拝見して良かったです。
次回の上映をとても楽しみにしています。
できれば、北部での上映会も企画して下さることを望みます。 40代女性
「武州藍」の職人さん方の手仕事にほれぼれしました。
工程ごとのこだわり、
藍を生き物として大切に向き合う姿に感動しました。
喜如嘉の女性たちのきずな、
村で大切にされている共同作業の様子がすばらしかった。
人の想いやくらしが織りこまれ編まれた布だと思いました。
平良敏子さんのお若い頃の姿を拝見できるだけで胸がいっぱいになりました。 40代女性
素晴らしい上映会でした。
古い撮影でも沖縄の伝統工芸や
それに関するテーマの映画を上映し続けて下さい。 40代男性
芭蕉布がたくさんの人の手によってつくられ、
またたくさんの人を支える存在だったのかなと思い、
その美しさの理由のひとつを見た気がしました。
どちらも貴重な資料映像で、見られてありがたいです。 40代女性
貴重な映像を見せていただき、大変勉強になりました。
その時代の風景や服装などとてもおもしろかったです。 40代女性
藍、芭蕉布と作り手の「想い」を学ばせていただきました。
しっかり心に刻みたいと思います。
貴重な映像をありがとうございました。 40代男性
すばらしく良い時間でした。
今後も楽しみにしています。続けてがんばって下さい。
他の沖縄のディープをクローズアップ楽しみにしています。 40代男性
とても良かったです。
ありがとうございました。 40代男性
今日、はじめて参加、とても良かったです。
特別イベントの上映会にも感動しました。
「芭蕉布」が生きもののよううに見えてきました。
とても好きになりました。
芭蕉布がもっと身近なものになることを願っています。
ありがとう、又、上映会に参加したいです。
スタッフさんおつかれさまです。 40代女性
どちらの映像も当時のありのままの様子や風景
(武州藍のほうでは子供がちゃんちゃんこを着ていたり、
芭蕉布のほうでは昔の那覇バスターミナルが写っていたり)が
記録されていて、とてもなつかしくノルタルジーな気持ちを味わいました。
前回に引き続き貴重な映像をこの場にいる方々と同時に共有することができ
嬉しく思うと同時に感謝の気持ちでいっぱいです。
芭蕉布につきましては、平良敏子先生のありし日の姿を拝見することができ
リアルタイムでお会いすることができなかった私には
ありがたい機会となりました。今回もありがとうございました。 40代女性
藍も芭蕉布も手間が掛かるものとは思っていましたが
ここまで大変な作業とは知りませんでした。
これからも日本の伝統、沖縄の伝統として
守っていって頂きたいと思います。 50代女性
今年、大宜味村の喜如嘉芭蕉布会館へお邪魔しましたが
今回の映画ほど詳しく理解することができていなかったなと痛感。
当映画にてより理解が増しました。
もっと多くの上映機会があるといいと思います。 50代女性
平良敏子さん、すばらしい人ですね。
芭蕉布展からの流れで鑑賞しましたが、
とても感銘を受けました。
お手配してくれた沖縄の友人に感謝です。 50代女性
武州藍
藍染めの工程、文化を知る事ができて、勉強になりました。
「小禄クンジーも同様な文化だったのかな⁈」と、
小禄出身なので想いをはせました。
とても興味深い内容でした。
芭蕉布を織る女たち-連帯の手わざ-
芭蕉布展(沖縄県立博物館美術館)
風にゆられて芭蕉布ワンピース展(南風原町立南風原文化センター)
喜如嘉の芭蕉布展(沖縄芸大)
を楽しんだ後なので「本当に丁寧な手仕事で素晴らしい文化だなぁ、」と
改めて感じました。 50代女性
すばらしかった。平良敏子さんはすごい。 50代女性
芭蕉布のできるまでを部分では見たことがありますが、
ここまで詳しいのは初めてみました。
わかりやすくてよかったです。平良さん、お若いですね。
前に倉敷に旅行にいったとき、大原美術館(?)で
経緯を知り、感動しました。 50代女性
この様な複雑な技が
どうして開発されたのか、
見ていてとても不思議だった。 50代男性
鑑賞できてよかったです。
ありがとうございました。 50代女性
日本、沖縄の素晴らしい手仕事、
豊かな暮らしを観ることができてとても良かった。
日本人であることをほこりに思えた。
伝統的なものをもっと生活に取り入れたい。 50代女性
映像と解説で武州藍と喜如嘉の芭蕉布について
よく知ることがでいました。
すばらしい映画の上映会を催して下さって
ありがとうございました。 50代女性
大変感動しました。
沖芸大の方でも芭蕉布展をやっていて、
たまたまこちらでは映画の上映もあるという事で
参加させて頂きました。
普段、米国に住んでいるという事もあり、
中々、沖縄の文化にふれる機会は少ないですが
(NYCではJapanSocieyで組踊などは見た事がありますが)
ぜひ、この映画、そして展示会をNYCの方、アメリカの方でも
やって頂いて、沖縄のすばらしいテキスタイル文化を知ってもらいたいですね。
今回はこういう機会を頂けて感謝しております。 50代女性
県内に産まれ育っていてもなかなか沖縄(琉球)の文化財について
学ぶ機会がなく細かな事まで学ぶ事が出来る良い時間を頂けました。
芭蕉布は知っていましたが、大宜味村喜如嘉にいらっしゃる女性の方の力で
現在まで受け継がれている事がすごくすばらしくこれから先も
沖縄の貴重な文化財として大切に守られて欲しいと思いました。 50代女性
村のどこそこでいつも芭蕉布の糸を積む女性たちが
いた時代の映像を見ることができました。
現代の風景とは違いますが、
たしかに今につながっているんだと思いました。
ありがとうございました。 50代女性
入館が遅くなってしまい、終わり15分前の鑑賞になりました。
でも、芭蕉布を織るのに、また織った後の作業の多さに
力仕事とこまやかさも必要だということを知ることができ
こんどから芭蕉布を見る時その作業を思いうかべたいと思いました。 50代女性
私の母も与那国織をしていて、
子や孫のために反物を織り、プレゼントしてくれた。
でも、映画で紹介されていたような工程をへて
織物が完成することを知らずに私は60歳を
目前に控えている。こんな自分を恥と思う。
織物をやっている人達の苦労を知らずにいたことが恥。
そして、平良さんの芭蕉布を守った心に感動した。 50代女性
なつかしい沖縄の風景とともに
大宜味、喜如嘉で、芭蕉布を再生、後世へとつないで
下さった平良敏子さんの姿に感動しました。
強い思いでつづけてこられたのだとしみじみ感じました。
芭蕉布は、ひとつひとつ丁寧な工程のたまものだと思います。
沖縄のほこるべき宝です。
今年、たまたま奥州浴衣を購入しました。
藍染の長板の工程など知ることができました。
浴衣を大切にしたいと思います。 50代女性
とても貴重な映像をありがとうございました。
芭蕉布が糸~布になるまで、大変な手間ひま、ご苦労がわかり
そんな芭蕉にとても興味がもてました。 50代女性
喜如嘉の村に生活の一部として根づいている芭蕉布織り。
村の女性達が協力し合い、伝統を守り、布を織っている姿に感動した。
これからもぜひ守り引き継がれていってほしい。
2つの映画とも自然の植物を相手に、染め、糸づくり、布を織ることを
記録していて、こういう記録を残すことが、これからの世代へとバトンが
引き継がれていくのでとても大切だと思った。
このような機会をこれからも設けてほしい。 50代女性
芭蕉布がこんなに手間ひまのかかるものだとは知らずにいました。
たくさんの沖縄の人に観てほしい作品です。
平良敏子先生のおだやかな表情ときびきび働くお姿が
とても素晴らしく感動しました。
すばらしい作品だと思います。ありがとうございました。 50代女性
藍、芭蕉布ともに良かったです。
藍は、種まきから染めまで見る事ができてよかったです。
芭蕉布は糸づくりから仕上げ、普段の生活の様子も見る事が
できてわかりやすかったです。平良先生、美恵子さん、お若い!
年をとっても、もの作りをする方々はお元気で輝いてすてきです。
先週の水害が心配ですが、どうかこの光景がずっと続くことを願います。 50代女性
武州が藍の産地ということは、大河ドラマを観て知ってはいましたが
実際どのように作られるのかは知りませんでした。
芭蕉もそうですが、まず植物を育てることからはじまって、
製品ができあがるまでにこんなに複雑な工程があり、たくさんの人々の手で
作られているのだということが、すごいと思いました。
今も、その技術は受け継がれているのでしょうか?
芭蕉布は高価でとても手に入れることはできませんが、
藍染の服は一着持っているので、
着るときには今回の映画を思いながら着ようと思いました。 50代女性
どちらの映像も、その土地に根付いた人々の営みとともに
栄えていった手仕事である事、そしてひとつひとつの作業の工程にかかる
手間ひま、難儀が、とても美しくどの作業も省略できない事が
私にはとても素晴らしく映りました。
武州藍も芭蕉布もどちらも(藍を育てていく、糸芭蕉を育てていくなど)
長い時間をかけて作られている事を改めて知る事ができて大変貴重な時間でした。
織りも染めもやはり祈りと希望がいつもそこに存在し、
作り手の方々の生きる喜びが共にあると強く感じました。
ありがとうございました。 50代女性
武州藍
藍染めの奥深さ、工程の細やかな作業を、初めて知ることができました。
泡のぶくぶくした状態になるまでには、数々の工程があるのですね。
職人さんの藍色に染まった手が格好よかったです。
芭蕉布を織る女たち
平良敏子さんの若かりし頃の映像を見るにたくましさをひしひしと感じました。
長く重い芭蕉布を、たらいでじゃぶじゃぶ洗う姿に
足腰の強さを感じずにはいられませんでした。
あの小さな体からあふれ出るパワーが
しっかり引き継がれていくことを心から願っています。
このようなすばらしいドキュメンタリー2本を
無料で鑑賞させていただきありがとうございました。 50代女性
とても勉強になりました。
ありがとうございました。 60代女性
芭蕉布は戦前、県内各地に在り、多くの担い手がいた。
戦後、喜如嘉だけがその伝統を守り存続したのは
平良敏子さんの力によるものだろう。
その想いはどこから来るものだろう。
喜如嘉の風土の力か。 60代男性
神奈川から来沖している友人を案内して参加。
芭蕉布展も観て、とても感銘したようだ。お連れできてよかった。
私も何度も観せていただいているが、次回の「むんじゅう笠」は
DVDを持っているので今回はパスします。 60代女性
衣料品の大量廃棄などが問題になっている
今だからこそ、ていねいな物づくりは
重要で必要になのだと感じました。 60代女性
もっと多くの方に観て頂きたいと思える素敵な映画だと思います。
今回、二度目でしたが、次の機会があれば又観に来ます。
ありがとうございました。 60代女性
藍について昔からの作り方、染め方、大変参考になった。
芭蕉布 制作工程はもちろん、
沖縄の昔ながらの民家や生活感がとても見れた事が良かった。 60代女性
大雨の中、まよいながら来たのだが
とても心おだやかで美しい作品でした。
ありがとうございます。
喜如嘉へ行ってその風を感じたい。
藍染は男の仕事なんだと思った。 60代女性
平良敏子が亡くなったのは残念です。
後継者が多数いることを願います。
武州藍を初めて知りましたが、とても素晴らしい芸術品ですね。
職人の知恵と技にただただ感心しました。 60代男性
「武州藍」の途中からしか鑑賞できなかったので
もう一度別の機会に上映してほしい。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
毎回見たいと思いました。 60代女性
素晴らしい映画上映をありがとうございました。
平良さんは御自分の使命をまっとうされたのだなぁと感じました。
喜如嘉の芭蕉布が一人の人の想いから
亡ばずに本当に良かったと思いました。
大原様に感謝です。
喜如嘉の芭蕉布を守り、生かしてくださったことに感謝です。
又、アンコール上映されることを願います。 60代女性
芭蕉布を織るのに手数がかかるというのは聞いていたが
これほどだと初めて知る。戦争やいろいろなことで
ほとんどすたれてしまったものが、喜如嘉でまた復興したというのは
ほんとうに奇跡で岡山の紡績工場の社長さんや柳宗悦さんには感謝である。
人間国宝にまでなった平良敏子さんの人となりと今に受け継がれるいしずえと
なった歩みがこの映画を見て知れてほんとうに有意義な時間でした。 60代女性
芭蕉布を守って育てた人々(女性)の生き様に大変感謝しました。 60代男性
昔の人のすばらしさにほんとうにカンプクの一言。
これからもいろいろなものをみてみたいです。 60代女性
平良さんには、ただただ頭が下がる思いです。 60代男性
芭蕉布作り、いろいろ手間などかけていて、すばらしい。
次世代の人々につないでほしい。又、県はもちろん
国などで代々守って欲しい。
武州藍、たくさんの人々の過程、手をかりて、すばらしい。
藍染めができて、すばらしい。これも日本の藍として守ってほしい。
ありがとうございます。 60代女性
喜如嘉にある芭蕉と木灰とシャリンバイから糸が生まれ
紡がれ織られ布になる。生産性向上や付加価値や品質管理はここにない。
あるのは、生活と連帯と感謝。
現代の日本がどこかに置いてきたものがここには全てある。 70代男性
見たい映画たくさんあります。 70代女性
良かったです。 70代男性
時間と労力をかけて紡がれる織の世界。
いつまでも継がれる事を祈るばかり。
平良敏子さんの情熱と村への思いを伝える上映でした。 70代女性
良かったです。
とくに「芭蕉布を織る女たち」は
観ているうちに涙が出てきました。 70代女性
宴会の余興等で着るぐらいしか機会のない芭蕉布でしたが
こんなにも手間ひまかけて布に織りあがるのだと初めて知りました。
ものすごく貴重な布なのですね。
芭蕉の木から布に織りあがるまでの過程がよくわかり感動しました。 70代男性
多くの方の協力で素晴らしい作品が生れてるのがわかりました。 70代女性
たいへん良い映画をありがとうございます。 70代男性
細かい作業や作品が一人一人の思いによって
できあがることを知ってよかたです。 70代女性
手仕事のすばらしさ、作品をみることができてよかったです。
ありがとうございました。 70代女性
若者へ
伝統の芭蕉布をつづける努力、
芭蕉布展をつづけてほしい。 70代男性
芭蕉布、藍染め、どちらもすばらしいですね!
生活の中に取り入れていきたいと思いました。
手間ひまのすごくかかった仕上げのもと
ステキな作品となるのですね。 70代女性
芭蕉布の工程については本も読んでおりましたので
ある程度は知っている心算でしたが、複雑で、気の遠くなるような工程は
予想を遥かに超えていました。このことは、武州藍についても同様です。
ただ、年月日も知りたかったです。
平良敏子さんの若いお姿は何歳位だったのでしょうか。 70代女性
[質問の回答]平良敏子さんの年齢について
平良敏子さんは1921年生まれのようです。『芭蕉布を織る女たち』の
製作年が1981年ですので、59才か60才だと思います。
芭蕉も藍も沢山の工程を経るのですね。
それを苦労っぽくなく、こなして楽しそうにやっていることがすごい。 70代女性
良かったです。
芭蕉布の値段が高いのがわかります。 70代女性
大変すばらしい映画でした。感動です。
喜如嘉の方々、芭蕉布作りを映像でみることが出来
また、映画を作ってくれたことに大変すばらしく、すばらしいことです。
平良敏子さん、芭蕉布をしている方々、とにかくすごいと思います。
上映会に来ることが出来、勉強になりました。ありがとうございます。 70代女性
自然と共に生きる、先人の知恵、
相手とじっくり付き合いながら、ひとつの物を作りあげていくことの喜び
今の時代に大切な事を教えてくれる作品でした。
感動しました。ありがとうございます。 70代女性
「芭蕉布を織る女たち」は以前にも見ましたが
「武州藍」は初めてで、藍の種をまくところから
藍染めができるまで詳しく工程が分かって良かった。
藍は沖縄では日かげか半日かげで栽培されていると聞いているが
日なたで育てているので驚いた。
沖縄の藍と違うのだろうか。 70代女性
[質問の回答]リュウキュウアイは日かげを好みますね。
藍の種類によって違うようです。武州藍のタデアイは
日光を好み日当たりのよい場所で育ててましたね。
武州藍、芭蕉布も、ひとつひとつの工程が
きちんとていねいに行われて布が完成していることがすばらしく、
生活の場と密着していることがよく映像化されていると感じました。
特に喜如嘉の女性達の生き生きとした姿が印象に残った。
今も喜如嘉にひきつがれていると感じる。 70代女性
とても大変なお仕事だと、ご苦労をおもいました。
現代においてずっと続けていく事は困難な作業だと思います。
記録を残すことがどんなに重要なことか、特に映像の力が大きいと思います。 70代女性
11/2に芸大で平良美恵子先生のお話を聞き
芭蕉布の事を初めて知り(県外人なので)映画も初めて見たのですが
びっくりする事ばかりでした。博物館のチラシで平良先生のお話しや
映画会がある事を知り、11/16、11/17と2日は博物館に来ました。
本当に皆さん苦労して文化をつないでこられたのだと頭が下がります。 70代女性
いづれにも共通する事だが
手間ひまが掛かり頭がさがる。
着物が好きで購入もするが、
琉球の伝統工芸は高額で手が出ない。
工程を知ってしまうと納得なのだが… 70代女性
感動致しました。 70代女性
すばらしい映画でした。 70代男性
今回の映画会は大変良かった。
芭蕉布の出来上がり、歴史の重みを感じました。
これからも小さな映画会がますます大きな映画会になりますように。
ありがとうございました。 80代男性
毎回、新たな感動を得ます。
手作業、伝統の奥深さを有難く見せてもらっています。
ありがとうございます。 80代女性
大変すばらしい。
沖縄の世界にほこる、すばらしいと思います。
「バショウ」の衣は、良い物です。
無地でバショウを作り、後であやを入れたらどうかと思いました。 80代男性
芭蕉布が布になるまですごい工程ですね。
昔の年配の人は、着物や洋服で着けていたのを思い出します。
祖母もバサーを洗たくする時は、クニブ(みかん)で洗ってました。
みかんで洗うとそれはきれいに鮮明に汚れも落ちていました。 80代女性
1.2編共大変良かった。
1本づつ上映した方が良かったのではないか。
2.取材時期が分からなかったが、最後に入れるべきと考える。
3.「芭蕉布を織る女たち」では、一着尺にどの程度の芭蕉布が使われ
どの位の時間がかかり、最終的にいくら位で取引されるのかが知りたかった。 80代男性
工芸の素晴らしさを再確認しました。
大変勉強になりました。 80代女性
・知識を広めるためとてもよかったと思います。
・手仕事のきびしさがわかった。
・奥深いきびしさがあることがわかった。 80代女性
こんなに素晴らしい映画を見ることが出来たのは
生涯忘れることが出来ない程感激した。反省するのみ。
平良先生を常に念頭に置き、残された時間を大切に生きたいと思いました。
先生を中心に織られた方達皆さんの
生き(活き)生きした姿をみることができたのも良かったです。 80代女性
芭蕉布工房で若い頃の敏子、美恵子さんのなつかしいお姿。
伝統を守ることのむずかしさ、受け継がれるのも御苦労様です。 80代男性
気の遠くなる程の過程を経て、出来上がる芭蕉布。
根気と愛で出来る布。永らく継承できる事を祈る。 90代女性
〈11月会を振り返って〉
「海燕社の小さな映画会2024」11月会、
ご鑑賞の143名のお客様、ありがとうございました。
「ポーラ伝統文化振興財団」様、「桜映画社」様、ありがとうございました。
「民族文化映像研究所」様、ありがとうございました。
11月会は沖縄県立博物館美術館『芭蕉布展』とのコラボ上映会が実現しました。
おかげさまでお客様に映画を無料でご鑑賞頂けることができました。
「沖縄県立博物館美術館」様、ありがとうございました。
後援の「沖縄県」「那覇市」様、ありがとうございました。
宣伝にご協力下さいましたマスコミのみなさま、ありがとうございました。
SNSや口コミで宣伝下さいましたみなさま、ありがとうございました。
みなさまに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
海燕社の小さな映画会は海燕社が「観たい」「観て欲しい」映画を
一緒に観ませんか、というスタンスで開催している映画会です。
劇場ではなかなか上映されない映像作品や旧作映画を上映しています。
映画の多様性、特にドキュメンタリーの幅広さを知ってもらいたいという気持ちもあります。
2024年の映画会は10年目を記念してご鑑賞者にオリジナル「栞」をプレゼントしています。
4月会は「獅子」5月会は「木」…上映作品に合わせてテーマを決めてデザインしています。
記念品を「栞」にしたのは、私が映画を観る前や観た後に原作本や関連する本を読みたくなるからです。
映画会の思い出とともに読書の時に「栞」を愛用して頂けたらうれしいです。
「海燕社の小さな映画会2024」の11月会は、
『武州藍』『芭蕉布を織る女たち-連帯の手わざ-』(以下『芭蕉布の織る女たち』)の二作品を上映しました。
沖縄初上映作品『武州藍』とアンコール3回目上映作品『芭蕉布を織る女たち』
この二本立を企画した理由を主催者挨拶で話しました。
きっかけは『芭蕉布を織る女たち』です。この作品で私が印象に残った言葉が「藍の花」です。
藍を、花のように見る、人のように思いやる、そこに惹かれました。
藍と藍をつなぐ上映会をしたいと『武州藍』と『芭蕉布を織る女たち』の二本立を決めました。
映像作品は完成後が大事だと思っています。
製作者としては観てもらうこと、観客としては観ること、
その二つを映画に贈りたいです。
「海燕社の小さな映画会」はその一役になって欲しいと願っています。
アンケートの提出して下さった139名様に感謝申し上げます。
アンケートのご協力ありがとうございました。
感想を書いて下さったのは120名様。感想ブログ掲載不可は15名様。
105名のお客様の感想を上記で紹介させて頂きました。
ブログでのお客様全員の感想を紹介する活動を続けています。
海燕社のスタッフだけで読むには惜しい内容の感想ばかりだからです。
映画会に来て下さった皆様と感想を共有したい、
映画製作者のみなさまにお客様の感想を伝えたい、
映画会に来れなかったみなさまに作品について伝えたい、
という思いで感想をブログで紹介しています。
これからも続けます。ご協力をよろしくお願いします。
城間あさみ
Posted by カイエンシャ at 05:41
│海燕社の小さな映画会